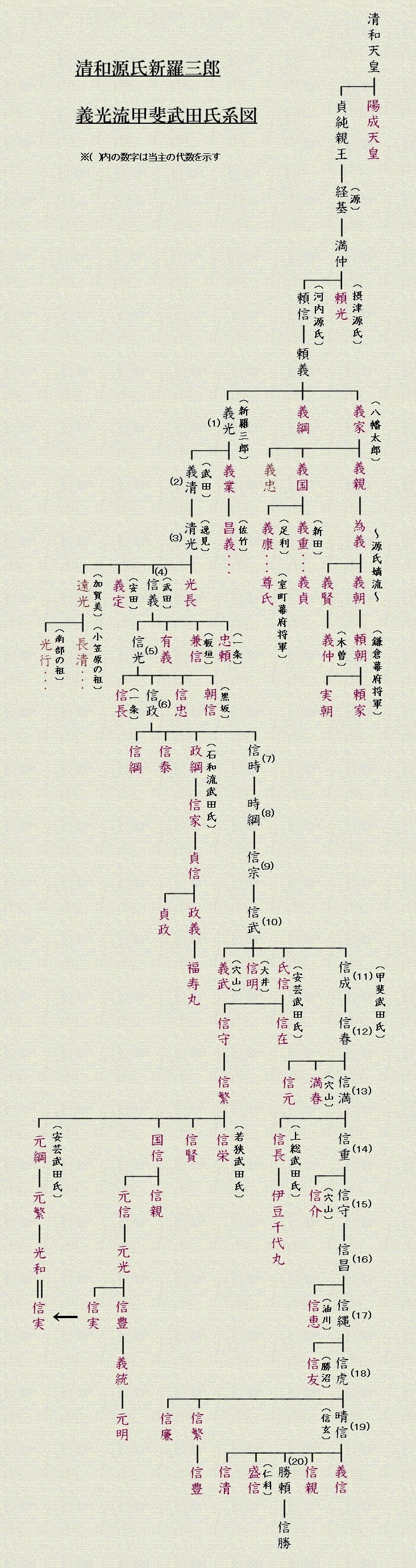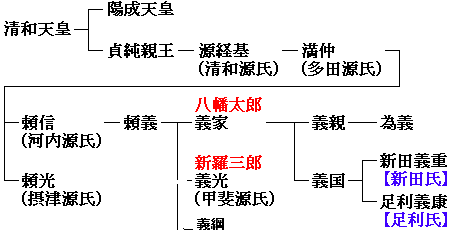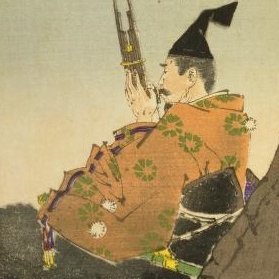「呪われたケネディ一家」を書いて、そうであった、当「牧原家」も呪われた一家であった。
歴史小説家の「柴田錬三郎」の小説『妬心』に当牧原家の初代「牧原直源只右衛門」が登場してくる。
会津藩三代目藩主正容(まさかた)の時、側室を家臣に払い下げるという事件があった。
会津藩三代藩主正容の正室は輿入れ後 2年余で亡くなった。16歳だった。
そこで最初の側室が「お祐」。正容の第一子「お元」を産んだ。女児だった。
その翌年、もう一人の側室「おもん」が男児「正邦」を産んだ。その翌年には「お祐」が男児「正甫」を産んだ。
お世継ぎを巡っての側室同士の確執が始まる。順番から言えば「おもん」が産んだ「正邦」が世継ぎになれるはずだったが、おもんは性格がきつく、正容はおもんを遠ざけ、お祐の方を寵愛した。これに嫉妬した「おもん」は、怒りを露わにし、正容の前で懐剣を抜いて「自害する」と騒ぎたてた。そのことがあって「おもん」は会津に送られ、幽閉される。その「おもん」の子「正邦」は宝永5年(1708)、疱瘡に罹り13歳で夭折した。「おもん」は悲嘆に暮れ、「お祐」に対する憎しみを増していった。「お祐」の産んだ「正甫」が世子となったが、病に臥しがちだった。「これはおもんの怨恨か」との噂もたち、身内の者からの嘆願もあって、「おもん」は17年の幽閉を解かれ、お使番「神尾八之丞」に嫁がされることとなった。しかし、家臣への払い下げという措置に「おもん」はますます反発し、その決定を下したと思われる側用人「杉本源五右衛門」と「牧原只右衛門」を憎んだ。
「おもん」は、屋敷内に祠を造り、毎日その前で手を合わせ呪詛するのが日課となった。柴田錬三郎の小説『妬心』では、「その結果、杉本、牧原の両家は断絶したと」なっている。
柴田錬三郎はこの事件をどこから調べたのだろうか。伯父から聞いた話では、「側室の呪詛によって、牧原家は7代に亘って男児は長生きしない」という言い伝えは、わが家にあったという。私は子供の頃それを聞いて、自分も長生きはできないかという思いがずっとつきまとっていた。しかし、もう7代は過ぎ、伯父も父も80過ぎまで長生きした。
柴田錬三郎の『妬心』は 昭和45年にテレビドラマにもなった。ネットで検索すると出てきた。
1970年(S45)の時代劇シリーズ『徳川おんな絵巻』の第7回。会津藩三代目藩主 正容(まさかた)の時に起きた「拝領妻」事件のドラマ化。登場人物は実名ではなく名前が変えられていて、側室「おもん」は「お葉」に、当家の先祖「牧原只右衛門」は、「只左衛門」と「右、左」を取り替えられていた。
『お妾拝領仕る』(前編) 放送日=1970.11.14
嫁地獄(後編) 1970.11.21
【スタッフ】監督=倉田準二、脚本=野上龍雄
【キャスト】中村玉緒(お綾の方)、天知茂(神尾新八郎)、
中原早苗(お葉の方)、葉山良二(藩主:保科正容)、
安部徹(牧原只左衛門)、杉村春子(語り手)