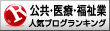アセスメントが苦労するようで「アローチャート」とか「スター理論(古い?)」「タイ方式」やら、加えセンター方式に竹内理論にICF、スパイラル方式なんてのも、もうなんだか、どれがいいのか、どれを使ったらいいのか、わかりません。それほどアセスメントが混乱していることなのでしょう。
で、基本は標準課題分析項目は23項目ですから、まずはこの項目について確認にすればいい。それも一度でできなければ数回にわたることもあるだろう、要は23項目を確認する。聞く、観る、診る、触れることで、時間をかけて、聴取。
問題は次の作業で、聴取したなかで気になること、言葉に限らず、その時に限って早口・小声・低い声・高い声・言いよどむといった口調動作や目の動き、手足の動き、そわそわの動きで気になることはなんだろうと考えみたい。そこになにかが潜んでいないか、と思う。そして「なぜ」です、「なぜ」ヘルパーにこだわる、「なぜ」サービスを利用しない、「なぜ」外出しない、「なぜ」「なぜ」「なぜ」です。「なぜ」から浮かび上がるイメージ、もしかしたらそこに回答がある、か。
そして「できる動作」「している動作」の差、があるでしょうか。「できる動作」は本当はできるはずなんだけど、と思う専門家の意見、「している動作」はとはいまその本人がしている動作そのもの、で、その落差があるのか、なにのか。あれば専門家の意見としてはできるわけですから、できない理由があるはず、です。また、ここに解決の糸口があるかもしれません。
要は情報を取得するのが目的ではなく、そこがアセスメントの終わりではなく、ここから「考える」ことが始まり、で、アセスメントとは「心を寄り添えて」とか「心に響く」とかにあるのではないと、そこからが始まり。
目的は「なぜ」だろう、「そうか」そういうことか、をつかみたい、です。
で、基本は標準課題分析項目は23項目ですから、まずはこの項目について確認にすればいい。それも一度でできなければ数回にわたることもあるだろう、要は23項目を確認する。聞く、観る、診る、触れることで、時間をかけて、聴取。
問題は次の作業で、聴取したなかで気になること、言葉に限らず、その時に限って早口・小声・低い声・高い声・言いよどむといった口調動作や目の動き、手足の動き、そわそわの動きで気になることはなんだろうと考えみたい。そこになにかが潜んでいないか、と思う。そして「なぜ」です、「なぜ」ヘルパーにこだわる、「なぜ」サービスを利用しない、「なぜ」外出しない、「なぜ」「なぜ」「なぜ」です。「なぜ」から浮かび上がるイメージ、もしかしたらそこに回答がある、か。
そして「できる動作」「している動作」の差、があるでしょうか。「できる動作」は本当はできるはずなんだけど、と思う専門家の意見、「している動作」はとはいまその本人がしている動作そのもの、で、その落差があるのか、なにのか。あれば専門家の意見としてはできるわけですから、できない理由があるはず、です。また、ここに解決の糸口があるかもしれません。
要は情報を取得するのが目的ではなく、そこがアセスメントの終わりではなく、ここから「考える」ことが始まり、で、アセスメントとは「心を寄り添えて」とか「心に響く」とかにあるのではないと、そこからが始まり。
目的は「なぜ」だろう、「そうか」そういうことか、をつかみたい、です。