都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」 細見美術館
細見美術館(京都市左京区岡崎最勝寺町6-3)
「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」
9/22-12/16
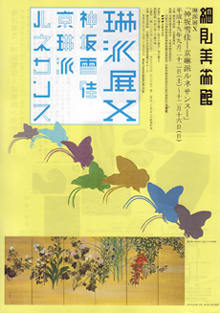
日本橋高島屋で見た展示の記憶がまだはっきりと残っています。明治より昭和にかけて京都で活躍し、主に光悦や光琳らの京の琳派を装飾芸術として復興させた(ちらしより引用。一部改変。)、神坂雪佳(1866-1942)の回顧展です。絵画、染物、陶器、それに図案など、全100点以上の作品にて雪佳の活動を辿ります。

上に挙げた「四季草花図屏風」など、まさに琳派の王道を往く絵画にも雪佳の魅力がありますが、やはり彼の真骨頂はデザイナーとしての活動にあるのだと思います。実際、雪佳は京都市立美術工芸学校の教諭をつとめた上、理想とする工芸をつくるべく「佳美会」という組織もつくり、琳派の図案、装飾の研究活動に勤しんでいました。この展示でも様々な文物にて、そのような雪佳のデザイナーとしての制作を知ることが出来ます。順路でいうと、ちょうど後半部分、「生活を彩る - 工芸図案家として - 」と「意匠・図案 - 雪佳デザインの世界 - 」です。

高島屋での展示の印象と重なってしまいますが、雪佳の画、清水六兵衛作による器が大変に魅力的です。朱に燃える赤樂に夕焼けの白波を大胆なデフォルメで描いた「波の図 赤樂茶碗」と、まるで豆のような形をした皿に流水紋を緩やかに配した「水の図 向附皿」はいつ見ても惹かれる良さを感じます。ともに仰々しさのない、素朴とも言えるデザインが、普段、日常で使いたくなるような親しみ易さも演出しているようです。
雪佳の制作が室内装飾はおろか、作庭にまで及んでいたとは知りませんでした。また大正4年の光琳200回忌には、雪佳図案による道具類がいくつも制作されていたのだそうです。そもそも雪佳は琳派の中でも光悦と光琳に大変な思いを寄せていますが、この辺の行は同じく光琳に傾倒していた抱一のそれを伺わせるものがあります。私淑のみで繋がり行くという、琳派ならではの独特の結びつきです。
もちろん高名な「金魚玉図」も展示されています。実際は、丸く吊るした鉢の中で金魚が泳ぐ様を描いたものですが、どう見ても金魚が月から降りてくる、さながら金魚来迎図とも言えるような作品に思えてなりません。微笑ましく、また意匠に斬新なこの作品は、もはや近代の琳派の代表作としても位置付けられるのではないかと感じました。
作品の数割が入れ替わっています。12月16日までの開催です。(10/26)
「神坂雪佳 - 京琳派ルネサンス - 」
9/22-12/16
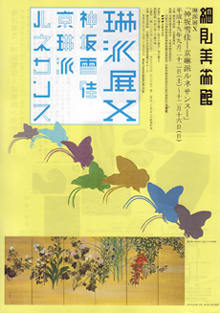
日本橋高島屋で見た展示の記憶がまだはっきりと残っています。明治より昭和にかけて京都で活躍し、主に光悦や光琳らの京の琳派を装飾芸術として復興させた(ちらしより引用。一部改変。)、神坂雪佳(1866-1942)の回顧展です。絵画、染物、陶器、それに図案など、全100点以上の作品にて雪佳の活動を辿ります。

上に挙げた「四季草花図屏風」など、まさに琳派の王道を往く絵画にも雪佳の魅力がありますが、やはり彼の真骨頂はデザイナーとしての活動にあるのだと思います。実際、雪佳は京都市立美術工芸学校の教諭をつとめた上、理想とする工芸をつくるべく「佳美会」という組織もつくり、琳派の図案、装飾の研究活動に勤しんでいました。この展示でも様々な文物にて、そのような雪佳のデザイナーとしての制作を知ることが出来ます。順路でいうと、ちょうど後半部分、「生活を彩る - 工芸図案家として - 」と「意匠・図案 - 雪佳デザインの世界 - 」です。

高島屋での展示の印象と重なってしまいますが、雪佳の画、清水六兵衛作による器が大変に魅力的です。朱に燃える赤樂に夕焼けの白波を大胆なデフォルメで描いた「波の図 赤樂茶碗」と、まるで豆のような形をした皿に流水紋を緩やかに配した「水の図 向附皿」はいつ見ても惹かれる良さを感じます。ともに仰々しさのない、素朴とも言えるデザインが、普段、日常で使いたくなるような親しみ易さも演出しているようです。
雪佳の制作が室内装飾はおろか、作庭にまで及んでいたとは知りませんでした。また大正4年の光琳200回忌には、雪佳図案による道具類がいくつも制作されていたのだそうです。そもそも雪佳は琳派の中でも光悦と光琳に大変な思いを寄せていますが、この辺の行は同じく光琳に傾倒していた抱一のそれを伺わせるものがあります。私淑のみで繋がり行くという、琳派ならではの独特の結びつきです。
もちろん高名な「金魚玉図」も展示されています。実際は、丸く吊るした鉢の中で金魚が泳ぐ様を描いたものですが、どう見ても金魚が月から降りてくる、さながら金魚来迎図とも言えるような作品に思えてなりません。微笑ましく、また意匠に斬新なこの作品は、もはや近代の琳派の代表作としても位置付けられるのではないかと感じました。
作品の数割が入れ替わっています。12月16日までの開催です。(10/26)
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )










