 東大寺の二月堂は「お水取り」の儀式が行われる堂宇として有名で、その舞台となる二月堂へ初めての拝観が叶いました。
東大寺の二月堂は「お水取り」の儀式が行われる堂宇として有名で、その舞台となる二月堂へ初めての拝観が叶いました。「お水取り」は福井県小浜市にある「神宮寺」の閼伽井で汲まれた水が小浜の鵜ノ瀬という川に流され、その水が奈良東大寺の二月堂の閼伽井にまで通じているという伝説による儀式です。
お水取りはTVでしか見たことはありませんが、大きな松明の火花を懸け造りの二月堂の上から散らしたりする珍しくも豪快な儀式だと記憶します。
福井県小浜市と奈良市はかつて渡来人の文化や経済が流通した経路といわれ、「お水送り」「お水取り」はその象徴的な儀式といえるのかもしれません。
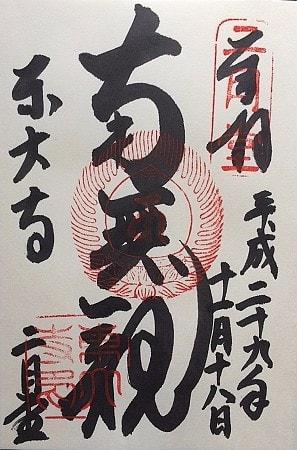


『二月堂』
奈良公園の中に「二月堂参詣道」の石標が建ち、その道の先に二月堂への石段が見えてきます。
TVで見る“懸け造りの建築の上段で松明の火花が散る”「お水取り」の二月堂とはどんな堂宇なんだろうと期待が高まります。


しかし東大寺は山の上にある山寺ではないのになんでこんなにガスっているのでしょうか。
“全てが霧に包まれるような寺院”と誤った認識をしてしまいそうですよ。

堂内へは石段を登って入ることになりますが、平地に立地する東大寺ではここは数少ない石段でした。
人が溢れている金堂(大仏殿)と比べると、人は格段に少なくなり落ち着いて境内を歩くことが出来ます。
ただし、東大寺は広い境内に堂宇が散在していますので、全てを見て回るには時間に余裕がないと巡れそうになさそうです。

石段を登ると正面に手水舎があります。お香水を儀式に使う堂宇ですから手水舎も立派な造りになっています。
この龍は吐水こそしてはいませんが、龍玉を握った大きく立派な龍でした。

二月堂は1180年と1567年の兵火には焼け残ったものの、1667年の「お水取り」の最中に失火により焼失。
しかしその2年後の1669年に再建されて現在に至り、建物は国宝に指定されています。
「お水取り」の行事はTVなどで見ていても“類焼しないのかな?”と思うことがありますが、再建後350年に渡って火災は発生していないようですね。

「お水取り」行事に欠かせないのが『閼伽井屋』ではないでしょうか。
閼伽井屋のお香水は福井県小浜市にある神宮寺の閼伽井屋で汲まれた水が遠敷川鵜ノ瀬から「お水送り」として流され、10日間かかって二月堂の閼伽井(若狭井)へ流れ着くという謂われがあります。
日本海に面して大陸・朝鮮半島の窓口だった小浜と当時の都・奈良との深いつながりが伺い知れる謂われです。

『法華堂(三月堂)』
東大寺には2月堂の他にも3月堂(法華堂)・四月堂(三昧堂)と月の名の付いた堂宇が同じエリアに並んでいました。
三月堂は、東大寺建築のなかで最も古く、寺伝では東大寺創建以前にあった金鍾寺(きんしょうじ)の遺構とされているとされます。
この三月堂は正堂と礼堂から成り、正堂は天平時代の建築。礼堂は鎌倉時代に建立されたもので、鎌倉時代の改築の際に2つの堂をつないだとされています。
正面になる礼堂から入りましたが、中に祀られている仏像は奈良時代の素晴らしい仏像が安置されておりました。


まず圧倒的な迫力と美しさの「不空羂索観音(像高362cm・国宝)」に目を奪われます。
あっと声をあげたまま壁側にあった座敷に座り、ひとしきり眺めてしまいました。

須弥壇に安置されている仏像は全て奈良時代の国宝仏ばかりです。
本尊の「不空羂索観音」の横には脇侍にあたる「梵天(像高402cm)」と「帝釈天(像高403cm)」。
四隅を守護するのは「持国・増長・広目・多聞の四天王立像」で、正面には「阿吽の金剛力士像」が門を構えており、観音様を万全の守護で守っています。

奈良仏は平安仏のデフォルメされた仏像や鎌倉時代のリアリズムの仏像とは違った、ある意味シンプルで素朴な仏像との印象を感じるものもありましたが、本尊の不空羂索観音のあの美しさはいったい何なんだと思うほど素晴らしい仏像でした。
やはり奈良の寺院・仏像には日本仏教始りの地ゆえの見所があり、法華堂(三月堂)へ行ってよかったとの感が深まる寺院でした。
『三昧堂(四月堂)』
「三月堂(法華堂)」は旧暦3月に法華会が行われることから三月堂と呼ばれるようですが、「四月堂(三昧堂)」は法華三昧会が旧暦4月におこなわれることから四月堂と呼ばれるようになったといいます。
御本尊は十一面観音立像(平安末期)と脇侍が安置されていました。
かつては千手観音像が本尊として祀られていたようですが、現在その仏像は東大寺ミュージアムへ移動してしまい、代わりに祀られたのが現在の御本尊だそうです。
東大寺ミュージアムへ行く時間がなくて拝観出来なかった「千手観音立像」は写真で見ても凄い仏像でしたので少し悔いが残ります。

『東大寺梵鐘』
東大寺金堂(大仏殿)は何もかもが巨大でしたが、梵鐘も信じられないような大きさです。
東大寺を去る最後に鐘楼へと立ち寄りました。

鐘楼は鎌倉時代に再建された建築物で国宝に指定されており、単層の鐘楼としては大きな建築物となっています。
それもそのはずで梵鐘は高さ3.86m、口径2.71m、重量26.3tと桁外れの大きさの梵鐘です。
撞木も長さ4.48m、直径30cm、重量200Kgと特大サイズですので、大晦日の除夜の鐘の時には8名が組になって綱を引いて鐘を撞くそうですね。
東大寺が建立された時代には巨人族が跋扈していたのか?と思えてしまうような寺院ですね。


奈良へは遥か昔に小学校の旅行や観光バスツアーでしか行ったことがないのですが、参拝してみたい寺院が有名寺院だけでもいくつもあります。
また有名寺院でなくても仏教の盛んだった土地には“こんな寺院があったのか!”と驚くような寺院がある事がありますから、出来たら宿泊していろいろな寺院を巡ってみたいものです。
















