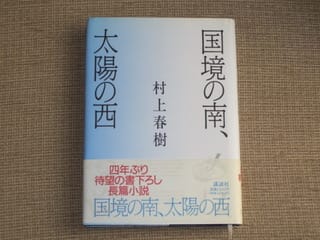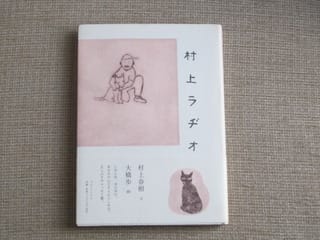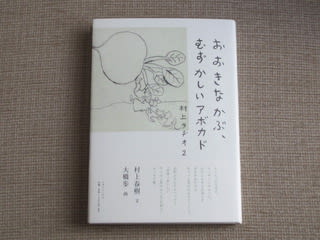ロバート・B・パーカー/菊池光=訳 1990年 ハヤカワ・ミステリ文庫版
順に読み返してるスペンサーシリーズだけど。
こないだ読んだ「レイチェル・ウォレスを捜せ探せ」(※2019年1月修正)の次が、かの「初秋」で、そのつぎが「残酷な土地」。
そのふたつについては、前にこのブログには書いたから、こんどの順番は、これ。
今回のスペンサーの仕事は、人探し。家出した女子高生探し。家出して売春してる女子高生。
誰の依頼だかよくわかんない感じで、父親は娘をもう家には入れないって言ってるし、母親は見つけてほしいんだけど、どうしていいか分からず混乱してる。高校のカウンセラーをしてるスーザンが、どうやら一番熱心に、彼女をみつけて保護すべきと思ってる。
で、スペンサーのことだから、例によって、その女の子を見つけるのはいいんだけど、本人が望まないならムリに家に帰そうとはしない。
依頼人の当初のリクエストにただ従うんぢゃなくて、自分の信念を大事にするから、ロクでもない家庭に戻すくらいなら、戻してもまた家出すんのは明白だし、少女本人が少なくとも今よりマシな環境におかれてマシな生き方するにはどうしたらいいか考えちゃう。
ちなみに、スーザンのほうも簡単な人間ぢゃなくて、全部をスペンサーに任せっぱなしにはしない。事件を追ううちにスペンサーは裏社会の悪党たちから脅迫を受けてるんだけど、巣窟に踏みこむときにスーザンは自分も行くという。「きみは直接かかわってはいけない。」っていうスペンサーに対して、スーザンは「あなたは、わたしの意に反してわたしを守る権利はないのよ。わたしには、自分の正義感と信念に基づいて行動する権利があるわ」と主張する。スペンサー曰く「たまげた科白だな」
どうでもいいけど、今回読み返して、チェックした箇所。
>私は、彼女が帰るか、自分が帰る時、いつもチラッと悲しみを覚える。たとえほんのしばしの別れであっても。明日会うとわかっている時ですらも。たぶん、それで新鮮な感じが続くのだろう。しょっちゅう一緒にいたら、お互いに頭がおかしくなるかもしれない。いや、おかしくなるはずだ。互いにそれぞれ住まいと仕事をもっていて、会いたい時に会う方がいい。
うん、そういうのが、いい。最初読んだときのことなんか憶えてないけど、けっこう影響受けてるのかも。

順に読み返してるスペンサーシリーズだけど。
こないだ読んだ「レイチェル・ウォレスを捜せ
そのふたつについては、前にこのブログには書いたから、こんどの順番は、これ。
今回のスペンサーの仕事は、人探し。家出した女子高生探し。家出して売春してる女子高生。
誰の依頼だかよくわかんない感じで、父親は娘をもう家には入れないって言ってるし、母親は見つけてほしいんだけど、どうしていいか分からず混乱してる。高校のカウンセラーをしてるスーザンが、どうやら一番熱心に、彼女をみつけて保護すべきと思ってる。
で、スペンサーのことだから、例によって、その女の子を見つけるのはいいんだけど、本人が望まないならムリに家に帰そうとはしない。
依頼人の当初のリクエストにただ従うんぢゃなくて、自分の信念を大事にするから、ロクでもない家庭に戻すくらいなら、戻してもまた家出すんのは明白だし、少女本人が少なくとも今よりマシな環境におかれてマシな生き方するにはどうしたらいいか考えちゃう。
ちなみに、スーザンのほうも簡単な人間ぢゃなくて、全部をスペンサーに任せっぱなしにはしない。事件を追ううちにスペンサーは裏社会の悪党たちから脅迫を受けてるんだけど、巣窟に踏みこむときにスーザンは自分も行くという。「きみは直接かかわってはいけない。」っていうスペンサーに対して、スーザンは「あなたは、わたしの意に反してわたしを守る権利はないのよ。わたしには、自分の正義感と信念に基づいて行動する権利があるわ」と主張する。スペンサー曰く「たまげた科白だな」
どうでもいいけど、今回読み返して、チェックした箇所。
>私は、彼女が帰るか、自分が帰る時、いつもチラッと悲しみを覚える。たとえほんのしばしの別れであっても。明日会うとわかっている時ですらも。たぶん、それで新鮮な感じが続くのだろう。しょっちゅう一緒にいたら、お互いに頭がおかしくなるかもしれない。いや、おかしくなるはずだ。互いにそれぞれ住まいと仕事をもっていて、会いたい時に会う方がいい。
うん、そういうのが、いい。最初読んだときのことなんか憶えてないけど、けっこう影響受けてるのかも。