岡野友彦 2003年 講談社現代新書
きのうまでとは何の関係もなく、最近読んだ本の話。
そもそもこれは、『落語の国からのぞいてみれば』で、堀井憲一郎が参考文献として挙げているところから、読んでみようと思った。
そのホリイ氏の著書には「名前は個人のものではない」という章があって、名前に関する本をいろいろ読んだようで、私もそこに挙げられてた『読みにくい名前はなぜ増えたか』を読んだりしたんだけど、
>この分野で圧倒的に面白かった一冊は岡野友彦のこれ。すごく面白かった。これと同じ講談社現代新書に入れるだけで光栄だ。
とまで言われては、こちらも読まないわけにはいかない。
ところが、そう思ったときには、どうやらこの本、絶版らしいってことがわかった。
ネット上で中古を探せばあるんだろうが、それぢゃおもしろくないので、これについては、自分の足で探すことにした。
べつに急ぐ必要もないし、運だけが頼りで、古本屋を見かけるたびに新書の並んだとこでタイトルをジーッと見て探す日々が続いた。
なかなか見つかんなかったんだけど、先日とうとうあるところで見つけることができた。意外と近いとこだったんで、とっくに来りゃあよかったのにとは思ったけど、まあ、探し物って、そういうもんである。
んで、私の古本屋めぐりはいいとして、本書のなかみなんだけど、冒頭の“はしがき”の最初に「征夷大将軍という地位は、日本の国家主権を示すものではなかった」ってことが、いきなり強調したいテーマとして書いてある。
“足利家は源氏だから将軍になれたけど、織田信長は違うからなれなかった”とか、“徳川家康は将軍になりたいから源氏になった”とかってのは、ちょっと違うよって話。
ただの将軍ぢゃなくて「日本国王」ってのになるためには、「源氏長者」というポジションになんなきゃいけない。家康は将軍職を秀忠に譲ったあとも、源氏長者の地位にありつづけたんで、実質上の「日本国王」は家康だったということらしい。
まあ、いろいろややこしいんだけど、「武家が日本の政権を獲ったんだったら、なんで天皇を滅ぼしちゃわなかったんだろう?」ってのは、日本史の重要なテーマだよね。
中沢新一の『僕の叔父さん 網野善彦』にも、生徒にそう訊かれて、律義に悩む網野善彦の姿が書かれてたけど、これに明快に答えるのは難しい。
どーでもいーけど、“織田信長や豊臣秀吉は、源氏ぢゃないから将軍になれなかったのではなく、将軍になろうとはしなかった。なぜなら、彼らの目標は、中国から一地方を治めることを命ぜられる「日本国王」になることぢゃなくて、中華皇帝そのものになることだったから”ってのは、いいね。ちょうど今私は『へうげもの』を読んでて、そういうくだりを半信半疑で楽しんでるもんで。
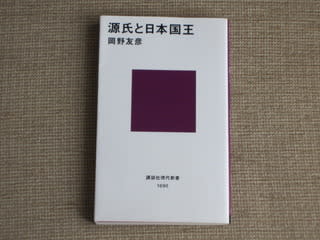
きのうまでとは何の関係もなく、最近読んだ本の話。
そもそもこれは、『落語の国からのぞいてみれば』で、堀井憲一郎が参考文献として挙げているところから、読んでみようと思った。
そのホリイ氏の著書には「名前は個人のものではない」という章があって、名前に関する本をいろいろ読んだようで、私もそこに挙げられてた『読みにくい名前はなぜ増えたか』を読んだりしたんだけど、
>この分野で圧倒的に面白かった一冊は岡野友彦のこれ。すごく面白かった。これと同じ講談社現代新書に入れるだけで光栄だ。
とまで言われては、こちらも読まないわけにはいかない。
ところが、そう思ったときには、どうやらこの本、絶版らしいってことがわかった。
ネット上で中古を探せばあるんだろうが、それぢゃおもしろくないので、これについては、自分の足で探すことにした。
べつに急ぐ必要もないし、運だけが頼りで、古本屋を見かけるたびに新書の並んだとこでタイトルをジーッと見て探す日々が続いた。
なかなか見つかんなかったんだけど、先日とうとうあるところで見つけることができた。意外と近いとこだったんで、とっくに来りゃあよかったのにとは思ったけど、まあ、探し物って、そういうもんである。
んで、私の古本屋めぐりはいいとして、本書のなかみなんだけど、冒頭の“はしがき”の最初に「征夷大将軍という地位は、日本の国家主権を示すものではなかった」ってことが、いきなり強調したいテーマとして書いてある。
“足利家は源氏だから将軍になれたけど、織田信長は違うからなれなかった”とか、“徳川家康は将軍になりたいから源氏になった”とかってのは、ちょっと違うよって話。
ただの将軍ぢゃなくて「日本国王」ってのになるためには、「源氏長者」というポジションになんなきゃいけない。家康は将軍職を秀忠に譲ったあとも、源氏長者の地位にありつづけたんで、実質上の「日本国王」は家康だったということらしい。
まあ、いろいろややこしいんだけど、「武家が日本の政権を獲ったんだったら、なんで天皇を滅ぼしちゃわなかったんだろう?」ってのは、日本史の重要なテーマだよね。
中沢新一の『僕の叔父さん 網野善彦』にも、生徒にそう訊かれて、律義に悩む網野善彦の姿が書かれてたけど、これに明快に答えるのは難しい。
どーでもいーけど、“織田信長や豊臣秀吉は、源氏ぢゃないから将軍になれなかったのではなく、将軍になろうとはしなかった。なぜなら、彼らの目標は、中国から一地方を治めることを命ぜられる「日本国王」になることぢゃなくて、中華皇帝そのものになることだったから”ってのは、いいね。ちょうど今私は『へうげもの』を読んでて、そういうくだりを半信半疑で楽しんでるもんで。
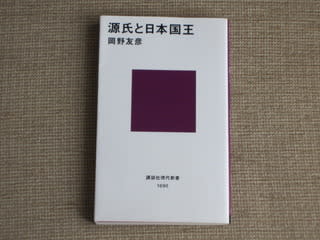










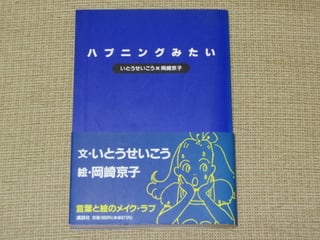
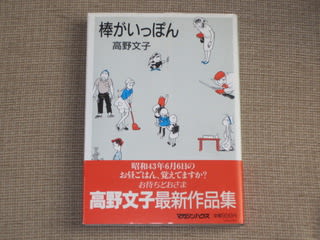


 もうホント早朝練習に切り替えたほうがいいかもしんない。暑いよ。
もうホント早朝練習に切り替えたほうがいいかもしんない。暑いよ。
 いや、ポクポクと急がせもせず森林を散歩するんだったらいいんだろうけど、ほらね、やっぱビシバシとやることあるわけだ、課題山積みの私には。
いや、ポクポクと急がせもせず森林を散歩するんだったらいいんだろうけど、ほらね、やっぱビシバシとやることあるわけだ、課題山積みの私には。






