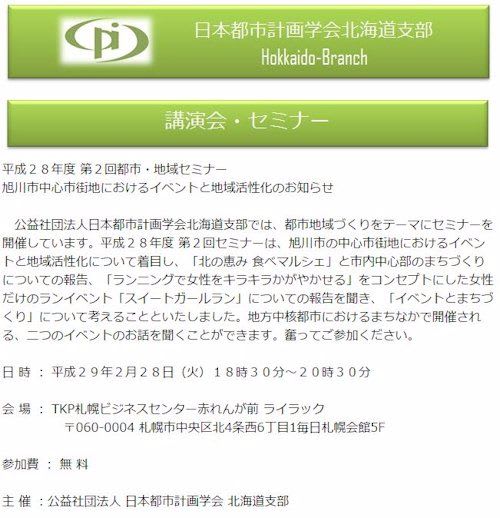今日も友人と一緒にワカサギ釣りに出かけました。
「最近ブログで良くワカサギ釣りの記事を読みますが、だいぶワカサギ釣りにはまっていますね」と言われるようになりました。
まあ今年の冬は、特にワカサギ釣りを楽しんでいますが、私自身の楽しみは、釣りの釣果よりもワカサギ釣りのポイントを知ることの方が楽しいと思っています。
今まで見慣れた場所でも、ワカサギ釣りとして訪れると、それまでと同じ場所なのに全く違う視点と楽しみが得られます。
そのことの方をずっと楽しいと思っているので、できるだけ新しい釣りのポイントへ行きたいと考えているのです。
そんなわけで、今日もワカサギ釣りのために訪れたのは、定山渓スキー場に至る道路の途中で左に広がる札幌湖でした。ここは、定山渓ダムによるダム湖で、札幌市の水がめとして札幌市民の生活を支えているのですが、ここが実に良いワカサギ釣りのポイントなのです。

案内をしてくれた友人は、「休日は駐車場に入れなくなる恐れがあるので早出しましょう」ということで、朝5時半に友人をピックアップして、一路札幌湖へ。
ところが札幌湖へ向かう朝里峠への道路は、冬季は夜7時から朝7時までが通行止めとなります。そこで多くの釣りファンたちは、朝7時の道路開門を目指して早くからゲートの前に集まります。
私たちも6時半くらいに到着したのですが、すでに30台ほどの車が先行して待っている状態。皆さん熱心ですねえ。

朝7時ちょうどの通行止めが融けてゲートが開くと、待ちかねた車たちが動き出します。
我々は第三展望台のところで車を止めて釣りの準備。とりあえず駐車場に入ることができて良かったのですが、車を止めた皆さんは次々に要した道具を準備してどんどん凍った湖面へと向かってゆきます。
皆さんこの場所に来慣れた様子に見えます。私たちのような素人とはちょっと違いますね。

我々もソリに道具を積んで湖面へと降りてゆきますが、およそ三段になっているダムののり面がとても急な難所になっています。
一緒に行った友人は、「降りるのはまだいいんです。でも帰りにこの急斜面を上るのが大変なので、できるだけ荷物は少ない方が良いんです」と教えてくれて、おまけに彼はスノーシューを履いています。
なるほど急な斜面を荷物を携えて上り下りすのが大変なのが、この札幌湖釣りポイントの特徴です。ソリに荷物を積んで慎重に降りてゆきます。


湖面につくと場所を定めてドリルで穴をあけ、その上にテントを張ります。湖面へ到着して、釣り糸を垂らすころには8時を過ぎていました。

さて、やっとのことで釣り始めてみましたが…、うーん、釣れないことはありませんが結構渋めです。
ワカサギのたまっている深さ、いわゆる棚は水深20メートルほどの湖底で、これでは釣るのに電動リールは欠かせませんし、今回は大いに威力を見せつけてくれました。
さて釣れ具合の方は、妻の釣る穴が良く釣れて、私も途中から調子が上がりましたが、昼頃からはパタッと釣れなくなりました。
それでも札幌湖のワカサギは、大きさがほぼ9センチほどで大きさにむらがありません。ポロト湖では5センチくらいの小さなワカサギが多かったので、そこに比べると、とても大きく感じます。
この大きさで全体に揃っているのがこの湖の特徴で、これならば食べてもとてもおいしそうです。
◆
お昼を過ぎて、釣れなくなったところで外に出てみましたが、吹雪模様の天気にもなって雪が降ってきました。
またキタキツネが一匹、釣り人のテントの間をうろついているも見えました。釣り人から餌をもらったり、余った魚などがもらえるという事を学習したのでしょうか。
夕方4時くらいまで釣り続けて、我々は夫婦で約60匹。一緒に行った友人は80匹を釣ったと言いますから、やはり腕の差ってあるんですね。

ところが帰る段になって、来るときは難なく下ってきた斜面を重たいそりを引きながら上がることの苦しさたるや、本当にしんどいものでした。
長靴に装着するスパイクがあったからまだ良かったようなものの、なければ滑ってしまって上がることができなかったでしょう。
それに斜面の長いこと長いこと。これほど息を切らせたことって、近年記憶にないほどです。上りきった時には本当にぐったりしてしばらく動けませんでした。
これを十分に知ったうえで、なお釣れるワカサギの魅力に惹かれる人が多いのでしょう。本当に魅力あるワカサギポイントであることがよくわかりました。
◆
家に帰ってから、今日のワカサギは全部唐揚げにしてビールとワインのおつまみに。大きさが手ごろで食べた時のボリューム感も結構なものですし、味は淡白で実にうまい! あっという間に妻と私の胃の中に納まってゆきました。

なるほど、ここのワカサギを食べると、小さかったり味が劣るようなところでの釣りは興味が失せてしまうかもしれません。それほど、食べるのには適したサイズに違いありません。
ようやく来ることができた札幌湖のポイント。釣りの魅力、札幌の魅力をまた一つ手にした思いです。