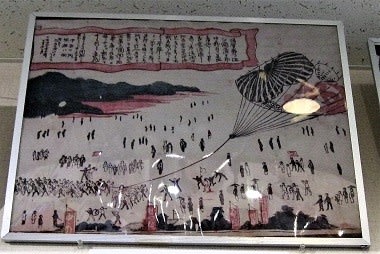アケビの葉が少し変です。
たたまれたような感じになっている葉があります。
(白く光っているのは雨の粒です。)
よく見たら茎に1つ2つ赤い小さな点が見えました。
病気でしょうか、それともダニでしょうか、
じっと見ていたら、素早く動いたのでびっくりしました。

息子に訊いたら、
それは多分セミやウンカの仲間だとおもうよ、
と言いながら写真に撮ってくれました。
(私のカメラでは撮れない)
セミそっくり!
1~2ミリサイズの真っ赤な体で、
目の大きいセミです。


ネットで調べてみたところ、
名前は「ベニキジラミ」という名の昆虫だということが分かりました。
カメムシ目キジラミ科で、
名前はシラミでもシラミとは全然違います。
(ちなみに、セミはカメムシ目セミ科)
アケビの茎の汁を吸ってアケビの葉を折りたたんで中に卵を産み、
アケビの葉の中で幼虫になる、
アケビで生きている昆虫なのだそうです。

閉じた葉を開いてみたら、
白い粉のようなのが、
卵なのか幼虫なのか小さすぎてわかりません。
幼虫は甘露を分泌し、
アリがその甘露を食べにくるそうです。
アブラムシとアリの関係と同様に、
ベニキジラミもアリと共生関係にあるのかもしれません。
たたまれたような感じになっている葉があります。
(白く光っているのは雨の粒です。)
よく見たら茎に1つ2つ赤い小さな点が見えました。
病気でしょうか、それともダニでしょうか、
じっと見ていたら、素早く動いたのでびっくりしました。

息子に訊いたら、
それは多分セミやウンカの仲間だとおもうよ、
と言いながら写真に撮ってくれました。
(私のカメラでは撮れない)
セミそっくり!
1~2ミリサイズの真っ赤な体で、
目の大きいセミです。


ネットで調べてみたところ、
名前は「ベニキジラミ」という名の昆虫だということが分かりました。
カメムシ目キジラミ科で、
名前はシラミでもシラミとは全然違います。
(ちなみに、セミはカメムシ目セミ科)
アケビの茎の汁を吸ってアケビの葉を折りたたんで中に卵を産み、
アケビの葉の中で幼虫になる、
アケビで生きている昆虫なのだそうです。

閉じた葉を開いてみたら、
白い粉のようなのが、
卵なのか幼虫なのか小さすぎてわかりません。
幼虫は甘露を分泌し、
アリがその甘露を食べにくるそうです。
アブラムシとアリの関係と同様に、
ベニキジラミもアリと共生関係にあるのかもしれません。