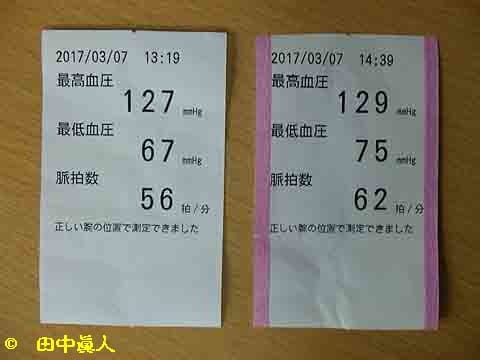晩飯を一人で喰うことはたんまにある。
年に一度か、それとも・・・。
そんなときには決めていたお気に入りの惣菜を狙う。
スーパーに出かけることは週に2、3度ある。
多い時には4度になることもある。
行き先々のスーパーに立ち寄ることも多い。
必ずといっていいほど目を通すのは惣菜売り場。
買ってすぐに食べることができるデキアイの商品。
冷凍もんではなくお店の人たちが作っている調理もんである。
惣菜にはフライもんや天ぷらもんもある。
晩食は飯を喰わないから弁当類は買わない。
飯は飯でも酢飯は美味い。
酒の肴に寿司の味は魅力的だ。
ただ、どうしても腹に堪える。
晩食に飯を喰わなくなったのは何時のころか。
もう何十年も前になる。
結婚したてのころは喰っていたような気がする。
それがいつしか言いわけを作った。
晩食にビールや酒はつきもの。
それがなけりゃ一日の〆にはならない。
ビジネスマン時代はツレらと飲み会。
仕事を終えてちょっと行こか、である。
そんな夜であっても帰宅すれば酔いは醒めている。
飲みなおしに500mlの缶ビールを一本。
元気ハツラツだった時代は630mlの瓶ビールが数本並んでいた。
いっときは休肝日を設けていたが、いつの間にか消え失せた。
今もそうである。
医師からは休肝日の指示はない。
γ-gtbの値も気にかかるが美味しいもんは美味しい。
カラカラに乾いた喉を潤す缶ビールは発泡酒になったものの美味いもんは美味い。
やめられない、とまらない、である。
さて、今夜の食事は一人。
我が食べたいものだけを通院帰りに買ってきた。
購入店は天理市田町にあるハッスル3。
最近になってよく出かけるスーパーだ。
商品棚を見て、これだと思って手にした商品は4品。
一つはビンチョウマグロの柵造り。
自宅で包丁切りしていただく。
二品目に買った商品はフライもん。
税抜き150円の豚ロース串カツだ。
三品目に買った商品はロースに続いてまたもや豚。
フライではなく味付け料理の豚トロ。
味付けはネギ塩を書いてあったから発泡酒にぴったんこ、である。
これだけあって税抜き価格が201円。
内容量はこれぐらいで十分。
これで済むかと思いきや、ついつい手がでてしまったなすの煮びたし。
炊いた茄子の色が鮮やか。
美味いのに決まっとるんやないかと思う。
盛ったパックにたっぷり漬かっている。
味は濃いめに違いない。量もまあまあで税抜き198円。
合計すれば724円。
一人夜宴にささやかながら食にする。
さて、お味はどうか・・・。
一番目に口にするのはいわずと知れたお造りだ。
和歌山県産のビンチョウマグロはトロトロ。
白いケン筋はあるが口の中で溶けてしまう。
包丁でぶつ切りしたがぐちゃぐちゃになってしまった。
二番手は豚トロだ。
味は表記された通りのネギ塩味。
味は美味いがトロ過ぎた。
脂でギトギト。
何枚も食べられるもんではない。
途中で厭いてきた。
発泡酒で口をさっぱりさせてまた一枚、一枚。
噛み応えのある豚トロは歯が唸る。
堅いのではなくすっと切れるという感じだ。
三番手は豚串カツ。
味があるのでそのまま食べても良いのだが、マヨネーズ或はウスターソースが〆てくれると思って冷蔵庫を開ける。
マヨネーズは底をついていた。
それならウスターソース。
味がしっかり馴染んで美味さを引き出す。
豚はロース。
串にタマネギもあるから甘さで包んでくれる。
脂っこくもない豚串カツがむちゃ美味いのである。
四番目は口直しに和風の味を楽しむ。
出汁で煮たなすび。
味はとんとんぐらいか。
旨みがないように思える煮びたし。
出汁そのものにないように思えた。
ひと通りの味具合を味わったら、あとはこれの繰り返し。
それにしても小食になったものだ。
無理やり胃袋に詰め込んで大丈夫なのか。
翌朝、起きたら胃袋はすっからかんになっていた。
(H29. 3. 7 SB932SH撮影)
年に一度か、それとも・・・。
そんなときには決めていたお気に入りの惣菜を狙う。
スーパーに出かけることは週に2、3度ある。
多い時には4度になることもある。
行き先々のスーパーに立ち寄ることも多い。
必ずといっていいほど目を通すのは惣菜売り場。
買ってすぐに食べることができるデキアイの商品。
冷凍もんではなくお店の人たちが作っている調理もんである。
惣菜にはフライもんや天ぷらもんもある。
晩食は飯を喰わないから弁当類は買わない。
飯は飯でも酢飯は美味い。
酒の肴に寿司の味は魅力的だ。
ただ、どうしても腹に堪える。
晩食に飯を喰わなくなったのは何時のころか。
もう何十年も前になる。
結婚したてのころは喰っていたような気がする。
それがいつしか言いわけを作った。
晩食にビールや酒はつきもの。
それがなけりゃ一日の〆にはならない。
ビジネスマン時代はツレらと飲み会。
仕事を終えてちょっと行こか、である。
そんな夜であっても帰宅すれば酔いは醒めている。
飲みなおしに500mlの缶ビールを一本。
元気ハツラツだった時代は630mlの瓶ビールが数本並んでいた。
いっときは休肝日を設けていたが、いつの間にか消え失せた。
今もそうである。
医師からは休肝日の指示はない。
γ-gtbの値も気にかかるが美味しいもんは美味しい。
カラカラに乾いた喉を潤す缶ビールは発泡酒になったものの美味いもんは美味い。
やめられない、とまらない、である。
さて、今夜の食事は一人。
我が食べたいものだけを通院帰りに買ってきた。
購入店は天理市田町にあるハッスル3。
最近になってよく出かけるスーパーだ。
商品棚を見て、これだと思って手にした商品は4品。
一つはビンチョウマグロの柵造り。
自宅で包丁切りしていただく。
二品目に買った商品はフライもん。
税抜き150円の豚ロース串カツだ。
三品目に買った商品はロースに続いてまたもや豚。
フライではなく味付け料理の豚トロ。
味付けはネギ塩を書いてあったから発泡酒にぴったんこ、である。
これだけあって税抜き価格が201円。
内容量はこれぐらいで十分。
これで済むかと思いきや、ついつい手がでてしまったなすの煮びたし。
炊いた茄子の色が鮮やか。
美味いのに決まっとるんやないかと思う。
盛ったパックにたっぷり漬かっている。
味は濃いめに違いない。量もまあまあで税抜き198円。
合計すれば724円。
一人夜宴にささやかながら食にする。
さて、お味はどうか・・・。
一番目に口にするのはいわずと知れたお造りだ。
和歌山県産のビンチョウマグロはトロトロ。
白いケン筋はあるが口の中で溶けてしまう。
包丁でぶつ切りしたがぐちゃぐちゃになってしまった。
二番手は豚トロだ。
味は表記された通りのネギ塩味。
味は美味いがトロ過ぎた。
脂でギトギト。
何枚も食べられるもんではない。
途中で厭いてきた。
発泡酒で口をさっぱりさせてまた一枚、一枚。
噛み応えのある豚トロは歯が唸る。
堅いのではなくすっと切れるという感じだ。
三番手は豚串カツ。
味があるのでそのまま食べても良いのだが、マヨネーズ或はウスターソースが〆てくれると思って冷蔵庫を開ける。
マヨネーズは底をついていた。
それならウスターソース。
味がしっかり馴染んで美味さを引き出す。
豚はロース。
串にタマネギもあるから甘さで包んでくれる。
脂っこくもない豚串カツがむちゃ美味いのである。
四番目は口直しに和風の味を楽しむ。
出汁で煮たなすび。
味はとんとんぐらいか。
旨みがないように思える煮びたし。
出汁そのものにないように思えた。
ひと通りの味具合を味わったら、あとはこれの繰り返し。
それにしても小食になったものだ。
無理やり胃袋に詰め込んで大丈夫なのか。
翌朝、起きたら胃袋はすっからかんになっていた。
(H29. 3. 7 SB932SH撮影)