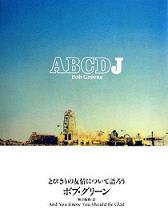
今は亡き友が死に至るまでの間、故郷オハイオ州ベクスレイで濃密な時間をともに過ごし、過去に共有した時間を回想しつつ友に鎮魂の詩(うた)を贈っている。 邦題のAはアレン、Bはボブ・グリーン、Cはチャック、Dはダン、Jは、ボブの最初の、そして一番古い友人ジャックのことを表わしている。この本はジャックとの五歳から五十七歳までのともに生きた時間が大部分を占めている。
書き出しはこうだ。“私たちは、「オーディー・マーフィーの丘」に向かって、ゆっくりと歩いていた。ジャックは以前ここに住んでいた。初めて親友になったとき、私たちは五歳だった。そして五十七歳になったいま、オーディー・マーフィーの丘と呼んだ芝生を前に、私たちはしばし立ち止まっていた。
「あの頃は、もっと傾斜がきつかったように思うけれど」と、私は言った。
「そうだな……まだ小さかったから」と、彼は答えた。
こんな風に二人で歩くことも、あと何回もないはずだった。今日までに至る数ヶ月間で、彼はすっかり体力を失っていた。それでも私は故郷に戻ってくるときはいつでも、彼と一緒に町を歩いた。彼がそう望んだからだ”
この友人のジャックは、金持ちにはならなかったが、人に尽くす献身的な人物でさりげなく語られている。サポート・グループの様子を伝えるジャックの心情に感動を受ける。
サポート・グループというのは、映画でよく見るアル中患者同士が語り合う場面と同じで、ぐるりと円にしたパイプ椅子に坐って発言するというあれである。
ジャックは夜遅くボブに電話をする。本からの抜粋は、“カウンセラーはいるものの、何を話すかは患者や配偶者や家族など、それぞれの自発性に任されていた。その進行を担うのがカウンセラーの役目で、予定表や議題といったものは一切なかった。ただ心に浮かんだことを口に出すのが、この集会の目的だった。
治療のこと、抱えている不安、施術のことから試薬による療法まで、何をテーマにしてもよかった。患者とその伴侶が外ではあまり口に出して言えないようなことを、同じ悩みを抱えたもの同士で語り合った。ここでは誰もがよき理解者だった。なぜ夜の遅い時間を選んで電話をしてきたのか、私は分からなかった。
「グリーン、彼らが気の毒でならないんだ」何か聞き間違えたのかと私は思った。「誰が気の毒だって?」と、私は訊いた。
「集会に来ていた人たちだよ」と、彼は言った。
「君だって同じ立場じゃないか」
「僕よりも辛い人ばかりなんだ。まずガンになってからの時間が長い。中には深刻な手術を経験した人もいて、付き添いなしでは何もできない人もいる。本当に辛い目に遭ってきているんだよ。彼らの話を聞いていたら、胸が張り裂けそうだった」だから電話をせずにいられなかった、と彼は言った。自分のことが辛くて電話をしてきたのではなかったのだ。同じ境遇の人を見て将来の自分を案じたのではなかったのだ。ジャックが冒されているガンは特に悪性で、その先には死が待っているとわかっているのに、彼はその夜をともにして初対面人たちを案じていた。
「あの様子を見たら君だって、自分に何か出来ることはないだろうかと考えると思うよ」と、彼は言った。そしてそのことを考えていたら、眠れなくなってしまったというのだ。
「ベッドで横になっていても、そのことが頭から離れないんだ」と、彼は言った。「どうしてあの人たちがこんな目に、と思ってしまう。彼らにどんな言葉をかけてあげたらいいのか、どうしたら楽にして上げられるのか、そんなことさえ上手く思いつけないんだよ」
これに続く文章を読んだとき、活字がにじんできて鼻がぐずぐずいった。少し長いけれど引用すると
“翌日私はシカゴのレストランにいた。席に一人で坐りながら、もちろんジャックのことを考えていた。彼に会いに行く次回の予定を考えているところだった。そこへある家族が、大きな息子を連れて入ってきた。見たところ彼は障害を負っている様子で、そのために体がときおり意思と関係なく動いてしまうようだった。おそらく神経障害の類だと思うのだが、体の動きといい、そのときに立てる音といい、彼にはまったく制御が不可能だった。
そして白いテーブルクロスがかけられた高級なレストランにいる客たちは、そのことをどこか不快に感じているようだった。一人のウェイトレスと二人のウェイター、そしてマネージャーの計四人が、家族のすわる席へ近づいていくのが見えた。他の客たちの拒絶するような態度を見て取り、その対応に向かったのだと私は思った。テーブルを遠くへ移すとか、あるいは他の店へ行くように促すのではないかと私は案じた。だとしたら法律に違反するような態度だが、それはそれでよくあることだった。
しかし、ウェイトレスは満面に笑みをひろげ、励ますような明るい声で「ハイ!」と、彼に話しかけた。そして彼の席に近寄り、そこにひざまずいた。
「元気にしていた?」と彼女は尋ねた。ニコニコと笑いながら、彼の目をしっかりと見ていた。
「会えなくて寂しかったよ」と、ウィエイターの一人が言った。
「いったいどこへ行っていたんだい?」マネージャーも声をかけた。
「レイ、お帰り! 調子はどうだい」その若い彼は微笑んでいた。前にもここに来たことがあり、スタッフは彼のことを知っているのだった。店は彼を心から歓迎し、楽な気持ちで過ごせるように即座に対応していた。それを見る家族も嬉しそうな様子だった。
彼らがこの店に何度も足を運ぶのも道理だ、と私は感じた。おそらく他の場所で、家族はこれほどの対応を受けてはいないだろう。生まれ持った障害のせいでどこへ行っても音を立ててしまい、先々で冷たい視線にさらされてきたはずだ。スタッフの対応を見て、レストランの客たちにも和やかな空気が広がった。ただそれだけで絶大な効果があった。その家族がやさしさと理解を持って迎えられたのを目にして、彼がここにいることは少しもおかしなことではないのだということに誰もが気づかされたのだ。むしろ彼が店にやって来たことで、そこにいる人たちは人間の持つ慈しみのようなものを感じていた。
そしてそんな体験を味わったからだろうか、あるいは前日の晩にジャックが電話で言っていた内容にいまだに驚いているからだろうか。私はこう思った。……ジャック、ここにもまた一つ、君の財産が受け継がれている。実にシンプルなことなのだ。困っている人には親切にすること、自分では何も出来ない人に対しては手を貸してあげること。自分を護るすべのない人を温かく迎えること”
こんなレストランなら贔屓にしたいものだ。ちなみに、オーディー・マーフィーの丘のオーディー・マーフィーは、第二次世界大戦のイタリア、南フランス戦線などで戦功をあげ、米陸軍の最高栄誉賞など24個を受章して英雄となる。帰国後映画出演などがあるが、1971年5月飛行機事故で死去。47歳だった。ボブ・グリーンたちは芝生の庭に、その英雄にちなんで名づけたのだろう。
著者は、1947年オハイオ州ベクスレイ生れ。アメリカの名コラムニストとして、30年以上にわたってサン・タイムズ紙、シカゴ・トリビューン紙などでコラムを執筆するほか、ライフ誌、エスクワイア誌でリード・コラムニストとして活躍。ABCのニュース番組「ナイトライン」の解説者を務め、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーの『十七歳春/秋』『チーズバーガーズ』『マイケル・ジョーダン物語』『DUTY-わが父、そして原爆を落とした男の物語』など著書多数。
















