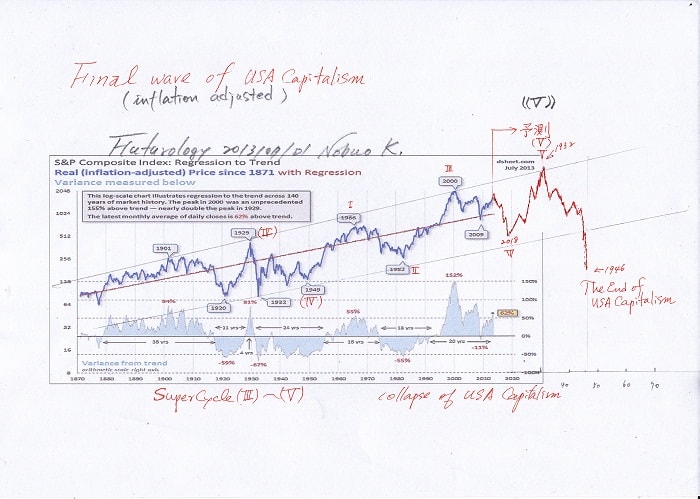http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20140211/plt1402110726001-n1.htm
機密は技術者の頭の中にある 「ゆりかごから墓場まで」が国家の使命 (1/2ページ)
★機密は技術者の頭の中にある 2014.02.11
.連載:ニッポンの防衛産業
.
安倍首相(奥中央)は官邸で開かれた総合科学技術会議で、ImPACTの重要性を訴えた
=2013年9月13日
新たに立ち上がったImPACT(インパクト=革新的研究開発推進プログラム)に対し、中国が露骨に嫌がったことは、この取り組みが、まさに日本の発展につながると教えてくれたようなものだろう。
ImPACTは、プログラムマネジャーが有能な人材を集めてチームをまとめ、研究を行う米国のDARPA(国防高等研究計画局)に倣ったものだ。そのDARPAでは、昨年開催されたロボットコンテストで日本企業が優勝したものの、その会社は米国のグーグルに買収されている。
今の日本の民間企業には、チャレンジングな試みを受け入れる余裕がないことが分かる。また、失敗が許されない、成果を必ず出されなければならないという空気が強く、思い切ったことができないようだ。国費を投じるとなればなおさらだ。
ImPACTを立ち上げたのは、内閣府総合技術会議であるが、ここに防衛省の技術研究本部なども参画し、「産官学」の観点でハイレベルな装備品開発が成功することに期待したい。
そのためには、民間活用できるデュアルユース(DU)の追求が重要になるだろう。しかし、一方で何から何までDU化できるはずはなく、ショッピング番組さながらに「自宅でも使えますが、兵器にもなります」などというわけにはいかないのである。むしろ、純粋なる軍事技術は汎用化できない。
やはり、根底にある「軍事アレルギー」を解消させる努力は同時進行されるべきであり、金欠病とアレルギーの根本治療は不可欠であろう。
さて、こうした取り組みの将来性の1つには、輸出という目的も見いだせそうだが、昨今、盛んになっている「武器輸出3原則」緩和議論では、とかく軍事転用の危険性ばかりが言われ、日本の技術を守る観点に欠けているのが気になる。
国力となる重要技術を「コスト削減につながる」「防衛産業を助けられるのではないか」といった安易な発想で流出させることになれば、それこそ「危険」だ。
ある企業幹部はこんなことを語ってくれた。
「国家機密は、設計図や仕様書などではなく、技術者の頭の中にあるんです」
防衛技術者たちには、リタイア後も秘密厳守が厳しく求められるが、欧米などのように恩給などで優遇されているわけではない。こうした人材に対する国の施策があってもいいだろう。それが、さらなるモチベーションとなれば、おのずと人材発掘にもなる。
防衛装備は技術者も含め「ゆりかごから墓場まで」守る、それは国家の使命だといえるだろう。
■桜林美佐(さくらばやし・みさ) 1970年、東京都生まれ。日本大学芸術学部卒。フリーアナウンサー、ディレクターとしてテレビ番組を制作後、ジャーナリストに。防衛・安全保障問題を取材・執筆。著書に「日本に自衛隊がいてよかった」(産経新聞出版)、「武器輸出だけでは防衛産業は守れない」(並木書房)など。
/////////////////////////////////////////////////////
● 先ず敵国への技術の流失は、とんでもない事である。お金と技術を敵国に与えて、
自分の国に核兵器の照準を合わせさせるとは、既に馬鹿を超えています。
これらはスパイとして取り締まる事が必要です。当然の事である。
● 少数の技術者の為に、国民全体が核兵器の危険のさらされることは、愚の骨頂です。
そんなことは馬鹿でも分かるのに、今までの官僚や政治家は何をしていた?
と言う事です。殆どは犯罪的な国家運営をしていた事に成ります。
● もっともっと、理系の優秀な人の給料を増やすべきです。待遇を良くして、大陸や
半島に人材が流れるのを防ぐべきです。これでこそ安全が確保できるのです。
機密は技術者の頭の中にある 「ゆりかごから墓場まで」が国家の使命 (1/2ページ)
★機密は技術者の頭の中にある 2014.02.11
.連載:ニッポンの防衛産業
.
安倍首相(奥中央)は官邸で開かれた総合科学技術会議で、ImPACTの重要性を訴えた
=2013年9月13日
新たに立ち上がったImPACT(インパクト=革新的研究開発推進プログラム)に対し、中国が露骨に嫌がったことは、この取り組みが、まさに日本の発展につながると教えてくれたようなものだろう。
ImPACTは、プログラムマネジャーが有能な人材を集めてチームをまとめ、研究を行う米国のDARPA(国防高等研究計画局)に倣ったものだ。そのDARPAでは、昨年開催されたロボットコンテストで日本企業が優勝したものの、その会社は米国のグーグルに買収されている。
今の日本の民間企業には、チャレンジングな試みを受け入れる余裕がないことが分かる。また、失敗が許されない、成果を必ず出されなければならないという空気が強く、思い切ったことができないようだ。国費を投じるとなればなおさらだ。
ImPACTを立ち上げたのは、内閣府総合技術会議であるが、ここに防衛省の技術研究本部なども参画し、「産官学」の観点でハイレベルな装備品開発が成功することに期待したい。
そのためには、民間活用できるデュアルユース(DU)の追求が重要になるだろう。しかし、一方で何から何までDU化できるはずはなく、ショッピング番組さながらに「自宅でも使えますが、兵器にもなります」などというわけにはいかないのである。むしろ、純粋なる軍事技術は汎用化できない。
やはり、根底にある「軍事アレルギー」を解消させる努力は同時進行されるべきであり、金欠病とアレルギーの根本治療は不可欠であろう。
さて、こうした取り組みの将来性の1つには、輸出という目的も見いだせそうだが、昨今、盛んになっている「武器輸出3原則」緩和議論では、とかく軍事転用の危険性ばかりが言われ、日本の技術を守る観点に欠けているのが気になる。
国力となる重要技術を「コスト削減につながる」「防衛産業を助けられるのではないか」といった安易な発想で流出させることになれば、それこそ「危険」だ。
ある企業幹部はこんなことを語ってくれた。
「国家機密は、設計図や仕様書などではなく、技術者の頭の中にあるんです」
防衛技術者たちには、リタイア後も秘密厳守が厳しく求められるが、欧米などのように恩給などで優遇されているわけではない。こうした人材に対する国の施策があってもいいだろう。それが、さらなるモチベーションとなれば、おのずと人材発掘にもなる。
防衛装備は技術者も含め「ゆりかごから墓場まで」守る、それは国家の使命だといえるだろう。
■桜林美佐(さくらばやし・みさ) 1970年、東京都生まれ。日本大学芸術学部卒。フリーアナウンサー、ディレクターとしてテレビ番組を制作後、ジャーナリストに。防衛・安全保障問題を取材・執筆。著書に「日本に自衛隊がいてよかった」(産経新聞出版)、「武器輸出だけでは防衛産業は守れない」(並木書房)など。
/////////////////////////////////////////////////////
● 先ず敵国への技術の流失は、とんでもない事である。お金と技術を敵国に与えて、
自分の国に核兵器の照準を合わせさせるとは、既に馬鹿を超えています。
これらはスパイとして取り締まる事が必要です。当然の事である。
● 少数の技術者の為に、国民全体が核兵器の危険のさらされることは、愚の骨頂です。
そんなことは馬鹿でも分かるのに、今までの官僚や政治家は何をしていた?
と言う事です。殆どは犯罪的な国家運営をしていた事に成ります。
● もっともっと、理系の優秀な人の給料を増やすべきです。待遇を良くして、大陸や
半島に人材が流れるのを防ぐべきです。これでこそ安全が確保できるのです。