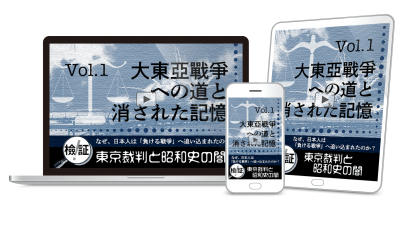人種差別の是正を求めるうねりは企業の経営判断にも影響を及ぼす(6月4日、ワシントン)=AP
米国での黒人暴行死事件を受け、企業が人種差別問題への対応を急いでいる。黒人の採用増や差別解消のために資金を出す動きに加え、事業内容を見直したり調達先を切り替えたりする企業も出てきた。うねりの大きさを象徴する一方、傍観すれば経営リスクになるとの危機感も企業の背中を押す。
白人警官によるジョージ・フロイド氏の暴行死事件は5月25日、ミネソタ州ミネアポリスで発生した。9分近く膝で首を押さえつける動画は瞬く間に拡散。3週間以上たった現在も全米各地で抗議デモが続くなど、1960年代の公民権運動以来の規模とされる。
■300社が反対表明
企業の動きは早かった。米小売り大手ウォルマートは6月5日、有色人種の採用拡大や、差別解消のために5年で1億ドル(約107億円)を拠出すると表明。9日には独アディダスが米国での採用の3割以上を黒人とヒスパニック(中南米系)にすると発表した。
米メディアによると、人種差別への反対を表明した企業は300超、黒人の地位向上や人権保護の取り組みへの資金提供を発表した企業も数十社にのぼった。
事業内容やサプライチェーン(供給網)を見直す動きも出ている。
アマゾン・ドット・コムやマイクロソフトは警察への顔認証技術の提供を当面やめる。顔認証はかねて白人に比べ黒人の識別精度が低く、黒人の冤罪(えんざい)につながると批判されており、「法律で人権に基づいた使用ルールが定まるまで販売しない」(マイクロソフトのブラッド・スミス社長)。シェアが低いIBMは同事業から撤退すると表明した。
「米国の黒人比率は15%だ。店の棚にも黒人事業主から仕入れた商品を15%以上置いてほしい」。小売業では黒人オーナーからの調達率の開示と引き上げを求める「15%の誓約」運動が広がる。アフリカ製のファッション商品を扱うニューヨークのデザイナーが提唱する運動で、化粧品販売大手セフォラなどが賛同を表明した。
米国では過去にも警察官による黒人死亡事件が起き抗議デモが広がったことがあるが、企業は沈黙を守るケースが多かった。今回、企業が相次ぎ対策を打ち出す背景には、抗議活動の規模が過去になく大きく、対応を誤れば経営リスクを招くとの判断がある。
■創業者が引責辞任
「多くの人を意図せず傷つけてしまった」。フィットネスジム大手の米クロスフィットを創業したグレッグ・グラスマン最高経営責任者(CEO)は6月上旬、辞任を表明した。暴行死事件を巡りツイッターで差別的な投稿をしたと批判され、アディダス傘下のリーボックがスポンサー契約の解除を打ち出していた。
明確な失言はなくても、「何もしないこと」がリスクになる状況も鮮明になっている。フェイスブックは「略奪が始まれば銃撃も始まる」というトランプ大統領の投稿を容認し掲載を続けた。反発した社員によるストライキや辞職に発展し、マーク・ザッカーバーグCEOが方針転換を迫られた。
企業は従来、政治的なメッセージを発することを極力避けてきた。異なる考えの顧客を失う可能性があるためだ。だが今回、人種差別撤廃の動きが強まるなか、「沈黙していることは共犯と同じだ」(米動画配信大手ネットフリックスの投稿)との意識が広がった。
危機管理に詳しい米FTIコンサルティングのクリスティーン・ディバルトロ氏は「経営者がリーダーシップを発揮して行動をとるべきだ」と指摘する。
今後問われるのは企業の本気度だ。売上高上位の米フォーチュン500の企業のなかで、黒人のCEOは4人しかいない。米ハーバード大などによると、18年時点で500社の取締役に占める黒人比率は9%にとどまる。女性の取締役比率が23%と10年から約7ポイント上昇したのに対し、黒人比率は1ポイントしか上がっていない。
フロイド氏の死を機に企業に潜む格差も改善できるか岐路に立つ。
(米州総局=中山修志、佐藤浩実、野村優子)