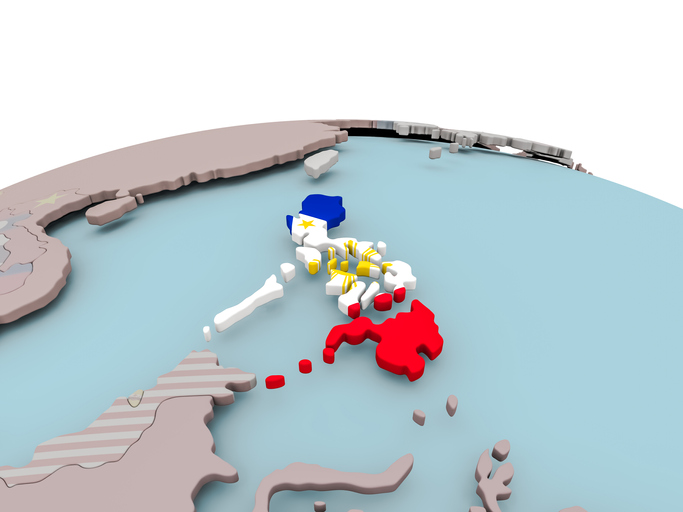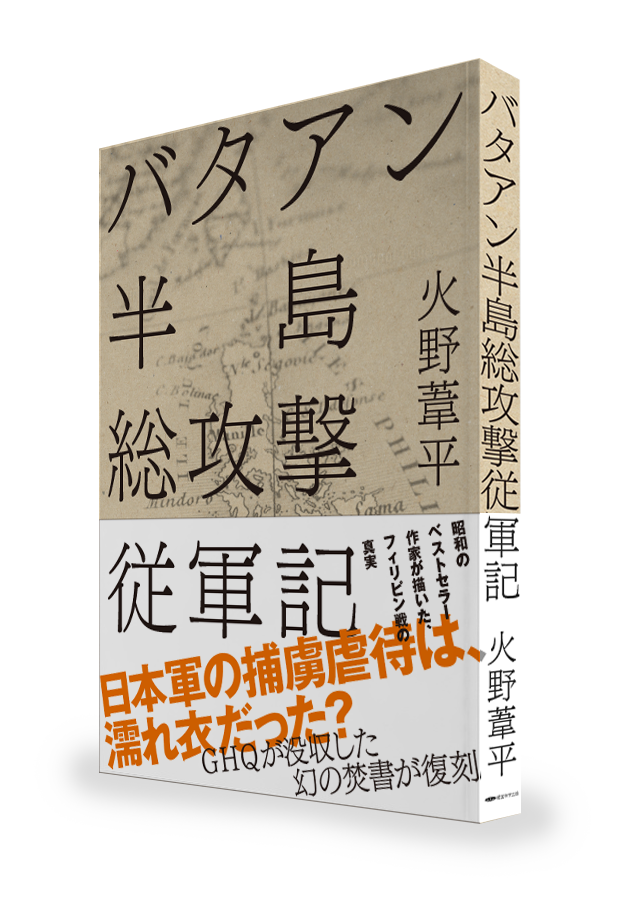〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和2年(2020)8月18日(火曜日)
通巻第6622号 <前日発行>
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
イスラエルとUAE国交、続く中東諸国はすでに数ヶ国が視野に
カタール、バーレン、オマーン、そしてサウジアラビアさえも前向き
****************************************
UEAとイスラエルが国交を開き、中東政治に突破口が開かれたと西側メディアは積極的に評価した。
UEAに続きそうなアラブ諸国の筆頭はドバイとバーレンである。水面下の接触どころか外務担当の高官らの相互訪問も繰り返されている。
ついでカタールだ。アルジャジーラ放送局のような、ややリベラルなメディアを誇るカタールは、国際的な平衡感覚があり、イスラエルとの関係改善に前向きと観測されている。
オマーンもイランを目の前にホルムズ海峡を扼し、イランの動きを慎重にみながらも、積極的な外交チャンネルを拡げてきた。タイミングを見計らっているかのようである。
このような鵺的な行動を取るのは、国内要因、政治家の資質もさりながら、イランとの関係からくる打算である。
モロッコはユダヤ人コミュニテイィもあって、セファルディの移民はモロッコからボロ船で地中海を横断してイスラエルに移住した。モロッコはポンペオ国務長官が仲立ちして、第三国でイスラエルとの交渉を進めているという噂がある。
阻害要因は汎アラブ人に共通するユダヤ人嫌い、イエーメンはイラン系「フウシ」の武装集団が「イスラエルに死を!」と叫んでいる。レバノン、シリアはシリアの代理兵が蠢き、イスラエルとの国交回復など当面はあり得ないし、アルジェリア、スーダン、リビア、イラクなどもイスラエルを敵視する頑固な姿勢に変わりがない。
ただしチュニジアを例外として、いずれも国も内戦もしくは部族紛争が続いており、国内事情で、それどころではないというのが実情だ。
こうなるとサウジアラビアがどうするのか。
じつはイランとの敵対という基本構造があり、アラブの団結の必要があるため、最期に名乗りを上げるだろう、と観測されている。
リヤドはじっとアラブ国家の動静をみているのだ。いま一つはトランプ政権との関係もすこぶる良好で、足繁く大統領女婿のクシュナーがサウジアラビアを訪問している議題のなかには、イスラエルとの関係改善が討議されている
近くUEAに続く国がでる。
☆○▽◇み◎○△□や○△□◇ざ◎○△□き△□☆☆
この2ブロック化は、コロナ禍にあえぐ新興国・途上国の経済を蝕む結果になってきています。以前、このコーナーでもお話ししたように、多くの新興国がデフォルトの危機と言われるほど、COVID-19は途上国経済に壊滅的な影響を与えつつありましたが、アメリカFRBによる措置が功を奏して、世界のドル不足を緩和したことで新興国経済は力強く回復したように見えます。
ここで皮肉なのが、その恩恵を最も受けたのが、そのアメリカと戦う中国の経済です。世界銀行やIMFの最新の分析によると、恐らく今年中には中国のGDPはBefore Coronaのレベルにまで回復する見込みとのこと。もちろん米中開戦など、大きな事態が起こらなければという条件付きではありますが。
ただこの中国経済の“復活”は、東南アジア諸国の経済回復を力強く後押ししている模様です。
しかし、実際には新興国・途上国経済の完全な回復は今後も見込めないと考えます。
理由としては、日本も例外ではないのですが、COVID-19の感染拡大が止まっていない、もしくは再拡大が進行していることで、経済活動と移動の自由の本格的な再開が見込めないことがあります。
また、今回のパンデミックは先進国・途上国の別なく、世界的に大打撃を与えており、今後、長い期間にわたってと上位国に対する海外投資が回復してこないだろうとの見解が強くなってきています。
戦争か?平和か?岐路に立つ世界
さらに、コロナ禍で若者の教育が世界的に中断されており、特に途上国では、家庭の生計を立てるために若者がpart-timeで働くことを余儀なくされ、それがコロナによるDrop out、そして教育の中断の恒常化を招くのではないかとの懸念が、UNESCO(国連教育科学文化機関)の最新のレポートで述べられています。その結果、労働生産性が低下することになり、途上国経済は一般的に将来にわたって稼げる能力を失うことを意味すると言えます。
そこに加えて激化する米中対立が生む世界の2ブロック化は、国際協調の鈍化に繋がり、これまで数十年間続いてきた経済成長モデルの構造を根本から変える可能性を帯び、サプライチェーンが変質することで、途上国にとっての“成長パターン”が無くなる可能性も生まれます。
先進国も例外なく、今回の新型コロナウイルスのパンデミックの打撃を被っており、自国経済の再建に必死であるため、途上国の救済にまで手が回らず、中長期的な危機を誘発する可能性もあるでしょう。
そのような中、米中が互いに自らのブロックに各国を迎え入れるために様々な手を講じようとしていますが、中国にとって、この覇権争いでアメリカや欧州と対抗するには、一帯一路政策の下、膨れ上がらせた支援国の重度の債務超過にどのように対応できるかが問われているようです。
債務放棄要請に応じるのか、それとも減額や支払い期限延長などの限定的な対応に留まるのか。経済で支配を広げてきたそのツケに今、中国政府は直面しています。
欧米諸国も同じく自国内・地域内の復興が先決であるため、中国の苦悩の隙を突けずにいます。
その突破口となり、世界の力の趨勢を決めるのはどのような出来事でしょうか?
南シナ海での米中の武力衝突、尖閣諸島周辺で日本や台湾も交えた衝突、米イラン(そしてイスラエル)の中東での紛争勃発、ロシアやトルコが仕掛ける国際社会への“挑戦”、そして、朝鮮半島における開戦…という戦争を介したネガティブなトリガーなのか、「新型コロナウイルスに対する有効なワクチンの開発と普及の拡大」というポジティブなトリガーを米中どちらの勢力が弾くことになるのかという戦いなのか。
残念ながら私には分かりませんが、世界は確実に米中を軸に動き、そして両国間の緊張は、まるで破裂する直前の風船のように、高まっていると言えます。
皆さんはどう思われますか?
国際情勢の裏側、即使えるプロの交渉術、Q&Aなど記事で紹介した以外の内容もたっぷりの島田久仁彦さんメルマガの無料お試し読みはコチラ
image by: The White House Flickr(public domain)