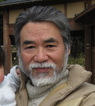少年犯罪の背景に潜む、心の闇と人間不信。
問題行動は、突然に起こるのではありません。?
長い時間をかけて許容限度を超えたときに暴発するのです。
?それまでに、何度もエマージェンシーやエスケープのサインを出しています。?
それをキャッチし、全霊を掛けて向き合い抱き留めることが必要です。
?愛されたいのです。家族から。?認めて欲しいのです。
自分の存在感を。?優しいまなざしで見つめてあげてください。
?きっと心を開いてくれます。
?でもそうなる前の親子の関係が大事です。?お金やもので、豊かな心は育まれません。
?快楽を求めると際限がありません。?そして、いつか大きなものを失います。?大切な「こころ」です。
親は、自分の子育ての間違いをなかな認めません。
?過保護や無関心から子どもを放任や過干渉にさせた結果です。
?また、否定されて養育された子どもも犯罪や依存症になりやすい。
犯罪を犯す子どもの多くは身体が育っても心が育っていません。
最近の犯罪の背景にあるのは、ゲーム脳が関係しています。
記憶、感情、集団でのコミュニケーション、創造性、学習や感情の抑止力をつかさどる脳の中の前頭前野が、ゲーム、携帯メール、テレビ、ビデオなどに熱中しすぎると働かなくなります。
?その結果「キレやすい」「集中力がない」「注意力散漫」「羞恥心欠如」「その日暮らし」「無気力」という症状がゲーム脳の特徴である。
最近の犯罪少年の成育歴の中に、ゲームに熱中していたとの報道からも裏付けられています。
幼児を育てておられる親は、心の隅に記憶しておいてください。
?我が子が求めるからといって、携帯電話やゲームを簡単に与えないでください。
後悔するのは親であるあなたです。
またテレビを視聴する習慣も出来るだけさせないようにしてください。?
親が視ていると子どもも視るようになります。
?テレビをベビーシッターにするのもやめましょう。?幼児番組も含めてです。
あなたの優しい愛情を与えてあげてください。?たくさん抱いてあげてください。
?そしてたくさん誉めてあげてください。
きっと、いい子に育ちます。