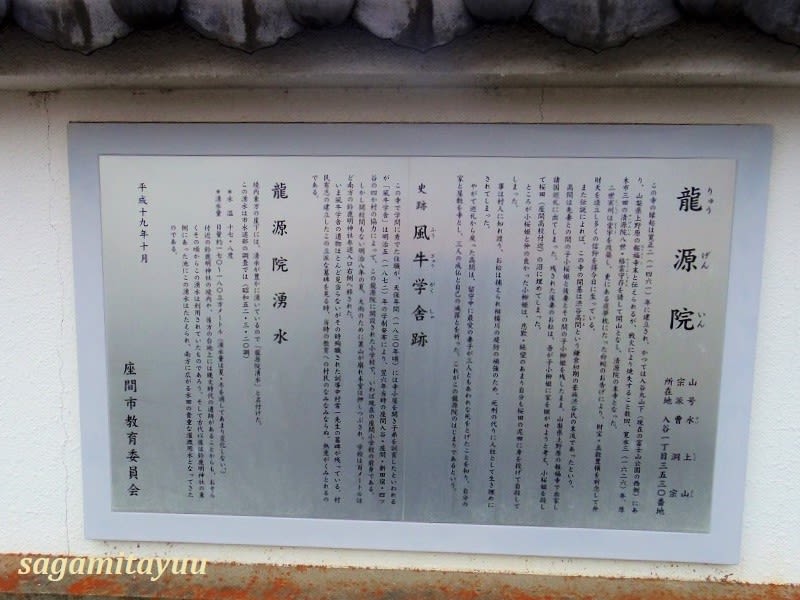模原市南区当麻に相模原の食ツウであれば知る人ぞ知る昭和34年創業の川魚料理店の老舗「飄禄玉」がある。相模原茅ヶ崎線の「麻溝小学校入口」先を右折、浅間神社前の坂を下りていくと店の前にはいくつもの生簀があるお店にたどり着く。店内もかなり渋い感じで昔ながらの雰囲気を有している。テーブル式最大50名は入れそうな広さである。メニューは鱒の唐揚げ(580)、若さぎの唐揚げ(486)、鮎の塩焼き(702)、鮎の煮付け(702)、鮎丼(1,263)、麦めし(248)、鯉の味噌汁(150)とリーズナブルな価格設定である。またお持ち帰り限定の「鱒の唐揚げ弁当」(1,000円)も用意してある。店内座敷・テーブルから湧水の流音を聞きながら丹沢の山並と田園風景の大パノラマを眺めながらオーダー料理に舌鼓を打つのもいいものである。生簀の奥には店主が収集した仏像60点が展示されている「仏像ギャラリー」もある。(2202)