
冒頭は小津の『浮草』のあの激しい雨のシーン(これはラストでシンメトリー化する)。唐突なベルイマンの『処女の泉』(話だけだが)といい、【原田眞人】はこの映画を何かオマージュっぽく集大成化しようとしているように見える。
確かに映像、演出、そして豪華な俳優陣、そして脇役の隅々までの彼らの確かな演技。どれを見ても一級品だ。現代日本映画の粋だろう。しかし私には作品的には立派でも肝心のわが心が全く触れてくれないのだ。揺れない。濡れない。渇きもしない。要するに映画を見ていて動揺がないのだ。
何故かなあと思う。それは(当時は認知症という概念がなかったと思うが)ボケが徐々に進んでくる老母の叙述は特に目新しいものではなく(現代では日常茶飯事でもある)、母親との間接的雪解けも僕にはそれほど感動を与えるものではなかったからだろうか、、。
そしてこの作家の生活レベルがあまりにハイソサエティで一般人の生活レベルを超えており、親近感を感じなかったというひっかかりがどこかにあるのかもしれない。あの、大掛かりな洋行シーンも映画的に何か意味があるのだろうか、と訝っている。
しかし、映画テク的には素晴らしい作品だと思いました。でも僕には触れて来ない映画でしたネ。母を想う心はここまで大そうにして描かなくても、市井のそこらの生活風景にいくらでも存在すると僕は思っています。










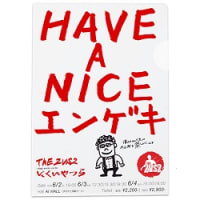






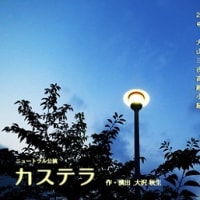







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます