読み始めて「しまった」と思った。
漢語がふんだんに出てきてとても読みこなせない。
鴎外の知識の広さには舌を巻くが、フツーの読者はついていけないよ。
と言いながら、いつのまにか読了している。

江戸後期の医官渋江抽斎にスポットを当てたのが鴎外だった。
抽斎を取り上げたのは、彼が単なる医者ではなく、儒学・芸術・趣味も広く、鴎外に共通するところが多かったからだろう。
小説というより編年体の日誌を読んでいる感覚だ。
抽斎をめぐる交友関係・親戚・趣味などをこと細かくメモランダムに羅列していく。
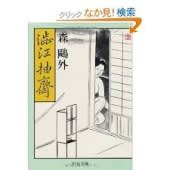
注目すべきは、抽斎の息子の「渋江保」が浜松や春野町にかかわっていることだった。
彼は教育者として浜松師範学校(静岡大学教育学部)の創設運営にかかわったり、春野町犬居村に住んだこともある。
場所は秋葉神社下社あたりではないかと、郷土史家の木下恒雄さんが自費出版の『山林の思想』のなかで推測している。
1年足らずだったが病気療養のためらしい。
彼は記者としても活躍し、自由民権運動の推進に論陣を張ったこともあったが干渉される。

珍しく漢和辞典を引っ張り出しながらだったが、基本的に惰性の流し読みとなる。
儒学が明治日本にまで学ばれていることが、ある意味素晴らしい。
日本の成長力は「学ぶ力」。
その先鞭に鴎外がいたんだ。
漢語がふんだんに出てきてとても読みこなせない。
鴎外の知識の広さには舌を巻くが、フツーの読者はついていけないよ。
と言いながら、いつのまにか読了している。

江戸後期の医官渋江抽斎にスポットを当てたのが鴎外だった。
抽斎を取り上げたのは、彼が単なる医者ではなく、儒学・芸術・趣味も広く、鴎外に共通するところが多かったからだろう。
小説というより編年体の日誌を読んでいる感覚だ。
抽斎をめぐる交友関係・親戚・趣味などをこと細かくメモランダムに羅列していく。
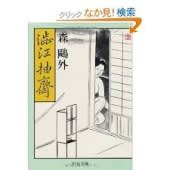
注目すべきは、抽斎の息子の「渋江保」が浜松や春野町にかかわっていることだった。
彼は教育者として浜松師範学校(静岡大学教育学部)の創設運営にかかわったり、春野町犬居村に住んだこともある。
場所は秋葉神社下社あたりではないかと、郷土史家の木下恒雄さんが自費出版の『山林の思想』のなかで推測している。
1年足らずだったが病気療養のためらしい。
彼は記者としても活躍し、自由民権運動の推進に論陣を張ったこともあったが干渉される。

珍しく漢和辞典を引っ張り出しながらだったが、基本的に惰性の流し読みとなる。
儒学が明治日本にまで学ばれていることが、ある意味素晴らしい。
日本の成長力は「学ぶ力」。
その先鞭に鴎外がいたんだ。



















