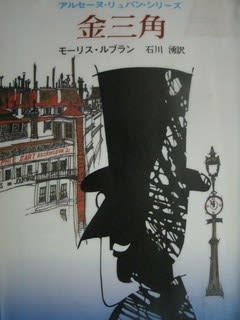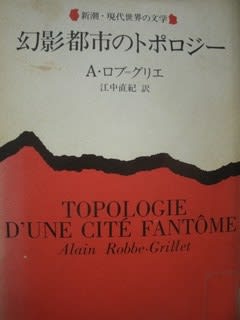ただタイトルに惹かれて久しぶりに「アルセーヌ・ルパン」シリーズの一篇を読んでみたのだが、それは決して良い意味ではなく推理小説のタイトルとしてははっきり言ってダサいのではないかと思ったからである。しかし「金三角」の原題は「Le triangle d'or」だから「黄金の三角形」という意味で間違いではないのである。
そこで「金三角」に言及されている箇所を引用してみる(『金三角』 創元推理文庫 石川湧訳 1972.12.22 原書は1917年出版)。最初は、パトリス・ベルヴァル大尉が事件の手掛かりを探すために、エサレス家の執事であるシメオン・ディオドキスの部屋を訪れた場面である。
「注目に値した唯一の発見は、箪笥の裏、白い壁紙に鉛筆で描かれた、かんたんな図形であった。ー 交差する三本の線が、大きな正三角形をなしている。この幾何学的図形のまんなかには、金箔でらんぼうになぐり書きがしてある。金三角! デマリオン氏の捜査になんの役にも立たないこの文句のほかには、手がかりとなるものは全然ない」(p.162)
次はパトリスがドン・ルイス・ペレンナ(=アルセーヌ・ルパン)と射殺されたヤボンの死体を発見した場面である。
「『しかし、とにかく、確かになったのは、ヤボンが、金貨袋を積んだかくし場所を知っていることと、そしてそれはおそらく、コラリーがいた、またたぶん今もいるかくし場所だということです。もしも敵が、何よりもわが身の安全をかんがえて、そこから連れだす時間がなかったとすればですがね』
『まちがいありませんか?』
『大尉どの、ヤボンはいつも、チョークを持ってあるいています。やつは字が書けないので ー わたしの名前以外は ー この二本の直線を引いたのです。それと、やつがなぞった壁の線とで、三角形になります。金三角です』」(p.286)
最後はドン・ルイスがフランス大統領のヴァラングレーに「金三角」について説明している場面である。
「『大統領閣下、わたしが魔法の杖で金貨を出現させたり、黄金を積んだ洞穴をお見せしたりするなどは、あまりあてにしないでください。わたくしは、《金三角》という言葉は、なにか不思議で伝説的なものを連想させて、とんでもないまちがいにみちびくものだと、いつも考えていたのです。わたくしの意見では、それはただ金貨のある場所が三角の形をしているというだけのことです。金三角というのは、金貨の袋を三角に積みあげてあるということなのです。だから、事実ははるかに単純なものであり、閣下は失望されることでしょう』」(p.362)
さらにドン・ルイスが説明している部分を引用してみる。
「『それが金貨の袋です。千八百個あるはずです。(中略)一キロの金貨は、三千百フランに相当いたします。そこで、わたくしが大体計算したところによりますと、千フランの丸い棒で十五万五千フランはいっている五十キロの袋は、かなり小さいものです。
その袋を並べたり重ねたりして積みあげると、約五立方メートルを超えない容積となります。もしもその袋の山を、三角のピラミッド形にいたしますと、それぞれの底辺は大体三メートル、袋と袋のすきまを考慮に入れると、三メートル半となりましょう。高さは、この塀ぐらいです。その全体に砂をかぶせると、閣下の御前にあるこの砂山になります。』」(p.364)
「『ヤボンはチョークで歩道に三角形をえがいた。そしてこの三角形には二辺しかなく、底辺は堀の裾になっていた。どうしてこんなだろう? なぜ底辺がチョークで描いてないのか? 底辺がないのは、かくし場所は堀の裾にあるという意味なのか?』」(p.380-p.381)
試行錯誤しながらドン・ルイスは目の前の砂山に思い当たり、掘ってみると袋とコラリーを見つけ出したのである。
ここまで読んで分かる人には分かるのだが、これはエドガー・アラン・ポーが1844年に発表した短編小説「盗まれた手紙」と同じ手法であり、実際にドン・ルイスも以下のように言及している。
「『ところで、ある場所をしらべて、さがす物が見つからないときには、わたしはいつでもエドガー・ポオの奇怪な小説『盗まれた手紙』のことを思い出すのです。ご存じでしょう ー 盗まれた外交文書が、どの部屋にかくされているのかわかっているという話を。その部屋は、隅から隅までしらべられる。床板を一枚のこらずはがしてみる。ない。しかしデュパン氏がやって来て、さっそく壁にかかっている小物入れのところへ行く。そこからはみ出している古い紙片がその文書だったのです。』」(p.380)
しかし『金三角』が「盗まれた手紙」のトリックのように上手くいっているとは思えない理由は、そもそも何故箪笥の裏に三角形の図形が描かれなければならなかったのかよく分からないし、正確を期するならば「砂山」は「三角形(le triangle)」というよりも「三角錐(le tétraèdre)」、あるいは「円錐(le cône)」だからである。
実はフランスの作家であるアラン・ロブ=グリエが1978年に上梓した小説『Souvenirs du Triangle d'Or(黄金の三角形の記憶)』は『金三角』をベースにしていると睨んでいるのだが、『Souvenirs du Triangle d'Or』はいまだに邦訳されていなかった。誰か訳してくれないかな?
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/spice/entertainment/spice-315025