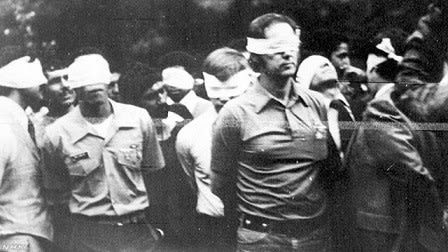(先週末に無人機の攻撃を受けた、サウジアラビアの首都リヤド郊外にある石油施設の衛星画像。米政府提供(2019年9月15日撮影、同16日提供)【9月17日 AFP】)
【「あまりにも脆弱」】
今回のサウジアラビア石油施設に対する攻撃は、いまだわからないことばかりですが、ひとつはっきりしたことは、世界経済に大きな影響を与える世界最大規模の石油施設の防衛体制が非常に脆弱であるということです。
そのことに関連して、かねてよりフーシ派のミサイル攻撃を阻止したと豪語していたサウジのパトリオットなどのミサイル防衛システムは今回はどうしたのか?という疑問も。(これまでもサウジ側の「攻撃を阻止した」との発表は“大本営発表”で、実際は防ぎきれていないとの指摘がありましたが・・・)
****脆弱ぶりを露呈****
攻撃を受けたのはサウジ東部ダーランから約60キロ離れたアブカイクにある世界最大規模の石油施設と、首都リヤド東方のクライス油田。(中略)
とりわけ、市場やペルシャ湾岸産油国がショックだったのは、石油施設が無人機攻撃に「あまりにも脆弱」(専門家)な実態を露呈したことだ。
サウジは巨額の軍事費を投じて防空網などを強化しつつあるが、こうした最新のシステムが、1機1万5000ドル(160万)程度の安価な無人機にいかに無力であるかを証明してしまった。(後略)【9月17日 WEDGE「サウジ石油攻撃、イラクから発進か?トランプ氏の報復示唆で緊張」】
*********************
攻撃は、施設の重要部分を狙ってピンポイントの正確さで行われており、攻撃能力の高さがうかがえます。
****フーシ派による武器増強****
フーシ派は2015年から、イエメンでサウジアラビア主導の連合軍と戦いを展開しており、そして、サウジの防衛をすり抜けることができる長距離の攻撃能力を増強していると、これまでに何度も表明している。
3月にはサウジの領空境界から120キロ以上入ったところにある淡水化施設をドローンで上空から撮影し、その映像を公開した。
また5月には、サウジの東部州から紅海までつながる主要パイプラインをドローンで攻撃し、一時的に閉鎖に追いやった。さらに6月には、少なくとも20基のミサイルとドローンでサウジを攻撃し、犠牲者を含む被害が出ている。
英ロンドン大学キングスカレッジのアンドレアス・クレイグ教授は、「フーシ派は近年、特に弾道ミサイルとドローン技術を大幅に増強している」と、一連の攻撃発生時にAFPの取材で述べていた。
フーシ派が公開した動画には少なくとも15機の無人ドローンとさまざまなミサイルが捉えられていた。フーシ派によると最新兵器には、「アルクッズ(エルサレムの意味)」と名付けられた長距離巡航ミサイルや爆弾を搭載し、1500キロ先のターゲットも攻撃できるドローン「サマド3」が含まれているという。
サウジアラビア主導の連合軍報道官は16日、今回の攻撃に使われた武器が「イランからのものだということをすべての状況が示している」と指摘した。
専門家らは、ドローンの脅威がこれからも続く見込みで、国家の防衛や反政府組織の武器をも変えていくとの見方を示している。 【9月17日 AFP「サウジ石油施設攻撃、国家防衛の見直し迫るドローンの脅威」】
****************
今回の攻撃については、トランプ大統領やポンペオ米国務長官、エスパー米国防長官の発言は相次いでいますが、実際に攻撃を受けたサウジアラビアからの発言がありません。
サウジアラビア主導の連合軍が16日、攻撃に使われた武器はイラン製だった(まあ、それはそうでしょう。誰がやったかは別にして)と発表したことぐらいでしょうか。
サウジの発言を私が見落としているのかもしれませんが、そうだとしても“見落とす”ぐらいのものだということでしょう。
単に状況を精査しているということかもしれませんが、ここから先は全くの素人の想像ですが、サウジとしては国家の根幹でもある石油施設が「あまりにも脆弱」であるという現実を踏まえて、イランとの関係を決定的に悪化させ、報復合戦に陥るような事態を懸念し、慎重に対応を検討している・・・ということかも。
仮にイランとの間での大規模な武力行使といった事態になれば、今回の攻撃で明らかなったように、サウジの石油施設は最初の一撃でひとたまりもないでしょう。その後の戦闘で勝とうが負けようが、いくらアメリカがトマホークをイランに撃ち込もうが、サウジにとっては国家の根幹を失うということにはかわりありません。
【アメリカの対イラン強硬派・・・アメリカが弱腰だからイランにつけこまれる】
一番の関心事となっている「誰がやったのか?」ということについては、いろんな考えが報じられています。
アメリカは「イランがやった」ということのようですが、先日のタンカー攻撃のときと同様に、決定的な証拠は示してはいません。攻撃の向きがイラン・イラク方面からのもので、イエメンからは難しい云々も、証拠としてはやや迫力を欠きます。
そうしたなかで、アメリカの対イラン強硬派は、直接にせよ、間接にせよ、イランの関与は間違いないという前提で、以前トランプ大統領が対イラン攻撃を直前に取りやめたように“弱腰”だからイラン側につけこまれるのだ・・・との主張です。
****【社説】サウジ石油施設攻撃はイランの答え ****
イランを警戒していたボルトン氏は正しかった
ドナルド・トランプ米大統領が2015年のイラン核合意からの離脱を表明して以来、イランは中東各地で軍事的緊張を高め、米国の決意を試してきた。
(中略)イランは攻撃への関与を否定しているが、直接的な衝突を避けるために代理組織を使うのがイランの常とう手段であり、他に思い当たる犯人もいない。
(中略)攻撃を行ったのがフーシ派ではなかったとしても、イランはイエメンでアラブ有志連合と戦うフーシ派を支援している。フーシ派はサウジ国内や紅海を航行する石油タンカーへの攻撃を激化させている。
もしサウジがイエメンをフーシに奪われれば、イランはアラビア半島をめぐる代理戦争にも勝利したことになる。サウジは理想的な同盟国とは言い難いが、サウジへの支援打ち切りを求める米上院議員は、イランに中東地域の覇権を握らせないための代替案を考えるべきだ。
ホワイトハウスによると、トランプ氏はサウジのムハンマド皇太子と電話会談し、米国による支持を約束した。しかしホワイトハウスは言葉だけで終わらせるべきではない。
イランはサウジに対してだけではなく、トランプ氏にも探りを入れている。「最大限の圧力」をかけるというトランプ氏の決意を試し、弱みをかぎつけている。
イランが夏に米国の無人機を撃墜したが、トランプ氏は軍事的報復の提案を拒否した。イランの対外工作を担うコッズ部隊のカセム・ソレイマニ司令官はこれまで、こうした抑制的な動きがあると、イラン側に分があり事態をエスカレートさせても問題ないと解釈してきた。
トランプ氏はイランのハッサン・ロウハニ大統領との直接会談についても前向きで、ポンペオ氏は国連総会の場での首脳会談を提案した。
トランプ氏はエマニュエル・マクロン仏大統領が提案したイランへの150億ドル(約1兆6200億円)の支援への支持も検討している。週末の攻撃はそうした米国の動きに対するイランの答えだ。(中略)
トランプ氏がジョン・ボルトン氏に謝罪することになるかもしれない。ボルトン氏は、イランがホワイトハウスの弱点を見つけてはそこを突いてくると繰り返し警告してきた。
そのボルトン氏は先週、イラン政策などをめぐる意見の相違から大統領補佐官を辞任した。週末の攻撃はボルトン氏が正しかったことをはっきりと証明した。トランプ政権の圧力キャンペーンは効果を上げている。今それを断念すれば、イランはこれまで以上に軍事的リスクを取るだろう。【9月17日 WSJ】
*****************
【外交プロセス進展を阻止する狙いのイランあるいはイラン関連の強硬派の犯行か】
この種の主張は「イラン」とひとくくりにしていますが、イラン内部にはアメリカとの緊張関係を望む強硬派と、市民生活の安定を優先させ、アメリカとの関係改善を志向する穏健派の微妙なバランス・綱引きが存在します。
対イラン強硬派からすれば、「イランに強硬派も穏健派もない、イランはイランだ」ということなのでしょうが、そうした強硬派と穏健派の存在ということを重視すると、アメリカとの対話が取り沙汰されるようになった矢先の今回攻撃は、(新たな制約がイランに課されることにつながる)対話による緊張緩和を嫌う強硬派による対話潰しではないか・・・との推測がなりたちます。
その、イランおよびイランが支援するサウジ攻撃能力を持つ強硬派としては、イラン革命防衛隊、イエメンのフーシ派、イラクの民兵組織「人民動員隊(PMF)」があげられています。
****サウジ石油施設への攻撃、背後に潜む意図とは****
外交は難しい作業だ。対照的に、外交を停止させるのは比較的容易だ。中東地域の強硬派はそれを知っており、その認識の下、これまで長年にわたり行動してきた。
週末にサウジで起きた石油施設への攻撃の後でも、この経験則を頭に入れておくことが重要だ。今回の攻撃では、サウジの2つの石油施設が被害を受け、そのうち1つは世界で最も重要な原油処理施設だった。
攻撃が誰の仕業なのかは依然分かっていない。イランの支援を受けているイエメンの反政府武装勢力「フーシ派」は、自らの犯行だと主張している。フーシ派は、イエメンの隣国であるサウジと激しい対立を続けている。
しかし、マイク・ポンペオ米国務長官は、直接イランに非難の矛先を向けている。米当局者らは16日、さらに踏み込んで、イランの領土内からミサイルが発射されたことを示す情報があると語った。
いずれにせよ、攻撃のタイミング自体に、大いに怪しむべき点がある。攻撃が行われたのは、まさにドナルド・トランプ米大統領が今月下旬の国連総会の場でのイラン大統領もしくは外相との外交交渉を可能にするため、厳しい対イラン経済制裁の若干の緩和を検討していた時だった。フランスも、まさにこうした若干の関係改善に向けて、精力的な働きかけを行っていた。
しかし、突然始まった外交的動きを好ましく思わない勢力も多い。そのうち一部は、動き始めた外交プロセスを停止させるような危機を生み出すため、ミサイルを活用できる立場にある。恐らくこれが、週末の出来事の説明になると思われる。
容疑者リストの筆頭に挙げられるのは、イラン政府内の強硬派だ。国際社会のみならずイラン国内でも、多くの人々は、オバマ前政権下でまとめられたイラン核合意からの離脱をトランプ氏が決めたことを危機と捉えた。しかし、イラン国内の一部強硬派は、これを好機と受け止めた。
イラン革命防衛隊の指導者を含む強硬派は、そもそも核合意を好意的に受け止めていなかった。むしろ核合意が廃棄されれば、核および弾道ミサイル開発の取り組み強化の論理的根拠になると考えている。
またイランの強硬派は別のことも知っている。米国との外交的なダンスをやめることに加え、サウジの石油施設を攻撃すれば、欧州とアジアの指導者たちを怖がらせ、米国の経済制裁に対する何らかの救済措置を引き出せるかもしれないことだ。
もちろん、それでイランが攻撃を仕掛けたという証明にはならない。ただ単に、強硬派はサウジの施設が火を吹いているのを見て悲しいとは思わないということだ。
イエメンのフーシ派は、緊張を高めることに同様の関心を持つ。イランから全面的な支援を得ているフーシ派は、サウジとの代理戦争を行っているようなものだ。サウジは国際的に認知されたイエメン政府の復権を試みている。
フーシ派には、サウジの施設を攻撃する彼らなりの理由が多くあり、サウジによる残忍な空爆への報復として頻繁に攻撃を行っている。
しかし、フーシ派には外交プロセスが始まることを懸念する理由もある。彼らは、イランと米国、そして米国の友人であるサウジとの緊張を緩和させるいかなる外交プロセスからも置き去りにされかねない。
またフーシ派は、米議会でサウジへの支持が脆弱(ぜいじゃく)になっていることも知っているはずだ。議会では、サウジ人ジャーナリストのジャマル・カショギ氏暗殺においてサウジ政府が果たした役割や、その他の人権侵害への懸念が収まっていない。共和、民主両党の議員は週末にトランプ政権に対し、今回の攻撃を受けてサウジとフーシ派およびイランとの戦いに米国が引きずりこまれてはならないと警告した。
要するにフーシ派には混乱を継続させるだけの十分な動機があるということだ。また彼らは、同じことをやりがたっているイランの強硬派の代理として活動することが可能である。
一方、イランの別の代理勢力もある。同じような動機を持つイラクの民兵組織「人民動員隊(PMF)」だ。PMFはイラン政府の暗黙の了解とイラン革命防衛隊の活発な支援を得てイラク国内に勢力地域を確保し活動している。イスラエルはPMFをイラン強硬派の前哨基地とみなして強く懸念しており、その表れとして過去数週間、PMFの施設を攻撃している。
重要な点は、これら勢力―イラン国内の強硬派、イエメンのフーシ派、イラクの親イラン派―のいずれもが、外交交渉が本格的に動き出す前にそのプロセスを停止させようとする動機を持っていることだ。米国とイランの間のどんな合意であれ、そこには、イランによる周辺地域の過激派に対する支援の縮小、その見返りとして米国による貿易制裁の緩和が含まれるだろう。
そうした交渉に基づく結果は、現状ではとても実現しそうもないように思われる。とはいえ、そのアイデアがトランプ氏の関心をある程度引いているのは明らかだ。
トランプ氏は15日のツイートで、自身がイラン指導者との前提条件なしの会談を行う用意があると示唆したとの報道内容は「フェイクニュース」の典型だと指摘した。
しかし、トランプ氏は今夏、NBCニュースのチャック・トッド氏とのインタビューで同じ内容のことを話していた。イラン指導者との会談のために前提条件はあるのかと聞かれたのに対し、トランプ氏は「私に関する限りはない。前提条件なしだ」と答えていた。
中東の悪人たちの大半が承知している通り、そうした外交プロセスを阻止する最善策はアイデアがゆりかご段階にある時に始末しておくことである。【9月17日 WSJ】
*******************
もし、今回攻撃が上記のようなイラン・アメリカの緊張を和らげる外交プロセスを阻止する目的でなされたのであれば、今回攻撃に対する「報復」は武力行使ではなく、彼らの嫌う外交プロセスを遅滞なく強力に推し進めることでしょう。
ただ、“イランの最高指導者ハメネイ師が17日、テヘランで演説し、「いかなるレベルであっても、二国間でも多国間であっても、我々は米国と協議しない」と述べ、トランプ米大統領が求めてきた米との直接交渉の拒否を明言した。”【9月17日 読売】ということで、現実には難しいハードルがあります。
【交渉に向けた圧力のつもりが“うまく行き過ぎた”との見方も】
なお、イランが交渉を有利に進めるために圧力をかけようとして攻撃を行ったが、“うまく行き過ぎた”という見方もあるようです。
****イランは計算違い?****
イラン指導部は最近、トランプ大統領の再選の可能性が濃厚であり、制裁で締め付けられている同国を経済的な崩壊から救うためには最終的に、トランプ氏と交渉せざるを得ないとの結論に達したと伝えられている。
そのためには、イラン配下の勢力を使って軍事的な緊張を作り出す一方で、トランプ氏との交渉に応じるというシグナルを送る“二重戦略”に転換したとされる。要はトランプ氏に「イランと交渉した方が再選に有利」と思わせて交渉に引き込むことが狙いだ。
トランプ大統領は無条件でイランのロウハニ大統領との交渉に応じるという姿勢を示し、離脱した「イラン核合意」に代わる合意をまとめることに意欲を見せ、17日から始まる国連総会の期間に訪米するロウハニ大統領との会談が実現する可能性が取りざたされていた。
トランプ氏は「イラン核合意」がイランに核開発の権利を認めていたのに対し、そうした権利を与えない合意に達することに自信を示している。
イランが米国の主張通り、サウジ攻撃に関与していたとすれば、「これほど攻撃がうまくいくとは想定していなかったのではないか。イランと交渉しないと、地域の安定はありえないことを示すために、小規模の損害を与えるつもりが計算違いで大打撃を与えてしまった」(ベイルート筋)との見方もある。
狂ったシナリオにどのような結末が待ち構えているのか、米・イラン首脳会談が遠のいたことは確かなようである。【9月17日 WEDGE「サウジ石油攻撃、イラクから発進か?トランプ氏の報復示唆で緊張」】
**********************
いろんな見方がありますが、真相はもう少し様子を見ないとわかりません。
ただ、先述のように、イラン内部の強硬派による外交プロセスを阻止する目的でなされたのであれば、今回攻撃に対する「報復」は武力行使ではなく外交プロセスの前進であるということは十分に念頭に置いておく必要があります。