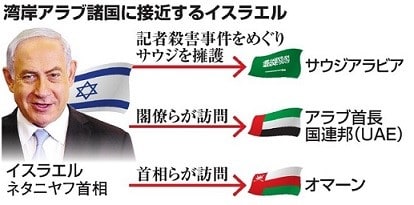(イラン・テヘランで女性のヒジャブ取り締まりで群衆ともめる宗教警察(多分、黒ずくめの女性)【2月20日 CNN】)
【自由を求める市民 アメリカ文化への憧れも】
いつも書いているように、イランは宗教・政治世界で力を有する保守強硬派と、自由な生活を求める一般市民の思いがせめぎあう関係にあり、そうした微妙なバランスの上に穏健派のロウハニ政権は成り立っています。
そんなイランで興味深い記事が。一般市民が宗教警察の取り締まりを実力で阻止したというものです。
****ベール着用違反の女性ら、連行を群衆が阻止 イラン****
イランの首都テヘラン市内で先週、イスラム教のベール「ヒジャブ」を正しく着用していないとして女性2人を連行しようとした宗教警察の車両が、通行人らに襲撃される騒ぎがあった。
騒ぎは15日、保守強硬派のアフマディネジャド前大統領の自宅があるテヘラン東部ナルマク地区で起きた。国営イラン通信(IRNA)によると、群衆は警察車両のドア1枚を破壊し、警察側が空中に威嚇射撃する場面もあった。女性らが車両から解放されると、群衆は解散したという。
現場の映像には、クラクションを鳴らして抗議する市民らの姿や、車両を取り囲む集団の様子などが映っている。
イランでは1979年の革命以来、女性のヒジャブ着用が義務付けられてきたが、最近はソーシャルメディアなどを通し、これに抵抗する運動も広がっている。
頭全体を覆うヒジャブの代わりに短いスカーフだけで外出したり、スキー場で帽子姿になったりする女性も多く、着用の規則に違反した場合も逮捕ではなく15ドル(約1700円)程度の罰金で済むなど、戒律の適用は緩み始めていることがうかがえる。【2月20日 CNN】
******************
アメリカ・トラン政権は、核合意から離脱し、イスラエルやサウジアラビアなどとともにイラン包囲網を形成して、イランを徹底的に叩く姿勢を続けていますが、上記のように自由な生活を望む多くの市民は、むしろアメリカ文化には憧れ的なものを抱いており、「アメリカに死を!」といったスローガンとは異なる側面も見られます。
****憧れつつ「米国に死を」叫ぶ イランの複雑な対米感情****
かつて米国のブッシュ(子)大統領から、金正日政権の北朝鮮、フセイン政権のイラクとともに「悪の枢軸」と非難されたイラン。
最近でも、トランプ米大統領がイランを「世界随一のテロ支援国家」と罵倒すれば、イランも最高指導者ハメネイ師が「悪と暴力の権化」とやり返す。
ペルシャ湾に面した産油国イランと米国の関係はどうして、ここまでもつれたのか。また、イランの人々は米国にどんな感情を抱いているのか。
イラン政府にとって米国は、体制転換を狙う「敵国」との位置づけだ。それには幾つかの理由があり、敵視の根は長く、深い。
イランは1953年、当時のモサデク政権が、米中央情報局(CIA)の関与した軍事クーデターで転覆させられた過去を持つ。また現在のイスラム体制は、79年に親米のパーレビ王朝を打倒した革命で成立している。革命翌年の80年に始まったイラン・イラク戦争では、米国にイラク支援に回られた経験もある。
さらに、自国の核開発疑惑をめぐり、2011年以降、国連安全保障理事会だけでなく、米国独自の厳しい制裁を科せられ、経済への打撃が続いている。オバマ政権時代の16年には、核合意に基づいて制裁が一部解除されたが、昨年8月以降は、トランプ政権によって再び制裁が復活した。
一方、米国にとって、イランに対する敵視政策が決定的になったのが、79年11月に起きた在テヘラン米国大使館占拠人質事件だ。解決までに444日かかり、米政権と米国民に強くイランへの嫌悪感を刻み込んだ。
これに加え、米国内ではイランと対立するイスラエルロビーや、親イスラエルが多いキリスト教福音派の存在が大きく、米国の対イラン政策に影響を及ぼしている。
政治家にとって、イランへの敵視が、選挙の票や資金集めに役立つ構図ができている。特にトランプ氏は福音派を最大の支持母体にしており、長女イバンカ氏の夫で敬虔(けいけん)なユダヤ教徒のクシュナー氏が大統領上級顧問を務めるなど、政権内に親イスラエルの考えをもつ幹部が多い。
トランプ政権の誕生後、イランの首都テヘランなどで行われる反米デモは激しさを増している。ただ、参加者は国民の一部で、イラン人の米国観は複雑だ。
テヘランではiPhoneなどの米国製品が人気を集めるほか、米国の有名なハンバーガーショップをまねたとみられる店舗などもあふれかえる。
市内で売られる海賊版やネットのダウンロードで、米国の音楽やハリウッド映画を楽しむイラン人も珍しくない。米政府やトランプ氏は嫌いでも、米文化への憧れを持つ人が多いのが実情だ。
あるイラン人の30代女性は「リーバイスのジーンズにナイキの靴をはき、左手にiPhoneを持ちながら、右の拳を突き出して『米国に死を』と叫ぶ。これがイラン人だ」と話す。
最近でも、オバマ前大統領の妻ミシェル氏が書いた回想録「Becoming」のペルシャ語版が、イランでベストセラーになっている。イランメディアによると、1月15日にペルシャ語の翻訳版が発売された後、すでに16回増刷され、「記録破りのペース」(イランのメヘル通信)という。(中略)
イラン人ジャーナリストも「オバマ氏は大統領だった時期に、(穏健派とされる現在の)ロハニ大統領と電話会談した。イランでは当時、米国との無意味な争いに終止符が打たれるのではないかとの希望が広がった。多くのイラン人の心にその記憶が今も残っている」と言う。
ただ、トランプ政権のイラン敵視政策が続くなか、ロハニ師も、イスラム体制の堅持を掲げる最高指導者ハメネイ師ら、国内の保守強硬派に配慮せざるを得ない状況だ。
イランの国是である「反米」を唱える政府の主張と、米国文化を受け入れている国民の意識は、どこまで重なるのか。私たちは、目をこらしていく必要がある。【2月13日 朝日】
*******************
【制裁で困窮する一般市民】
一方、経済的にはアメリカの制裁はイラン経済・市民生活を確実に締め上げています。
****イラン観光地、悲鳴=制裁や通貨暴落で「収入激減」****
トランプ米政権が「前例のない経済的圧力」として制裁を復活させ締め付けを強めているイランでは、主要産業の観光が大打撃を受けている。通貨リアル暴落やインフレ激化でイラン人の購買力が低下し、業者の収入も激減。観光で生計を立てる人々は悲鳴を上げている。
サファビー朝の都として繁栄を極め、かつては「世界の半分がここにある」と称されたイラン中部の観光地イスファハン。2月上旬、中心部にある世界遺産のイマーム広場は観光客でにぎわっていた。ただ、広場を囲むように土産物店が並ぶバザールの店主らの表情はさえない。
「2年前に比べて客が激減した。生活費は4倍に上がったのに、収入は3分の1だ」。バザールにある宝石店のファルハドさん(35)は肩を落とした。ペルシャ特有の繊細な柄の雑貨を売るアリさん(30)も「雑貨は必需品ではないので、家計が苦しければ買ってもらえない。通貨の価値が下がって商品の価格を倍にしたが、客には申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と嘆く。
国際社会との融和を志向したロウハニ政権の下、一時は制裁も解除されて経済が上向き、イスファハンでも欧米の観光客が増えた。
ただ、イランを敵視するトランプ政権発足で事態は一変。政治的緊張も高まったせいか、今ではその姿はまばらだ。
衣料品店で働くモハンマドさん(20)は「来るのはイランより貧しい国の人ばかりだ」と、欧米に代わって近年増えているイラクやシリア、アフガニスタンなどからの訪問者をやゆする。
国内に23の世界遺産を有するイランは、経済活性化の一つとして2025年までに年間2000万人の外国人旅行者誘致を目指すが、その前途は多難だ。(後略)【2月16日 時事】
*********************
イランの観光資源は素晴らしいものがあり、本来はもっと多くの観光客に楽しんでもらえるものなのですが。
イランの経済が制裁で締めあげられているといっても、保守強硬派の革命防衛隊などが手広く独占的に行っている事業は、制裁で自由な経済活動が抑制されるほど、逆にうま味が増すところがあり、アメリカの経済制裁は反米・保守派と利害が一致している面があります。
【トランプ政権の対決姿勢で、勢いを増すイラン保守強硬派 揺らぐ穏健派ロウハニ政権】
アメリカの制裁で市民生活が困窮すれば、当然に核合意を主導し、制裁解除・経済の回復を語っていた穏健派ロウハニ政権への視線は厳しいものに変わります。
政界にあっては、核合意が進められていたころはやや身を潜めた感もあった保守強硬派が政権批判を強め、穏健派ロウハニ政権の求心力は揺らいでいます。
核合意を主導したザリフ外相の辞任騒動は、そうしたロウハニ政権の苦境を象徴する出来事でした。
****イラン保守強硬派、圧力強める 穏健派の外相、辞意表明 核合意の立役者、大統領は慰留示唆****
イランのザリフ外相は25日、自身のインスタグラムに「職務を続けるには不適任で、在任中の全ての不足点を謝罪する」と記した画像を投稿し、辞意を表明した。
ロハニ大統領は慰留する考えを示唆した。ザリフ氏はイラン核合意の立役者で、米国の合意離脱と制裁再開によるイラン経済の停滞を受け、保守強硬派からの批判が強まっていた。
ザリフ氏の辞意表明に対し、ロハニ師は26日、テヘランでの演説で「厳しい状況でのザリフ氏の仕事ぶりに感謝する」とし、慰留する考えを示した。対外融和路線をとる保守穏健派のロハニ政権にとってザリフ氏は象徴的な存在で、辞任すれば大きな痛手になる。
イランでは米国の制裁再開で、国民生活が圧迫されている。国内の保守強硬派は「核合意で米国に妥協した上に経済もよくなっていない」と政権を批判しており、ザリフ氏は主要な標的になっていた。
イランのネットメディアは26日、ザリフ氏が「辞意は外務省の地位を守るためで、(撤回させるための)懐柔は必要ない」と取材に語ったなどと報じた。
国営メディアなどによると、外相にもかかわらず、25日にシリアのアサド大統領のイラン訪問を事前に知らされず、ロハニ師との会談にも同席出来なかったという。
イラン政府関係者は、「たとえザリフ氏が翻意しても、イランの外交政策に亀裂が生じたのは事実で、今後の政権運営に悪影響だ」とみる。【2月27日 朝日】
*********************
ロウハニ大統領は「辞任を受け入れることは国益に反する」として辞任を認めない考えを示し、結局、ザリフ外相も辞意を撤回してロウハニ政権にとどまることになりました。
保守強硬派からの厳しい批判の矢面に立つザリフ外相が、ロウハニ大統領に対し「自分をとるのか、保守派に屈するのか、明確にしてくれ」との踏み絵を迫った・・・という一件でしょうか。
ただ、下記の記事なども併せると、保守強硬派主導の流れがイラン政治で進んでいるようにも思えます。
****イラン、司法府代表に保守派重鎮 最高指導者ハメネイ師が任命****
イランの最高指導者ハメネイ師(79)は7日、サデク・ラリジャニ司法府代表の後任として保守強硬派の重鎮、ライシ前検事総長(58)を任命した。
ハメネイ師のウェブサイトで明らかにした。ライシ師は高齢のハメネイ師の信頼が厚いとされ、有力な後継者候補の一人との見方もある。任期は5年。
ライシ師はイラン北東部マシャド出身でイスラム教シーア派の聖地コムで学んだ聖職者。1979年のイラン革命後は革命体制の秩序を強権で維持する司法当局の要職を歴任し、2014年に検事総長に就いた。
16年にはハメネイ師に国内最大聖地のイマーム・レザー廟の最高位に任命された。【3月8日 共同】
****************
ライシ師は2017年の前回大統領選挙でロウハニ師に敗れた、反米・保守強硬派を代表する人物です。
司法面でも懸念されるニュースが。
****イランの人権派女性弁護士、有罪判決か 人権団体が発表****
イランの人権派弁護士で、欧州議会が人権や民主主義を守る活動で功績があった人に贈るサハロフ賞の受賞者ナスリン・ソトウデさんがイランの裁判所で有罪判決を受けたと国際人権団体などが、7日までに明らかにした。
ソトウデさんは昨年6月に当局に拘束されたとみられ、数十年にわたる禁錮刑に処される可能性があるという。イラン当局は、判決などについて公表していない。
「イラン人権センター」(米国)によると、ソトウデさんは、公共の場で髪の毛を隠す布(ヘジャブ)の着用義務に抗議して拘束された女性の弁護をしたことなどで、国家安全保障を侵害した罪などに問われているとみられるという。【3月7日 朝日】
*******************
アメリカ・トランプ政権がイランを締め上げるほどに、イランでは反米・保守強硬派が力を増し、市民生活の自由は奪われるという残念な結果になります。イラン保守強硬派にとって最大の協力者はトランプ大統領という関係です。
トランプ大統領の対決姿勢がもたらす成果は、宗教支配の体制転換ではなく、せいぜいが穏健派政権の崩壊・反米保守強硬派政権の誕生でしょう。そして核開発の再開、中東情勢の緊張、市民の自由抑圧、宗教支配の強化・・・。
それでもトランプ大統領は「偉大な勝利」とツイートするのでしょう。何が“勝利”なのかは知りませんが。