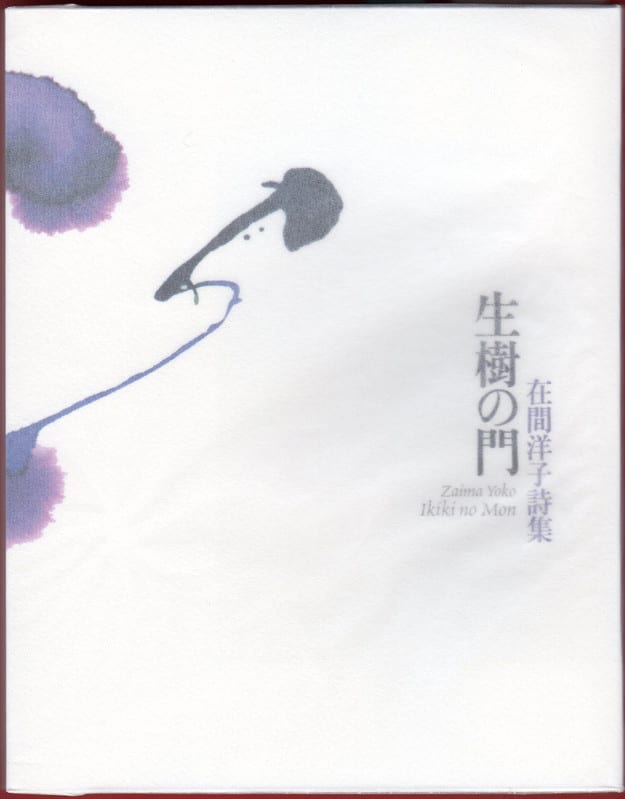在間洋子さんから詩集『生樹の門』をお贈り頂いた。
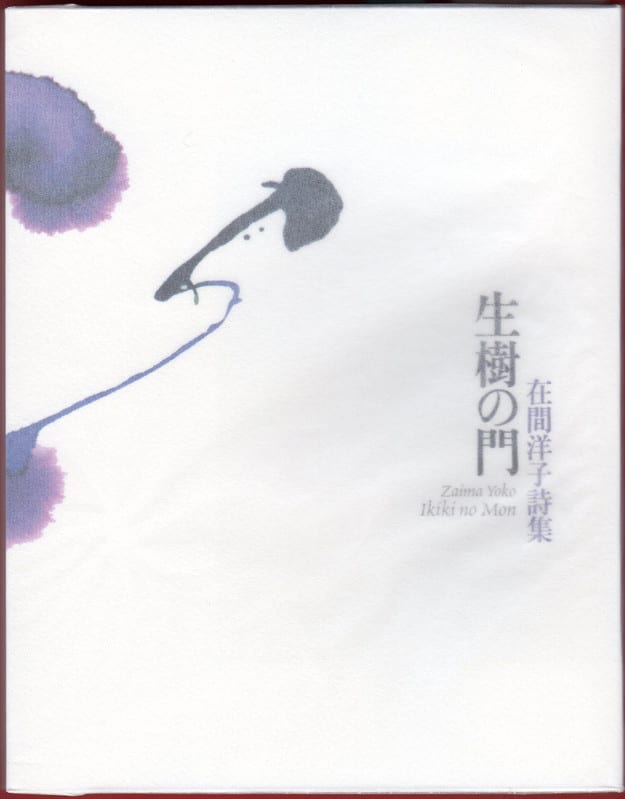
彼女は詩歴の長い人です。経歴を見ると1968年に高田敏子さん主宰の「野火の会」に入会しておられる。
わたし、お姿をお見かけしたことはあるが親しくお話をさせて頂いたことはない。
でも、加古川の高橋夏男さんが送って下さる詩誌「別嬢」でいつも作品を見せて頂いている。
さて今回の詩集ですが、一読、多彩な作品が並んでいる。
一つのテーマに縛られず、ご自分の心を動かせたいろんなことがらを詩に昇華しておられる。
巻頭詩はこれです。
 ←画面をクリックしてお読みください。
←画面をクリックしてお読みください。
日常の表層を描きながら、さりげなく心の内を差し出していて上品だ。
そうかと思えばこのような作品も。


見事なユーモア!わたしこんなん大好きです。
そして、このようなしみじみと読ませる作品も。


「ほろり と去ってゆくひと」など見事な一行ですね。 よく言葉を選んでおられる。
・
表題の「生樹の門」は巻末に置かれている。


産土の地を語りながら、詩作を通じてのご自分の人生の覚悟のようなものが見える。
まことに誠実で清らかな人物なのでしょう。
そして感心したのが「あとがき」です。

多くは書かれていないが、高田敏子さんの言葉「上手に書かなくていいのですよ。自分自身の目で、耳で感じとったものを言葉に、でも言葉を選んでね」というのが印象的。
この教えを守ってこられたという気がする。
真摯に詩に向かえばこのように人間を磨くことになるのですね。ああ、わたしはダメだ。










 「え?そんなことないやろ。わたしお客さんには特に気を使ってるけどなあ」
「え?そんなことないやろ。わたしお客さんには特に気を使ってるけどなあ」