戦前の難しい漢字が今の簡単なものになり、当用漢字で数も少なくなったことで、覚えることが少なくなって有難いと思っていたバカな私です。
それでも、ネットのお陰で日本語の素晴らしさを知るにつれ、何とも勿体無いことをしてしまったのだろうと、戦後教育に疑問を覚えたものです。
ところが、いつものねずさんが、1月19日 、第1310回の「筆順が日本人をアホにする」で、筆順にまでGHQの工作がされていたことに改めて驚かされました。
一日も早く教育の改正が必要ですが、やってることは全く逆のようです。これも、あの前川なんてトップにするような文科省の日本人をバカにする意図があるようです。
ねずさんが、再び警告を発してくれています。
大和心を語る ねずさんのひとりごとより 2018年03月28日
漢字の筆順と日本人の文化性
以前にも書きましたが、漢字の旧字が、今使われている新字に改められたのは、日本が占領下におかれていた昭和21年11月16日のことです。
このときに、GHQの指導によって、当用漢字が定められました。
公文書や出版物などは、その漢字のみを用いるようにとされ、これに呼応して学校教育の現場でも、新字のみが教えられるようになり、さらにこれに追い打ちをかけるように、漢字の筆順までが変えられるという状況となったのです。
これによって、たとえば礼儀作法の「礼」ならば、もともとは「禮」と旧字で書かれることで、「相手にはっきりとわかるように豊かに示すことが礼なのだ」と、誰もが漢字を通じて「文化の共有」ができていたものが、まったくできなくなりました。
「礼」という新字を見て、これで漢字の意味をとれる人など、およそ皆無だと思います。
ですから昔の教育現場では、系統学習と言って、まず「示偏(しめすへん)」は、示(しめ)すことだと教え、「豊」という漢字は「ゆたか」であることが教えられます。
その上で、「禮」という字を先生が黒板に書いて、
「この字が意味するものは何か、みんなわかるかな?」
と生徒たちに質問したわけです。
そして、
「そう。相手にわかるように
豊かにしっかりと示すのが禮なんだ。
だから君たち、
ちゃんと相手にわかるように
相手の目を見て、
深々とお辞儀をして、
おはようございますとか、
こんにちはとか、
言うんだよ。
それが禮なんだ」
と、教えたわけです。
つまり生徒たちは、漢字と読みをただ丸暗記するのではなくて、その意味を推理し理解し、それだけでなく漢字を通じて文化を共有して行ったわけです。
だから学校がおもしろい。
授業が楽しい。
小学生の子供達が、片道6キロも7キロもある道のりを、雨の日も雪の日も歩いて毎日学校へ通い、田植えがあるから学校を休めと親に言われると、泣いて悔しがったというのも、うなづけます。
おそらくいまの日本の学校では、考えられないことであろうと思います。
それもそのはずです。
いまの教育ならば、先生が黒板に「礼」と書いて、「この字は<れい>と読みます」とだけ教えます。
そして「テストに出るよ」と言うから、生徒たちは、「礼=れい」だと、ただ丸暗記するだけです。
そこには推理も理解も、文化の共有もありません。
ただテストに出るからと、丸暗記があるだけです。
これでおもしろいと感じる生徒がいるなら、むしろ神経を疑う。
徳という漢字を見せられて、
「徳とはどのような意味ですか?」
と質問されたとき、ちゃんと即答できる人は、おそらくあまりいないと思います。
けれど徳という字は、もともとの古字は「彳悳」で「彳+直+心」でした。
彳(ぎょうにんべん)は、進むという意味がありますが、要するに真っ直ぐな心で進む(生きる)ことが、徳の意味だとわかるわけです。
ところがこの字は、直の目の部分が横倒しにされて「またまたテレビで「漢字の書き順が昔と今と違っている」という特集が組まれるのだそうです。
なるほど学校教育の現場での、筆順は、昔と今とでは違っています。
だから「このように変わりましたよ」ということをいいたい番組のようなのですが、問題はむしろ、
「どうしてそのように変わったのか」
にあるのではないでしょうか。…以下略
これ以上日本人を劣化させたい意図が感じられますが、やはり文科省も特亜3国に乗っ取られているのでしょう。
それにしても、政治もそうですが官僚の劣化も酷すぎますね。こんなことで日本の再生は出来るのでしょうか。
とは言いながら、日本が再生して世界を導くようにならなければ世界も消滅でしょう。日本人の目覚めが望まれます。それこをが世界を救うはずです。
最新の画像[もっと見る]










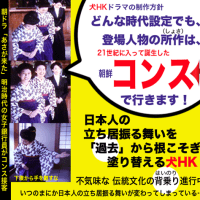
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます