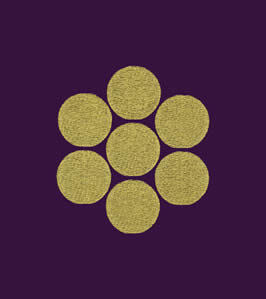☆髪結いの亭主(1990年 フランス 82分)
原題/Le Mari de la coiffeuse
監督・脚本/パトリス・ルコント 音楽/マイケル・ナイマン
出演/ジャン・ロシュフォール アンナ・ガリエナ アンヌ・マリー・ピザーニ
☆「愛に溺れる。前よりも、深く」
ってのが公開時のキャッチコピーなんだけど、
ここでいう「前」ってのは、誰の「前」なんだろ?ってこと。
以前の恋っていうんなら、女理髪師にして妻アンナ・ガリエナの「前」だろう。
彼女の手首にはひとすじの傷痕が入ってる。むかし、恋い焦がれた男がいて、その男との愛に溺れていたんだけど、自分を愛してるふりをしているんだと気づいたとき、彼女は手首を切った。男に別な女が出来て棄てられるかもしれないっていう絶望からじゃなく、たぶん、男の愛が冷めてきたことで自分のプライドが崩壊したからだろう。
それが「前」なんだけど、これについてもうすこし考えよう。
アンナ・ガリエナにとって、愛されるということは、男が自分の価値を認めてるってことで、それはすなわち、自分の美貌がいまだに相手を溺れさせてるっていう満足感だ。
ところが、愛しているふりを男がするときには、自分に対する憐憫が芽生えてる。自分が以前ほどに魅力的ではなくなってるけど嫌われたわけではないため、男は自分を傷つけまいとして愛しているふりをする。つまり、恋い焦がれてはいないものの、家族や相棒とかいった感じで愛してくれてる。
そんなのは憐れみでしかないし、憐れまれている自分は哀れだ。だったら、もう生きていても仕方ないから、手首を切ろう。
てなことで、彼女の「前」は終わったんだけど、自殺未遂だったもんだから、アンナ・ガリエナとしては次の恋に生涯を賭けるよりほかになくなっちゃった。
で、彼女とはまるでちがった「前」を持ってるジャン・ロシュフォールに出会った。ジャン・ロシュフォールの「前」は、ほんわかしたものだ。幼い頃から女理髪師のアンヌ・マリー・ピザーニに憧れていたジャンは、おとなになって、アンヌが他界したあと、アンナ・ガリエナと出会った。
かれにとって人生は、髪結いの亭主になるということしかない。
簡単にいってしまえば、ヒモになるってことなんだけど、もしかしたら、理髪店の経営者におさまっていたのかもしれない。でも、経営してようがしてまいが、そんなことはどっちでもいい。ジャン・ロシュフォールは客がいようといまいと、その視線が自分たちから外れていれば、アンナの肉体を賞玩し、愛撫するっていう唯それだけの人生を送れればいいわけだ。
でも、アンナは、ジャンにいうんだな。
「約束してちょうだい。愛しているふりだけはしないで」
愛しているふりさえしなければ、自分はあなたに尽くしてあげると。
あなたがヒモだろうと、生活破綻者だろうと、そんなことは関係ない。わたしを綺麗だとおもい、わたしを欲し、わたしを満足させてくれるなら、わたしが、あなたの面倒くらい最後まで見てあげる。だから、約束して、というわけですよ。
ところが、ジャンとしては約束してるつもりだし、このまま愛を交わし合っていけば、一生、幸せに暮らしていけるとおもうんだけど、幸せの絶頂にあるアンナからすると、そうじゃなくなってくのがわかるんだよね。で、川へ飛び込むんだけど、手紙を一通残していくんだ。
「あなたが心変わりして不幸になる前に死にます」
こうなっちゃうと、もう、手に負えないっていうか、アンナは死ぬしかないわけで、男と女の寓話ってのはこんな感じなんだろかともおもえてくる。
まあ、エドゥアルド・セラの撮影も情感と官能がたっぷり匂ってるし、なんといっても、マイケル・ナイマンのイスラム的っていうんだろか、音楽が絶妙だ。
映画を観てる間中、至福の時を味わっているような、そんな感じだったわ~。