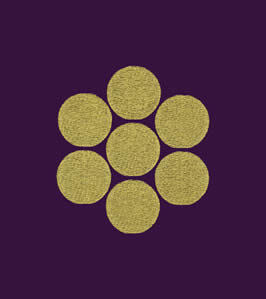☆大いなる旅路(1960年 日本 95分)
監督/関川秀雄 音楽/斎藤一郎
出演/三國連太郎 風見章子 高倉健 中村嘉葎雄 梅宮辰夫 東野英治郎 加藤嘉
☆昭和19年3月12日7時56分、C58283号、転落
この事故の概要をもう少し詳しくいうと、こんな感じになってる。
3月11日19時、宮古経由釜石行の貨物列車が盛岡を発車した。宮古機関区の機関車C58283が牽引する13輌の下り貨物列車だった。釜石製鉄所からの軍事物資の鉄を満載して盛岡まで到着していたのが、この夜、岩手県内の山田線を利用して、宮古へ空車回送するために出発したものだった。
乗員は、福島県出身の加藤岩蔵機関士(28歳)と前田悌二機関助士(19歳)だった。しかし、2メートルを超す積雪と強風の猛吹雪のため立ち往生し、途中の平津戸駅への到着は2時間以上も遅れ、午前0時が過ぎていた。さらに、先行する列車が川内駅で立ち往生していると連絡を受けたため、駅で列車を止めて、釜の火を調節しながら一夜を明かした。
翌朝、先行する列車が動いたという報せが入り、7時56分、加藤機関士は前田機関助士と宮古へ向けて出発した。橋梁やトンネルは雪がなく加速をつけられたが、そうでない鉄路では雪の壁を押しのけながら進まなければならなかった。
加藤機関士は、必死になって火を焚かせた。第三大峠トンネルを出、第一小滝トンネルをめざした。その間の鉄橋は、3つ。事故が起きたのは、2つ目の第二下平鉄橋である。
橋桁が雪崩に押し流され、線路が宙づりの状態になっていたため、8時7分、いきなり脱線し、30メートル下の閉伊川に転落した。連結器がちぎれて貨車7輛は線路に残ったが、あとは転落した。
機関車は転覆し、運転席の加藤機関士は右胸に重症を負った。前田助士は軽傷だったが、右手に裂傷を負い、骨が露出していた。加藤機関士は、前田助士に懐中時計を渡した。ガラスが割れて止まっていた。
「これが事故の起きた時間だ。後続列車の二重事故を防げ」
前田助士は平津戸駅へ戻ろうと出発したが、腰までの積雪のため断念し、加藤機関士のもとへ戻って怪我の手当を行った。
その頃、平津戸駅では、予定時間を大幅に過ぎているのに、貨物列車が川内駅に到着していないという知らせを受け、地元青年団が除雪する中、保線員が徒歩で川内駅へ向かった。
二時間後、保線員が脱線を発見、加藤機関士と前田助士は救助された。
しかし、医師看護班を乗せて宮古を発した列車が川内に着いたのは23時を回っていて、それまでに加藤機関士の容態は悪化、前田助士の手を握ったまま息をひきとった。
戦時だったためか、脱線事故は新聞記事にも取り上げられず、横転したC58283が引き揚げられたのは、戦後数年を経てからだった。
前田機関助士は、事故のあった年の9月に召集され、横須賀海兵団に入団していたが、戦後まもなく復員し、宮古機関区に復職した。引き揚げられたC58283は、郡山工場で修復復元され、山田線がディーゼル化される昭和45年まで、前田機関士により稼働した。
事故の前後はそんな感じなんだけど、昭和30年代の前半、盛岡鉄道管理局機関部労働組合盛岡支部で『殉職者頌徳帳』が刊行された。これに、山田線・平津戸ー川内間での脱線事故の詳細について、前田機関助士の手記が掲載された。
この手記を目にとめたのが脚本を担当した新藤兼人で、東映に持ち込んだとされてるんだけど、ちょっと腑に落ちない。というのも、原作者は加藤秀雄とされているからだ。この加藤秀雄という人はいったい誰なんだろう?殉職した加藤岩蔵の長男かなにかなんだろうか?わからない。
たぶん、東映の社員でも、当時の映画化のいきさつを知っている者はいないんじゃないかしら。まあ、それはいつかわかるときが来るとおもっておいとくけど、それにしても、仲沢半次郎、よく撮った!本物の機関車を脱線させて雪の谷底へ落とし、撮影したのは驚きだ。国鉄の全面協力とはいえ、職員立ち会いのもととはいえ、凄すぎる。
明朗健全東映現代劇を代表する作品のひとつだと、ぼくはおもってるんだよね。