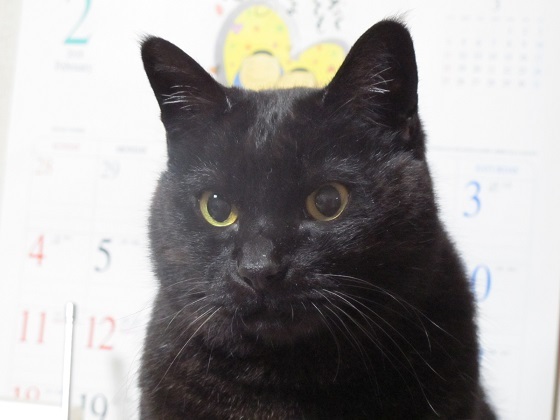応仁の乱の兵火によって焼失した清水寺を再興した
願阿上人(がんあしょうにん)の居住場所として造られたのが成就院の始まりだそう。
http://www.kiyomizudera.or.jp/info/index02.html
幕末には近衛忠熈公、西郷隆盛公をはじめとする勤皇の志士たちが集い、
密談を交わした場所でもあるそう。
清水寺には何度も行ってるけど、
そんなことも境内に成就院があることさえも知らなかったけど・・・・・
その成就院の襖絵を
http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/9046ca643a559f0a885f81cd9ac05161
クラブツーリズム貸切で、見て来た。
青蓮院門跡の襖絵を見た時も、
こんな現在的な襖絵があるんだと衝撃を受け、
それを受け入れたお寺もすごいと。
今回の中島潔さんの襖絵も肌を出した女性や鰯と
問題になったようだけどね。
成就院の襖絵は他にもあって、
http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/1610a54411349dc2a03911c428d353c1
毎年、模様替えして、期間を限って、特別公開しているいようだ。
庭は「月の庭」(実際の月は見えず、池に映った月を愛でるのだそう)
と呼ばれ、国指定の名勝で、座って見るのが作法だそう。
しかし、斬新な現在的な絵もいいけど、
静かに座って庭を愛でるにはミスマッチかなと。
元の襖絵はどんなんだろう・・・・・・・・・・見てみたいと思った。
こんな螺髪の仏像は初めて。
金戒光明寺の墓地に、



お遊び で作ったのかと思ったら、
で作ったのかと思ったら、
ちゃんと五劫思惟(ごこうしゆい)阿弥陀仏と言う名前があった。
この頭にもわけがあって、
阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、
衆生を救わんと五劫の間ひたすら思惟をこらし
四十八願をたて、修行をしている時の姿で、
五劫とは時の長さで、一劫は
「四十里立方(約160km)の大岩に天女が三年(百年という説もある)に一度
舞い降りて羽衣で撫で、その岩が無くなるまでの長い時間」のこと。
五劫はさらにその5倍ということになり、そのような長い時間、
思惟をこらし修行をした結果、
髪の毛が伸びて渦高く螺髪を積み重ねた頭となったと。
全国でも16体ほどしかみられないという珍しい姿だそう。
阿弥陀様も普段は床屋に行って
髪の毛手入れしてるのかな
金戒光明寺の若冲の画は
金戒光明寺のパンフレットより
「群鶏図押絵貼屏風」。
京都には中国画の名画を所蔵する寺が多く、
若冲は各寺へ足を運び千枚近くも模写したのだそう。
しかし、「絵から学ぶだけでは絵を越えることができない」という思いに至り、
また、生き物の内側に「神気」(神の気)が潜んでいると考えていた若冲は、
庭で数十羽の鶏を飼い始め、
朝から晩まで鶏の生態をひたすら観察し続け、
そして一年が経ち、ついに「神気」を捉え、おのずと絵筆が動き出したそう。
鶏の写生は2年以上も続き、
その結果、若冲は鶏だけでなく、草木や岩にまで「神気」が見え、
あらゆる生き物を自在に描けるようになったのだそう。
若冲の号は、『老子』にある
「大盈(だいえい)は冲(むな)しきが若(ごと)きも、其の用は窮(きわ)まらず」
“満ち足りているものは空虚なように見えても、その役目は尽きることがない”
から名付けられたのだそう。
金戒光明寺の屏風絵は水墨画だけど、
若冲は多彩な色を追求したり、いろいろな技法を駆使し、
「神の手を持つ男」と呼ばれていたそう。
http://www.bell.jp/pancho/k_diary-18/2016_04_30.htm
ところで、若冲より感動した画とは、

襖を開くと、虎の数が半頭に・・・・・・・面白い
4頭かたまりの右端の虎はどこから見ても
目線が合う、八方睨みの虎。
手前の虎は見る場所で体型が変わる。
メタボになったりスリムになったり・・・・・・・・・不思議。
仕掛け襖絵の虎図に、若冲さん、ちょっと影薄かった
今週1週間仕事がないので、
1泊2日で行ってきた。
お茶会と各寺院が所蔵している特別拝観の若冲の画が目的。
2日目の一番印象的だった金戒光明寺から。
金戒光明寺のパンフレットより
法然上人が比叡山の修行を終えて、
浄土宗最初の念仏道場を開いた場所で、
山門には「浄土真宗最初門」の額が掛かっていて、
‘日本の浄土宗の真のはじまりの場所’という意味があるのだそう。
山門の特別公開をしていて登ってきた。
知恩院三門には劣るけど、
楼上には、釈迦三尊像、十六羅漢像が安置され、
天井には「蟠龍図」が描かれている。
鳥よけのネットの隙間から御影堂を望む。
この地が自然の要塞になっていること、
遠く天王山や、淀川、大阪城まで見渡せたことから、
京都守護職として任命された会津藩主松平容保が
この寺を本陣にしたそう。
また、幕府が将軍上洛警備のため浪士組を結成し、
容保に浪士差配を命じたことから、
金戒光明寺は新選組発祥の地でもあるのだそう。
そんな関係から会津藩殉職者墓地もあるようだ。
詳しくは↓
http://www.kurodani.jp/roots/index.html
ところで、ここには次期将軍をめぐって対立した
春日局が建てたというお江のお墓(遺髪が納められている)もあった。
高野山高野山奥の院めぐりにもあったな・・・・・・。
お江のお墓へ行く階段を登りきったところにある
金戒光明寺のパンフレットより
三重塔は、お江の夫、秀忠を弔うために建てられたものだそう。
で、お目当ての若冲の画は次回に。
しかし、若冲の画より感動した画が。
温かい汁物が恋しくなる。
このところ、連日、夕食に汁物作ってる。
それも汁椀じゃなくて、スープ鉢でいただいている。
沢山飲める
土曜日に食べた精進料理の
レンコン団子汁が美味しかったので、
作ってみた。
レンコンすりおろして、おろししょうが・醤油少々・片栗粉適当入れて、
こねて団子にして、昆布と鰹節でだしとって、醤油で味を付け、
お吸い物風に。
シメジとわかめ、ネギをたっぷり入れて。
レンコンのすりおろし、初めて調理するけど、
意外に簡単!
レンコンのきんぴらや煮しめ酢の物より
よほど手間かからんでいいわ。
これから我が家の
手抜き料理のレパートリーになりそう