先週に引き続きフランスの虫の話です。
見出しのカマキリは、
バスの中から撮ったため何とか見える程度ですが・・・
ある村の入り口にあった巨大なカマキリのオブジェです。
さて、ここはどこでしょう?(・・・答えは末尾で)
話は変わって・・・
お世話になった牧場で飼われていたミツバチたちの家がこちら↓。

当たり前ですが、日本で言う「セイヨウミツバチ」です(笑)
すごい数のハチたちが働いていました。
高原の牧場は花盛りでしたので、大忙しだったのでしょう。
冬は雪が積もる厳しいところなので、
冬ごもりに備えて、たっぷりと蜜を蓄えるそうです。
それを人間に取られてしまうとは知らないで・・・(涙)
こちら↓は、新しく出来た一群の巣箱だそうで、
少し離れた場所にありました。

でも、どうなのでしょう?
ミツバチたちは、実は知っているのかも?!
こんなに立派な家を用意してもらえるのですからね~。
こちら↓は、山の上にある羊の放牧場で見つけた甲虫です。

素晴らしい色ですね!!
俗称フンコロガシ。タマオシコガネの仲間とのこと。
モミノキの森に多くいたのは、少し小ぶりでした↓。

スカラベは、動物のフンを球にして転がす習性で有名です。
地中に穴を掘り、フン球を入れて卵を産みつけ、
幼虫は球の内部を食べて育ち、そこでサナギになります・・・が、
これが、その種類かというと疑問です。
オオタマオシコガネは、もっと大きいし、
頭部や前肢の作りが違うようです。
むしろ、日本のオオセンチコガネのルリ色型に似ていますね。
紀伊半島にいるルリセンチコガネですか?
動物のフンの下や近くに穴を掘って、
フンを運び込み幼虫のエサにするところは一緒です。
それにしても、こんなに美しいのは、なぜでしょう?!
フランスといえば、この虫↓でしょう。

日本でも養殖をしているとも聞きましたが、
ほとんどは缶詰で輸入されるそうです。
大きなものは直径4センチ、高さ4センチくらいありました。
庭などを這っていました。(写真を撮りそこねました・・・とほほ)

↑エスカルゴの盛り付け例。ガラスの器の中はサラダでした。
エスカルゴの本来の意味は、「ブドウ畑のカタツムリ」だそうです。
古代から食用にされていて、
現代は養殖したものを食用カタツムリにしています。
オリーブ油と黒コショウで味付けされているのが一般的だそうですが、
野菜とバターで作ったソースをかけて焼いて、
レモンを搾って食べる地方もあるそうです。
大島でいうと磯で採れる、メッカリ、シッタカでしょうか?
食感は、よく似てますよね。
地中海に近い南フランスのアルルの宿で、
ロビーにあった飾り皿を撮らせてもらいました。

この辺りプロバンス地方は暖かいので、
セミをデザインしたものが色々ありました。
テーブルクロスやランチョンマット・・・
何にでもセミを描いてしまうというのもユニークです。
おみやげ屋には、こんなもの↓もありました。

何かと思ったら、
冷蔵庫などにメモをとめるマグネットでした。
冒頭のクイズの答えは、こちら↓。
フランスと虫といえば、もうお分かりですね?!
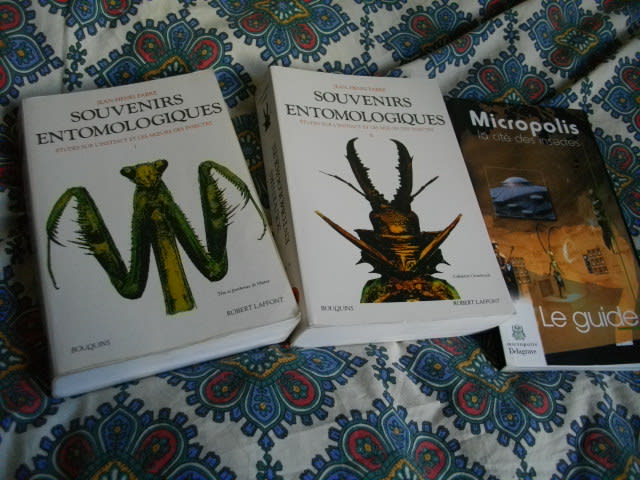
直訳すると「昆虫学的な回想録」とでもいうのでしょう。
日本でも新しい翻訳本が出版されていますが、
フランスでも再評価されているようです。
『昆虫記』を書いたファーブルが晩年を過ごした村を訪ねてみました。
カマキリのオブジェは、その「セリニャン村」の入口にありました。
(なるせ)
見出しのカマキリは、
バスの中から撮ったため何とか見える程度ですが・・・
ある村の入り口にあった巨大なカマキリのオブジェです。
さて、ここはどこでしょう?(・・・答えは末尾で)
話は変わって・・・
お世話になった牧場で飼われていたミツバチたちの家がこちら↓。

当たり前ですが、日本で言う「セイヨウミツバチ」です(笑)
すごい数のハチたちが働いていました。
高原の牧場は花盛りでしたので、大忙しだったのでしょう。
冬は雪が積もる厳しいところなので、
冬ごもりに備えて、たっぷりと蜜を蓄えるそうです。
それを人間に取られてしまうとは知らないで・・・(涙)
こちら↓は、新しく出来た一群の巣箱だそうで、
少し離れた場所にありました。

でも、どうなのでしょう?
ミツバチたちは、実は知っているのかも?!
こんなに立派な家を用意してもらえるのですからね~。
こちら↓は、山の上にある羊の放牧場で見つけた甲虫です。

素晴らしい色ですね!!
俗称フンコロガシ。タマオシコガネの仲間とのこと。
モミノキの森に多くいたのは、少し小ぶりでした↓。

スカラベは、動物のフンを球にして転がす習性で有名です。
地中に穴を掘り、フン球を入れて卵を産みつけ、
幼虫は球の内部を食べて育ち、そこでサナギになります・・・が、
これが、その種類かというと疑問です。
オオタマオシコガネは、もっと大きいし、
頭部や前肢の作りが違うようです。
むしろ、日本のオオセンチコガネのルリ色型に似ていますね。
紀伊半島にいるルリセンチコガネですか?
動物のフンの下や近くに穴を掘って、
フンを運び込み幼虫のエサにするところは一緒です。
それにしても、こんなに美しいのは、なぜでしょう?!
フランスといえば、この虫↓でしょう。

日本でも養殖をしているとも聞きましたが、
ほとんどは缶詰で輸入されるそうです。
大きなものは直径4センチ、高さ4センチくらいありました。
庭などを這っていました。(写真を撮りそこねました・・・とほほ)

↑エスカルゴの盛り付け例。ガラスの器の中はサラダでした。
エスカルゴの本来の意味は、「ブドウ畑のカタツムリ」だそうです。
古代から食用にされていて、
現代は養殖したものを食用カタツムリにしています。
オリーブ油と黒コショウで味付けされているのが一般的だそうですが、
野菜とバターで作ったソースをかけて焼いて、
レモンを搾って食べる地方もあるそうです。
大島でいうと磯で採れる、メッカリ、シッタカでしょうか?
食感は、よく似てますよね。
地中海に近い南フランスのアルルの宿で、
ロビーにあった飾り皿を撮らせてもらいました。

この辺りプロバンス地方は暖かいので、
セミをデザインしたものが色々ありました。
テーブルクロスやランチョンマット・・・
何にでもセミを描いてしまうというのもユニークです。
おみやげ屋には、こんなもの↓もありました。

何かと思ったら、
冷蔵庫などにメモをとめるマグネットでした。
冒頭のクイズの答えは、こちら↓。
フランスと虫といえば、もうお分かりですね?!
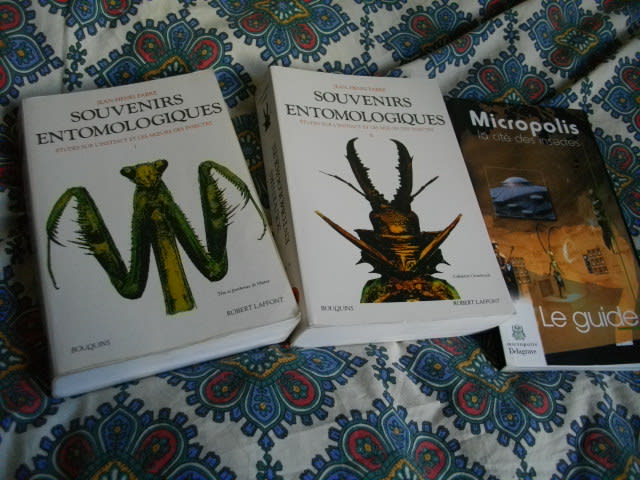
直訳すると「昆虫学的な回想録」とでもいうのでしょう。
日本でも新しい翻訳本が出版されていますが、
フランスでも再評価されているようです。
『昆虫記』を書いたファーブルが晩年を過ごした村を訪ねてみました。
カマキリのオブジェは、その「セリニャン村」の入口にありました。
(なるせ)

















