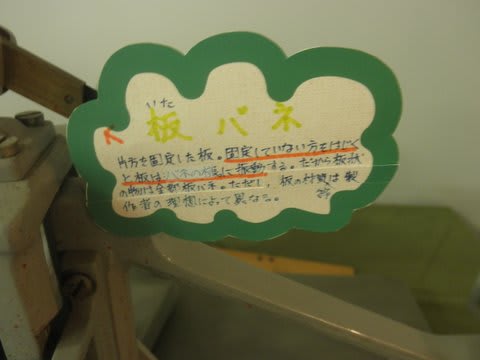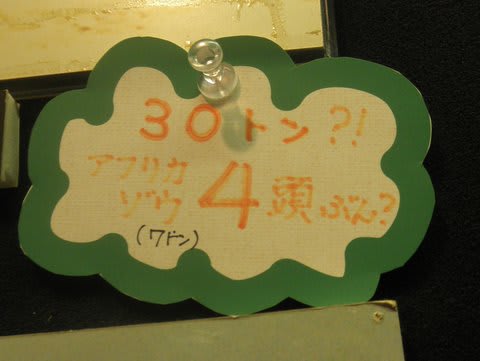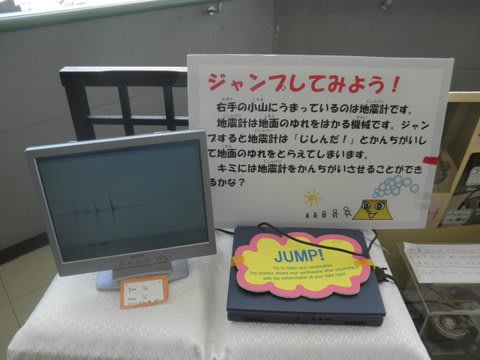今週の自然現象で驚きだったのは、やはり「竜巻」ですね!?
ゴールデンウイークの最終日に、スゴイことになってしまいました。
テレビのニュースでは、
「日本では、竜巻はあまり発生しない」とか、
「アメリカでは竜巻の発生が多いので研究が進んでいる」
などと解説されていました。
あれ、そうなの? と、ちょっと違和感がありました。
大島に住んで20年ほどですが、何度か竜巻らしきものを見聞きしています。
私の生活圏は、主に大島の南西部ですが、
陸地から海の方を見て、
隣の利島との間の海上を東へ向かう竜巻を2回見ました。
1回は1990年代前半で、2回目は90年代後半でした。
あと1回は、10年くらい前でしょうか?
元町の都立大島高校の杉林がなぎ倒されたり
民家の屋根が剥がされる被害があったと思います。
昨年の、初冬(でしたでしょうか?)に、
大島沖から三浦半島に向かう竜巻らしきものが映像に記録されて、
テレビのニュースで流れました。
大島周辺って、竜巻が多いのでしょうか?
たしか、『大島町史』に竜巻の写真があったのですが…。
どこだったろう? (汗)
「大島で寒候期に竜巻が発生することはあまり知られていない。
発生場所が海上であり、規模が小さく、竜巻災害が少ないためである。
1938年(昭和13年)から1997年(平成9年)までに
大島測候所で観測した竜巻は25個あり、そのうちの23個が
12月から2月に発生している。発生場所は全て海上であり、
大島と伊豆半島の間が多い。ただし、大島の東側は大島測候所から
目視観測ができないので、実際の発生数は25個を上回るだろう。
東海汽船の船員によれば、寒候期に1回くらいは竜巻を見るという。
大島の寒候期の竜巻は、ほとんどが収束線付近で発生している。
収束線を形成する西風と北東風が低気圧性に回転すること、
風の収束によって上昇気流が起きること、海面水温が気温よりも
高いことなどが竜巻の発生に都合が良いためである。しかし、
収束線が形成されるときは、上空約1000mから3000mに
安定な空気層があって、雲が発達しにくくなっている。
これは、竜巻が発生しても規模が大きくならないことに関係する。
竜巻による災害は、1975年(昭和50年)2月15日に発生している。
この時には、海上で発生した竜巻が上陸して、民家の屋根を飛ばし、
ブロック塀を倒し、窓ガラスを割った。」
『大島町史 自然編』168~169ページ 原基氏著1997年
「伊豆諸島北部の竜巻について」
(東京管区気象台、東管技術ニュース128より)
少し長いですが、『町史』の「気候」のところで解説されている
「竜巻」を転載しました。何となく様子が分かった気がします。
いかがですか?
この文章についている写真---
(大島測候所から伊豆半島方向の竜巻を
1994年12月19日安藤邦彦氏撮影)
---の竜巻が、
すごく長く伸びてクッキリ写っているので
これだけが記憶に残っていました。
解説の内容はすっかり忘れてました(笑)すみません。
60年間に測候所で25回の記録があり、
寒候期に1回見るという証言があるということで、
大島近海で年1回くらいは竜巻が発生しているという
ことのようです。
ビデオなどで竜巻の動画が撮られることが多くなって、
その実態がより詳しく分かるわけですが…、
今度、竜巻に出会ったら撮影できるかな?!
(なるせ)
ゴールデンウイークの最終日に、スゴイことになってしまいました。
テレビのニュースでは、
「日本では、竜巻はあまり発生しない」とか、
「アメリカでは竜巻の発生が多いので研究が進んでいる」
などと解説されていました。
あれ、そうなの? と、ちょっと違和感がありました。
大島に住んで20年ほどですが、何度か竜巻らしきものを見聞きしています。
私の生活圏は、主に大島の南西部ですが、
陸地から海の方を見て、
隣の利島との間の海上を東へ向かう竜巻を2回見ました。
1回は1990年代前半で、2回目は90年代後半でした。
あと1回は、10年くらい前でしょうか?
元町の都立大島高校の杉林がなぎ倒されたり
民家の屋根が剥がされる被害があったと思います。
昨年の、初冬(でしたでしょうか?)に、
大島沖から三浦半島に向かう竜巻らしきものが映像に記録されて、
テレビのニュースで流れました。
大島周辺って、竜巻が多いのでしょうか?
たしか、『大島町史』に竜巻の写真があったのですが…。
どこだったろう? (汗)
「大島で寒候期に竜巻が発生することはあまり知られていない。
発生場所が海上であり、規模が小さく、竜巻災害が少ないためである。
1938年(昭和13年)から1997年(平成9年)までに
大島測候所で観測した竜巻は25個あり、そのうちの23個が
12月から2月に発生している。発生場所は全て海上であり、
大島と伊豆半島の間が多い。ただし、大島の東側は大島測候所から
目視観測ができないので、実際の発生数は25個を上回るだろう。
東海汽船の船員によれば、寒候期に1回くらいは竜巻を見るという。
大島の寒候期の竜巻は、ほとんどが収束線付近で発生している。
収束線を形成する西風と北東風が低気圧性に回転すること、
風の収束によって上昇気流が起きること、海面水温が気温よりも
高いことなどが竜巻の発生に都合が良いためである。しかし、
収束線が形成されるときは、上空約1000mから3000mに
安定な空気層があって、雲が発達しにくくなっている。
これは、竜巻が発生しても規模が大きくならないことに関係する。
竜巻による災害は、1975年(昭和50年)2月15日に発生している。
この時には、海上で発生した竜巻が上陸して、民家の屋根を飛ばし、
ブロック塀を倒し、窓ガラスを割った。」
『大島町史 自然編』168~169ページ 原基氏著1997年
「伊豆諸島北部の竜巻について」
(東京管区気象台、東管技術ニュース128より)
少し長いですが、『町史』の「気候」のところで解説されている
「竜巻」を転載しました。何となく様子が分かった気がします。
いかがですか?
この文章についている写真---
(大島測候所から伊豆半島方向の竜巻を
1994年12月19日安藤邦彦氏撮影)
---の竜巻が、
すごく長く伸びてクッキリ写っているので
これだけが記憶に残っていました。
解説の内容はすっかり忘れてました(笑)すみません。
60年間に測候所で25回の記録があり、
寒候期に1回見るという証言があるということで、
大島近海で年1回くらいは竜巻が発生しているという
ことのようです。
ビデオなどで竜巻の動画が撮られることが多くなって、
その実態がより詳しく分かるわけですが…、
今度、竜巻に出会ったら撮影できるかな?!
(なるせ)