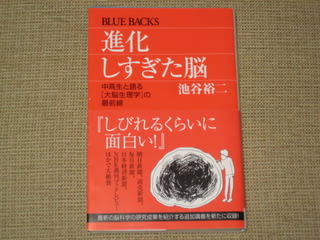池谷裕二 2007年 講談社ブルーバックス版
こないだ池谷裕二氏のことば(元ネタはアインシュタイン「学べば学ぶほど私は無知だと知る~」)を引いたんで、その著書。
副題は「中高生と語る[大脳生理学]の最前線」っていうように、慶応義塾ニューヨーク学院高等部での講義の記録を刊行したもの。
大教室での講義ぢゃなくて、生徒8名だけって少人数制なんで、全般に講師と生徒の対話形式になってます。
最新の実験結果とかも随所に紹介してるし、ときどき話題が小さな脱線を起こしたりして、記述が話し言葉でもあることもあわせて、学術書ぢゃなくて学習マンガ的なノリで読み進められます。(そのへんも売れた要因かな?)
タイトルの“進化しすぎた”の意味は、脳が最低限必要な程度の進化を遂げたんぢゃなくて、過剰に進化してしまったという考えによるもの。
人間は脳のもっているポテンシャルをほとんど使いこなしてないとは、よく言われることだけど、そのリミッターになっているのは身体。生まれ持った身体にあわせて脳は動いてるんで、たとえば腕がもう何本かあったら、それなりに脳は今より働いて力を発揮できるという。
これをもったいないと思うか、何か予期せぬ環境の激変とかがあったときにも対応できるための、将来への余裕ととらえるかは考え方次第。
ほかにも、刺激的な話題はいっぱいあって、「見る」というのは、三次元のものが二次元の網膜に映ったのを脳が三次元に再解釈する、だから人間はありのままぢゃなくて脳の解釈した世界から逃れられないとか。
言語は、コミュニケーションの手段ってだけぢゃなくて、抽象的な思考のためのツールでもある。では、なんの目的で抽象的な思考をするんだろうかとか。
正確無比な記憶は役に立たない、たとえば他人が最初見たときと服装を変えても表情を変えても、引き続き同一人物として認識できるのは、脳が「汎化」して情報を処理しているから。では、そのあいまいさは何に由来するかというと、神経の構造によるものであるとか。
ときどき、人間は自然淘汰の原理に反している、たとえばアルツハイマー病はなぜ自然淘汰で消えないかというと、子孫を残すという役を果たした後の病気だからであって、人間という動物は長生きしすぎてるから、いろんな病気が問題視されてる、なんてドキッとすることも出てくる。
脳のはたらきについて考えてくうちに、つきつめると「意識」とはなにかってことが議論をすすめていくうえで重要なことになるんだけど、この講義での一応の定義というか最低条件として挙げられているのは「1 表現の選択」「2 ワーキングメモリ(短期記憶)」「3 可塑性(過去の記憶)」。
でも、最終章の大学院生との対談で、著者は、できたら意識の話題は避けたい、客観性と再現性を重視する科学の対象として、主観的な存在である意識をとりあげるのはどうか、と正直に言っちゃってます。
ちなみに、最終章の最後の話題は、科学は(社会的に)役に立たなきゃいけないのか?です。大事なとこですが、さて結論は。
第一章 人間は脳の力を使いこなせていない
第二章 人間は脳の解釈から逃れられない
第三章 人間はあいまいな記憶しかもてない
第四章 人間は進化のプロセスを進化させる
第五章 僕たちはなぜ脳科学を研究するのか
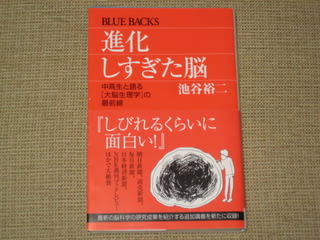
こないだ池谷裕二氏のことば(元ネタはアインシュタイン「学べば学ぶほど私は無知だと知る~」)を引いたんで、その著書。
副題は「中高生と語る[大脳生理学]の最前線」っていうように、慶応義塾ニューヨーク学院高等部での講義の記録を刊行したもの。
大教室での講義ぢゃなくて、生徒8名だけって少人数制なんで、全般に講師と生徒の対話形式になってます。
最新の実験結果とかも随所に紹介してるし、ときどき話題が小さな脱線を起こしたりして、記述が話し言葉でもあることもあわせて、学術書ぢゃなくて学習マンガ的なノリで読み進められます。(そのへんも売れた要因かな?)
タイトルの“進化しすぎた”の意味は、脳が最低限必要な程度の進化を遂げたんぢゃなくて、過剰に進化してしまったという考えによるもの。
人間は脳のもっているポテンシャルをほとんど使いこなしてないとは、よく言われることだけど、そのリミッターになっているのは身体。生まれ持った身体にあわせて脳は動いてるんで、たとえば腕がもう何本かあったら、それなりに脳は今より働いて力を発揮できるという。
これをもったいないと思うか、何か予期せぬ環境の激変とかがあったときにも対応できるための、将来への余裕ととらえるかは考え方次第。
ほかにも、刺激的な話題はいっぱいあって、「見る」というのは、三次元のものが二次元の網膜に映ったのを脳が三次元に再解釈する、だから人間はありのままぢゃなくて脳の解釈した世界から逃れられないとか。
言語は、コミュニケーションの手段ってだけぢゃなくて、抽象的な思考のためのツールでもある。では、なんの目的で抽象的な思考をするんだろうかとか。
正確無比な記憶は役に立たない、たとえば他人が最初見たときと服装を変えても表情を変えても、引き続き同一人物として認識できるのは、脳が「汎化」して情報を処理しているから。では、そのあいまいさは何に由来するかというと、神経の構造によるものであるとか。
ときどき、人間は自然淘汰の原理に反している、たとえばアルツハイマー病はなぜ自然淘汰で消えないかというと、子孫を残すという役を果たした後の病気だからであって、人間という動物は長生きしすぎてるから、いろんな病気が問題視されてる、なんてドキッとすることも出てくる。
脳のはたらきについて考えてくうちに、つきつめると「意識」とはなにかってことが議論をすすめていくうえで重要なことになるんだけど、この講義での一応の定義というか最低条件として挙げられているのは「1 表現の選択」「2 ワーキングメモリ(短期記憶)」「3 可塑性(過去の記憶)」。
でも、最終章の大学院生との対談で、著者は、できたら意識の話題は避けたい、客観性と再現性を重視する科学の対象として、主観的な存在である意識をとりあげるのはどうか、と正直に言っちゃってます。
ちなみに、最終章の最後の話題は、科学は(社会的に)役に立たなきゃいけないのか?です。大事なとこですが、さて結論は。
第一章 人間は脳の力を使いこなせていない
第二章 人間は脳の解釈から逃れられない
第三章 人間はあいまいな記憶しかもてない
第四章 人間は進化のプロセスを進化させる
第五章 僕たちはなぜ脳科学を研究するのか