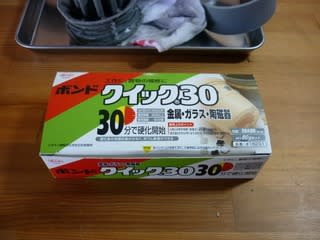Campagnolo カンパニョーロが発売していた 昔の乳白色のカンパグリス
これは製造中止でもう手に入れる事は出来ません どの様なグリスか
少し見てみましょう


このグリスは私が自転車を好きになりだした頃から有り
何時の発売か正確な事は不案内です 写真の物は全て
樹脂の容器ですが これの前は金属の缶に入っており
それで良く指先を切りました
このグリスが製造中止になりもう久しいですが 私の
在庫ももうこれだけになってしまいました


私もあまり気にした事は無かったのですが この容器も
製造年によりわずかに容量が違う様ですね 約 100gです
この容器はおそらく 35年程前の物だったと思いますが
当時のお値段が 580円 これの倍以上の量が有るイモグリスが
80円程でしたから 当時とすればやはり高価なグリスだったと
思います


手触りはそれ程粘度の高い物ではなく デュラなどと比べると
ややサラッと感が有ります 近年は色々な上質で高性能な
グリスが出ていますので このカンパグリスがそれ以上に
優れているとは言えないと思います
しかし私が使っていた 40年以上前にはこれの右に出るグリスは無く
選手時代このグリスを使いトラブルが一度も無かったのが その
優秀さの証明ではないでしょうか
ジモンディやエディ・メルクス セルキュにモレロンそれにイノー
なんかの一流選手の自転車にも使っていたのじゃないかな(笑)



Campagnolo LB100 カンパが近年発売したグリスがこれ
PTFE 配合のグリスで昔の乳白色の物とは明らかに異なります
手触りは粘度が高いと言うより やや硬いグリスでサラサラ感を
感じます 普段使いのデュラのグリスなどと同じ様にあまり難しい
事を考えずに使える商品だと思います


さてさて何をしてるんだ 我々の年代の自転車愛好家は
この乳白色のカンパグリスを競技者もツーリング派の人達も
使った事だと思います しかし今の若い人達は興味を覚えても
もう見る事も触る事も出来ないでしょう
先日研究熱心な知人がその様な事を 自身のブログに書いていました
この様な自転車の歴史の一つとも言える商品を後年に語り継いで頂きたく
小分けし送らせてもらいます 小分けの容器は指の滑り止め剤の中身を
捨てて使いましょう この大きさが丁度良かったんですよ(笑)


私自身の在庫が残り少ないので この容器一杯で
勘弁してもらいます10g 強入りました


カンパグリスのオリジナル容器とその中身
乳白色でやや甘い香りがする ピーナツバターを
思わせるグリスです
この時代はこのグリスを回転部にかなり多くの量を
使いました これは回転部に防水の為のシールが
ほとんどされていない事が影響していたと思います

LOC TITE ネジの緩み止剤のロックタイトです 用途により強度が色々と有り
私はホイールを組む時 ニップルの緩み止めに 222を使っています 過去に
これらの強度検証をしています ちょっと面白いですよ
その様子はここからどうぞ 過去日記 【 LOCTITE ある試み】


このカンパのグリスを望んでいた知人は ホイール組が
好きで色々な事にチャレンジしています ロックタイトも
この容器の物を買えばそこそこのお値段がします これも
少し小分けし一緒に送りましょう


しかし金魚に入れるのも難しいじゃないか 注射器型の
ポンプを使いましたが 何か思いっ切り怪しい写真に
なってしまいました(笑)
ロックタイトは嫌気性の性質で空気が遮断されると硬化
します 依って容器一杯に入れず容器内には空気を
残しておきます

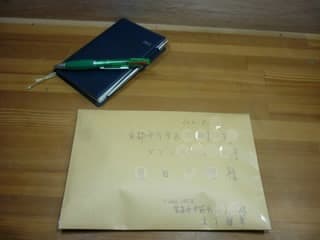
じゃこの怪しい金魚とカンパのグリスを送りましょう
グリスの容器を薄型にしたのは メール便で送りたかった
からで 輸送費を考慮しての事です
送り先の知人のブログ 【 ヌーボカステ工房 】
これは今回グリスを送る事になった記事ですが 他の
記事も中々講釈がきついブログです 又覗いてみて下さい

最近はケミカル品や油脂類に限らず 多くの自転車部品が科学的な理屈で良く述べられています
しかし今回のカンパグリスが使われていた当時には その様な難しい事は何一つ書かれていません
しかし多くの選手がこのグリスを選んだのは 理屈では無く良い物は良いと感じるからでしょう
人間の持つ経験則や感じる力 大切だと思います
雨上がり後の黄色いお花 穏やかで良いですね
これは製造中止でもう手に入れる事は出来ません どの様なグリスか
少し見てみましょう


このグリスは私が自転車を好きになりだした頃から有り
何時の発売か正確な事は不案内です 写真の物は全て
樹脂の容器ですが これの前は金属の缶に入っており
それで良く指先を切りました
このグリスが製造中止になりもう久しいですが 私の
在庫ももうこれだけになってしまいました


私もあまり気にした事は無かったのですが この容器も
製造年によりわずかに容量が違う様ですね 約 100gです
この容器はおそらく 35年程前の物だったと思いますが
当時のお値段が 580円 これの倍以上の量が有るイモグリスが
80円程でしたから 当時とすればやはり高価なグリスだったと
思います


手触りはそれ程粘度の高い物ではなく デュラなどと比べると
ややサラッと感が有ります 近年は色々な上質で高性能な
グリスが出ていますので このカンパグリスがそれ以上に
優れているとは言えないと思います
しかし私が使っていた 40年以上前にはこれの右に出るグリスは無く
選手時代このグリスを使いトラブルが一度も無かったのが その
優秀さの証明ではないでしょうか
ジモンディやエディ・メルクス セルキュにモレロンそれにイノー
なんかの一流選手の自転車にも使っていたのじゃないかな(笑)



Campagnolo LB100 カンパが近年発売したグリスがこれ
PTFE 配合のグリスで昔の乳白色の物とは明らかに異なります
手触りは粘度が高いと言うより やや硬いグリスでサラサラ感を
感じます 普段使いのデュラのグリスなどと同じ様にあまり難しい
事を考えずに使える商品だと思います


さてさて何をしてるんだ 我々の年代の自転車愛好家は
この乳白色のカンパグリスを競技者もツーリング派の人達も
使った事だと思います しかし今の若い人達は興味を覚えても
もう見る事も触る事も出来ないでしょう
先日研究熱心な知人がその様な事を 自身のブログに書いていました
この様な自転車の歴史の一つとも言える商品を後年に語り継いで頂きたく
小分けし送らせてもらいます 小分けの容器は指の滑り止め剤の中身を
捨てて使いましょう この大きさが丁度良かったんですよ(笑)


私自身の在庫が残り少ないので この容器一杯で
勘弁してもらいます10g 強入りました


カンパグリスのオリジナル容器とその中身
乳白色でやや甘い香りがする ピーナツバターを
思わせるグリスです
この時代はこのグリスを回転部にかなり多くの量を
使いました これは回転部に防水の為のシールが
ほとんどされていない事が影響していたと思います

LOC TITE ネジの緩み止剤のロックタイトです 用途により強度が色々と有り
私はホイールを組む時 ニップルの緩み止めに 222を使っています 過去に
これらの強度検証をしています ちょっと面白いですよ
その様子はここからどうぞ 過去日記 【 LOCTITE ある試み】


このカンパのグリスを望んでいた知人は ホイール組が
好きで色々な事にチャレンジしています ロックタイトも
この容器の物を買えばそこそこのお値段がします これも
少し小分けし一緒に送りましょう


しかし金魚に入れるのも難しいじゃないか 注射器型の
ポンプを使いましたが 何か思いっ切り怪しい写真に
なってしまいました(笑)
ロックタイトは嫌気性の性質で空気が遮断されると硬化
します 依って容器一杯に入れず容器内には空気を
残しておきます

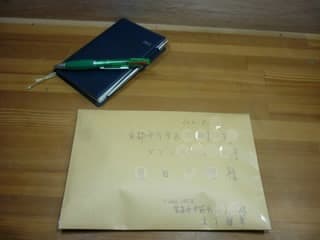
じゃこの怪しい金魚とカンパのグリスを送りましょう
グリスの容器を薄型にしたのは メール便で送りたかった
からで 輸送費を考慮しての事です
送り先の知人のブログ 【 ヌーボカステ工房 】
これは今回グリスを送る事になった記事ですが 他の
記事も中々講釈がきついブログです 又覗いてみて下さい

最近はケミカル品や油脂類に限らず 多くの自転車部品が科学的な理屈で良く述べられています
しかし今回のカンパグリスが使われていた当時には その様な難しい事は何一つ書かれていません
しかし多くの選手がこのグリスを選んだのは 理屈では無く良い物は良いと感じるからでしょう
人間の持つ経験則や感じる力 大切だと思います
雨上がり後の黄色いお花 穏やかで良いですね