
40代にダイビングにはまった時期がありました。
ちょうど長野県の松本にいた頃で、環境問題に関心を寄せる人たちと意見を交わしていた頃です。
環境に詳しい方から「陸上だけ見ていちゃダメだ。海の中を見て、そしてその接点である水辺を学ばないと環境のことは分からない」と妙な理屈を言われて、それが心に響いてその方に誘われるままにダイビングの免許を取りその世界に入ったのです。
ダイビングの免許は佐渡島で取得しました。直江津まで車で行ってそこからフェリーに乗って佐渡島まで渡り、ようやくとったCカードでした。
佐渡島ではファンダイビングと言って、地形や魚を見て楽しむダイビングを何度もしました。
佐渡島で潜っているとたまにとてもきれいな色をした熱帯魚のような魚に出会うことがありました。
あとで教えてもらったことは、「あれは対馬暖流に乗って南から流れてくる魚だよ。海が温かいからそのまま流れてきたけれど、このまま北へ流れて水が冷たくなると死んでしまう魚で、死滅回遊魚という」ということでした」
「死滅回遊魚」という呼び方が妙に印象的で今でも頭に残っています。
◆
かつて日本の技術屋のエースがこぞって炭鉱の世界に飛び込んだ時代がありました。
炭鉱を経営する企業は最も安定していて高い給与がもらえた時代で、当時の話を聞くと20代で何百人もの炭鉱労働者を束ねて、その地域の名士扱いだったといった話は枚挙にいとまがありません。
それが炭鉱が斜陽産業になった後には公共事業の時代がやってきました。
そこでは建設業が大きな産業となり、それを担う公共事業官庁とともに建設系産業に優秀な技術屋が飛び込んでいきました。
しかしそのときに、炭鉱技術者が公共事業を担う技術者として転換できた例はあまりなかったでしょう。
一つの世界に特化して能力を最大限に発揮した者ほど、他の分野へ転向するのが難しいのです。
ある方は、「時代が求めた役割が終わったら、それはただ消えるのみだな」と寂し気に言っていました。
そういう意味では、別にぬくぬくしていたわけではないでしょうけれど、冒頭の「死滅回遊魚」の話にどこか通じるものがありそうです。
◆
ネットの日経ビジネスの記事を読んでいたら、「AIが奪う仕事 vs 少子化で減る人手」という記事がありました。
著者は米国エール大学准教授の伊神 満さんという方です。
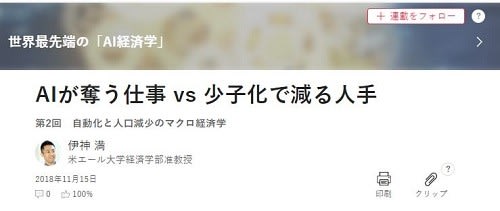
【AIが奪う仕事 vs 少子化で減る人手】 http://bit.ly/2D4JlFw
記事の内容は、AIが進んだら人間の仕事は奪われるだろうけれど、一方で少子化で人手は減りつつあり、それらはうまく相殺されるのだろうか、というもの。
研究の結果を言うと、アメリカでは仕事は増える方が多かったものの、それは国や時代によって違いそうだ、ということでした。
記事ではいろいろなエピソードが語られるものの、最後に私たちが本当に考えるべきこととして、4つの項目が提示されていました。
4つのポイントとは、
① 仕事と人手の出会いを、業界・社会全体でスムーズにする工夫。
② いまある人手でこなせるように、仕事のカタチを柔軟に変化させる工夫。
③「新たな仕事」に柔軟に対応できるような、新スキル習得の場所と機会。
④「人手不足の分野を狙って自動化を進める」ような、研究開発と企業活動。
…というものでした。
人口や若者が減ってどうしよう、と嘆いてばかりおらずに現実にこれからできることを明確にしてそれを確実に実践してゆこう、という強い気持ちが表れていて、意を強くしました。
さて、年寄りはどんな応援ができるのか。
しっかり考えて実践してゆきましょう。















