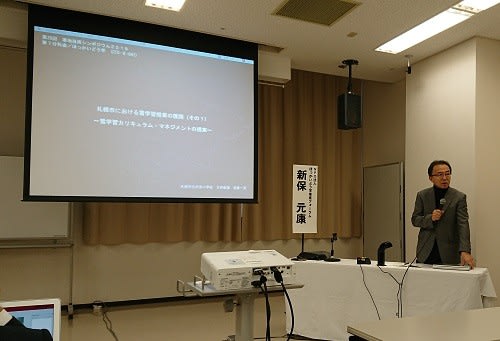
(一社)北海道技術センター主催の寒地技術シンポジウム。
昨日の27日から三日間の日程で開催されているこのシンポジウムは、今年が第35回目。
これまでも寒冷地技術の交流を目指して、これまでのジャンルでの様々な防災や河川技術、道路技術などの研究発表があったほかに、今年から新しく「ほっかいどう学」というジャンルが加わりました。
「ほっかいどう学」は、第8期北海道総合開発計画のなかにも「北海道の自然や歴史、文化、環境などの分野で、北海道の地域特性や個性に焦点を当て、…北海道に対する理解と愛着を一層深めるとともに、北海道の強みを生かして『世界の北海道』づくりに取り組む人材を発掘・育成する」などと書かれていて、北海道の隠れた魅力を発見する一つの取り組みと言えます。
とくにこれを提唱された新保元康さんが長年取り組まれてきた、小学校での社会科教育の分野で、北海道らしさとして雪について学ぶなどと言った先駆的な取り組みが多く行われています。
今日のシンポジウムの「ほっかいどう学」分科会では、札幌市における雪教育の取り組みや陶器防災授業の実践事例、交通環境学習、エネルギーの地産地消学習、さらに北海道での製氷業の揺籃期の歴史物語など興味深い発表がありました。
北海道における「雪」は、全国一律の学習指導要領では触れることが難しいテーマですが、ここに住む者としては避けられないものであり、これを利用したり楽しんだり、克服したりと様々な切り口で子どもたちに多角的に考えさせる取り組みは、まさに「ほっかいどう学」を体現する取り組みの一つでしょう。
これを本気で学ぼうとすれば、雪にまつわる多くの外の関係者と触れ合ったり話を聞いたりすることが必要で、教科書の中に閉じこもってはいられません。
それは地域のテーマを扱いながら「地域に開かれた教育課程」という学習指導要領の理念に沿ったものともいえ、これに取り組んでこられた先生たちのご努力に敬意を表します。
◆
分科会の最後には、座長である新保元康さんから「ほっかいどう学」推進に向けた考え方がお話されましたが、地域に眠っている物語を掘り起こして見えない魅力を発見することが北海道の魅力増進につながる、ということ。
それには退職された先生たちの力に期待するところも大きい、と。
一方私としては、こうした物語が観光と結びつくことで経済につながるような橋渡しの工夫も必要と感じた次第。
「ほっかいどう学」が地域をガイドするコンテンツ作りに繋がるという期待も膨らみます。
「学」と言いながら、もっと緩やかに面白がりながら膨らませるそんな取り組みでもよさそうです。
北海道の釣りだってそういう側面は大ですよね。よーし、週末はほっかいどう学を極めるためにも釣りに行くか!















