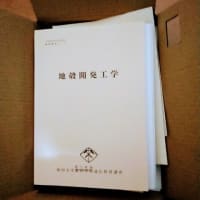池田信夫氏が「アゴラ」の「よみがえる社会主義」という記事で述べた「モラルハザード」と言うことについて小倉秀夫氏が彼のブログの「モラルハザード」という記事で批判していた。
池田氏はこう言っている。
<モラルハザードとは「行動のコストを負担しないで自己の利益を追求すること」です。たとえば派遣村に集まった浮浪者に役所が無差別に生活保護を与えることはマスコミに賞賛されるが、そのコストは税金だから広く分散されて見えない。このように個別の(事後的な)利益が見えやすく、全体の不利益が見えにくい構造は公共的意思決定にはありがちです。>
これに対して小倉氏は、モラルハザードとは、コストの話ではなくリスクの話として、次のように書いている。
<モラルハザードというのは,例えば,妻の実家から莫大な遺産を受け継いだために仮に失業しても経済的に困らない人が,そのような遺産等の支えがない人であれば自らが長期的に失業することになった場合のことを考えて現在の失業者に対して失業給付や生活保護等の名目で給付することに賛成するであろう公的資金についても,その給付に反対するような場合をいうというべきでしょう。>
モラルハザードとは、経済学の定義では、プリンシパル(依頼人)とエージェント(代理人)の関係において、情報の非対称性のために、エージェントがプリンシパルの利益に反する行動をとることを言う。たとえば、株主が取締役を監視できないので、取締役が株主の利益に反するような行為をすると言ったようなことだ。
この観点から、両者の意見を比べてみよう。まず池田氏の意見である。例えば、役所が納税者からの監視が十分でないことをいいことに、いい加減な審査をして、もらえるべき人がもらえなかったり、本来はもらうべきでない人までもらっているというのなら「モラルハザード」であろう。役所のモラルハザードとしては、年金問題が典型的な例であると思う。また、生活保護というセーフティネットがあるために、働けるのに働こうとしない者が出てくるのなら、これもモラルハザードといえよう。しかし、単に緊急避難的に無差別に生活保護を与えること自体は、納税者と役所の関係においても、役所と生活保護を受ける人との関係においてもただちにこれを、モラルハザードと呼ぶことは適当ではないと思う。一つ一つの行為は賞賛されても、トータルすると全体の不利益になるということを言いたいのなら、「合成の誤謬」といった方がふさわしいかもしれない。
次に、小倉氏の意見だが、これもその人が利己的であるとは言えるが、上の定義に照らしてみれば、遺産等の支えがない人とプリンシパルーエージェントの関係が特にあるわけではないので、「モラルハザード」とは呼べないだろう。
(応援クリックお願いします。) ⇒
「読書と時折の旅(風と雲の郷 本館)」はこちら
「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら
○関連ブログ記事
・404 Blog Not Found
池田氏はこう言っている。
<モラルハザードとは「行動のコストを負担しないで自己の利益を追求すること」です。たとえば派遣村に集まった浮浪者に役所が無差別に生活保護を与えることはマスコミに賞賛されるが、そのコストは税金だから広く分散されて見えない。このように個別の(事後的な)利益が見えやすく、全体の不利益が見えにくい構造は公共的意思決定にはありがちです。>
これに対して小倉氏は、モラルハザードとは、コストの話ではなくリスクの話として、次のように書いている。
<モラルハザードというのは,例えば,妻の実家から莫大な遺産を受け継いだために仮に失業しても経済的に困らない人が,そのような遺産等の支えがない人であれば自らが長期的に失業することになった場合のことを考えて現在の失業者に対して失業給付や生活保護等の名目で給付することに賛成するであろう公的資金についても,その給付に反対するような場合をいうというべきでしょう。>
モラルハザードとは、経済学の定義では、プリンシパル(依頼人)とエージェント(代理人)の関係において、情報の非対称性のために、エージェントがプリンシパルの利益に反する行動をとることを言う。たとえば、株主が取締役を監視できないので、取締役が株主の利益に反するような行為をすると言ったようなことだ。
この観点から、両者の意見を比べてみよう。まず池田氏の意見である。例えば、役所が納税者からの監視が十分でないことをいいことに、いい加減な審査をして、もらえるべき人がもらえなかったり、本来はもらうべきでない人までもらっているというのなら「モラルハザード」であろう。役所のモラルハザードとしては、年金問題が典型的な例であると思う。また、生活保護というセーフティネットがあるために、働けるのに働こうとしない者が出てくるのなら、これもモラルハザードといえよう。しかし、単に緊急避難的に無差別に生活保護を与えること自体は、納税者と役所の関係においても、役所と生活保護を受ける人との関係においてもただちにこれを、モラルハザードと呼ぶことは適当ではないと思う。一つ一つの行為は賞賛されても、トータルすると全体の不利益になるということを言いたいのなら、「合成の誤謬」といった方がふさわしいかもしれない。
次に、小倉氏の意見だが、これもその人が利己的であるとは言えるが、上の定義に照らしてみれば、遺産等の支えがない人とプリンシパルーエージェントの関係が特にあるわけではないので、「モラルハザード」とは呼べないだろう。
(応援クリックお願いします。) ⇒
「読書と時折の旅(風と雲の郷 本館)」はこちら

「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら
○関連ブログ記事
・404 Blog Not Found