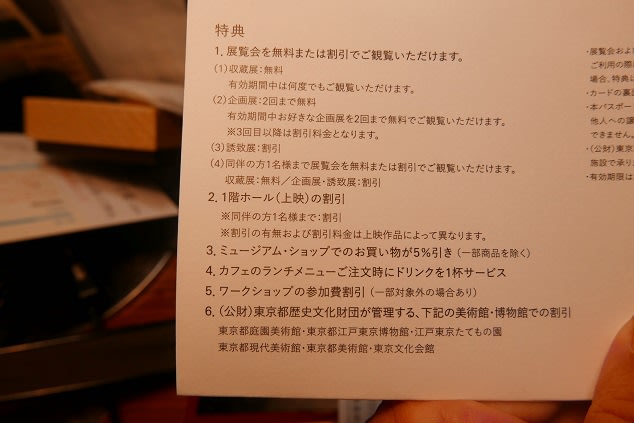8時半、起床。
今日は涼しいという感じでもなかったのでシャワーを浴びる。やっぱり朝のシャワーはいい。
トースト、サラダ(炒り卵)、牛乳、紅茶の朝食。

朝食にもデザート。昨日、チヒロさんからいただいた「わたなべ」の文士村饅頭。

昼食はインスタントラーメン+野菜炒め。

昼過ぎに家を出て、大学へ。
今日は大学院(修士課程)の入学試験の日。

入試関連の業務。
それを終えてから研究室で雑用。

夕方、帰宅の途中に神楽坂で途中下車して「SKIPA」に顔を出す。先日の句会のとき、財布を忘れてツケで飲食した分を忘れないうちに払わねばならない。
神楽坂の駅を降りたとき、改札口に卒業生のアスカさん(論系ゼミ3期生)が立っていた。私を待っていた・・・のではもちろなくて、彼氏と待ち合わせとのこと。これからお蕎麦屋さんに行くのだという。

満席だったら支払いだけして帰るつもりだったが、席が空いていたので、一服していくことにした。
ホットドッグとアイスチャイを注文。

小雨が降ってはいるが、土曜日の夕方の神楽坂は賑わっている。
改札口を入る時、さきほどのアスカさんとは別の卒業生が彼氏(たぶん)と一緒に改札口から出てきた。会釈だけ交わしてすれ違う。

蒲田に着いて、「鈴文」の前を通ると、いつもよりも長い行列が出来ている。閉店まで今日を入れてあと4日である。

夕食はポトフ。

今日、「あゆみブックス」で購入した、中牟田洋子『モレスキンのある素敵な毎日』(大和書房)。
いま、私はほぼ日手帳(カズンとウィークリー)を使っているが、その前はモレスキン(当時は「モールスキン」と言っていた)の手帳を使っていた。あれはあれでなかなか味わいのある手帳だった。

これは2004年に使っていたポケットサイズのモレスキン(罫線、ハードカバー)。
この年の9月に私は尿管結石の手術で一週間ほど入院生活を送ったのだが、そのときのメモから。
「手術前日の夕食。かやくご飯、しじみの味噌汁。手術翌日の昼食。親子煮、おかゆ、ほうれん草のおひたし。どちらも美味しかった。」
「手術台の上に寝て、見上げる看護婦が美人だと嬉しい。手を握ってくれたりするともっと嬉しい(脈をとっているだけなのだけれど)。」
「尿の色が前よりちょっと濃いとか薄いとかで気分が暗くなったり明るくなったりする。」
「病室のベッドで聴く雨音はわびしい。病室の窓から見る夕日は美しい。病室のベッドで聴く救急車のサイレンに孤独を慰められる。」
「風呂に入ると気分が明るくなる。風呂がこんなにいいものだとはふだんはわからない。温泉に入ったときのようにリフレッシュする。」
「同じ病室の人たち(自分のほかに4人)の中で気楽に会話ができるのは、Aさんだけだ。そのAさんが昨日一昨日と外泊だったので、居心地が悪かった。今日戻って来られてさっきデイルームでおしゃべりができてホッとした。同室の患者との人間関係は大切だ。」
「朝食のときAさんと話をしていて、彼がパン職人であることを知った。1960年に高校を出て、銀座木村屋に入社。以後、木村屋一筋で、現在は藤沢工場に勤務している。いろいろなパン作りについての話を聞くことができた。ベルト―の『パン職人のライフヒストリー』みたいだ。」
「同室の偏屈なジジイと思っていた患者が親身になってくれる看護婦に「ありがとう」と言っているのを聞くと、単純に人を見てはいけないと自戒する。」
「田村泰次郎『肉体の門』(1947)を読んだ。初版本で読んだ。すり減った紙面から当時のグツグツとしたエネルギーが立ち上がってくる気がした。」
「戦後の「第三の新人たち」の作品も読んでみよう。村上春樹が彼らに着目したのは「政治から経済へ」という戦後日本の社会の転換期に登場した作家たちだからだろう。」
「トイレの個室に忘れた財布が、しばらくして行ったらそのままだった。」
「医者はより重病の患者のことをよりケアする。しかし一人一人の患者は自分の病気という唯一無二のものと向きあって不安を感じているのだ。重い病か軽い病かは関係ない。」
「医者がこちらの質問に丁寧に答えてくれて、看護婦が親身になってくれて、同室の患者と打ち解けて話が出来て、毎度の食事がうまいということが入院生活ではとても大切。」
「退院が決まったら下痢が治った。」
日記帳ともスケジュール帳とも違うこういうメモ帳(思いついたことを書き記しておく手帳)を現在の私は使っていない。復活させようかしら。

2時、就寝。