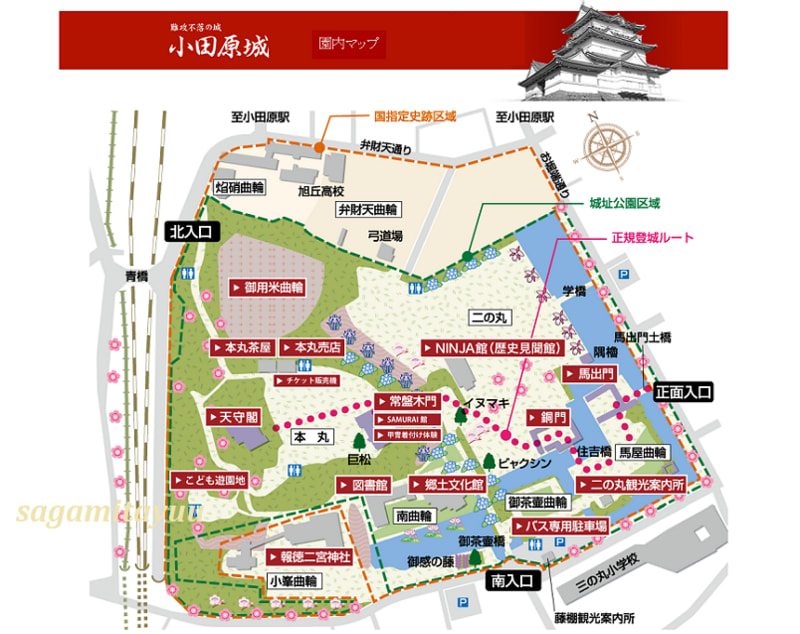相模原市南区新磯野に1600世帯というGPマンモス団地がある。ここの敷地内には雨水を貯蓄する広さは400㎡ほどの「雨水調整池」がある。通常雨水が引いた半分は広場グランドとして少年野球のグランドとして使用されている。半分は雨水池として冬場に時折「カモ」が数十羽やってきて雛を孵している。今日そばを通りかかると珍しく二種の「アオサギ」と「チュウサギ」いた。サギはペリカン目サギ科の鳥で世界に72種、国内に19種いる。他にゴイサギ、ササゴイ、アマサギ、ダイサギ、コサギ、シラサギがいる。しばらくすると一羽の「カモ」も飛んでやってきた。しばら動きを止め池の中で休息中かと思いきや池に頭と嘴を突っ込み捕餌し始めた。縄張り争いなのか時折灰色の「アオサギ」が「シラサギ」を追いかけまわし、威嚇し合っていた。撮影の機会到来、早速フォーカスしてみた。(2012)