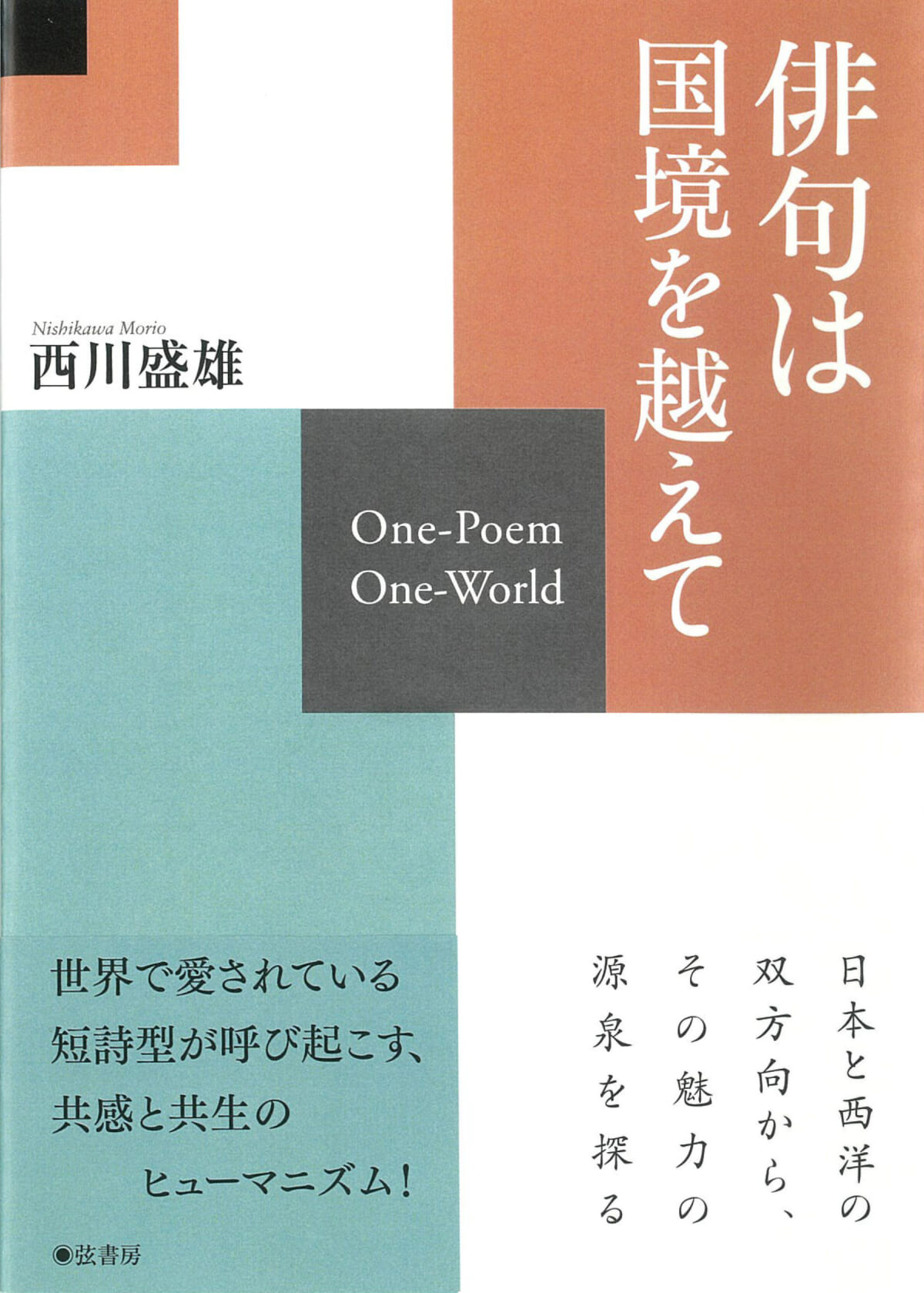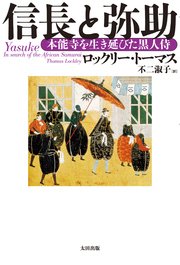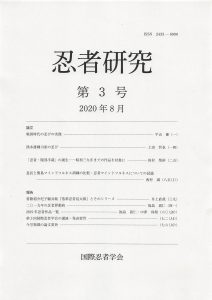八代の宝暦五年球磨川の大水害に伴う「萩原堤修復工事」の詳細を知りたいと思うが、詳しい史料に行き着かない。
稲津弥右衛門が7日間でこれを修復したというが、いつ頃始めたのかさえ判らない。
時の藩主・重賢は四月には参勤交代でこの時期は江戸在住であり、この大事は当然江戸に急使が送られたことであろう。
稲津弥右衛門に事を当たらせるのにも、江戸の重賢の決裁を得ているようだから、一月以上は時間が経過していると思われる。
そこで銀台遺事の該当項を読んでみようと思い至った。原本は「早稲田大学所蔵本」を使わせていただいた。
肥後文献叢書(一)に「銀臺遺事四巻」の釈文が掲載されているが、若干の食い違いが見て取れるが、これは使用された原本が違うことを意味する。ここでは早稲田大学原本に添い、特に脱落が認められるものは肥後文献叢書から( )書にて補筆した。

(四行目から)
宝暦五年當国の洪水こそ夥しかりき 六月朔日ゟ降出
せし雨篠を束て突くが如く九日まておやミたにセす川々
の水皆あふれけるに芦北瀬戸石山たちまちに崩れて
球广川をせき留けれハ川浪逆巻て山を包ミ陸に登る
といへる 古の程も今眼前に見へけるハ頓て其ときおし
流し一同に川下の方へ出けれハ八代萩原といふ所の堤忽
数十丁おし切りて田も畑も道もしれ万分らず神社仏閣を初
人家数多流れ溺死する者数百人目も當られぬ有様
そかし 此年は君東都にまし/\けれハ其よし注進す
君則 懸官へ言上したまふ其状に曰
私領分肥後の内六月朔日ゟ九日迄追々強雨洪
水山崩破損之覚
一高貮拾三万五百六拾石餘 潮入・砂利洗・剝山崩
此田貮万千七百五十三町餘
畑七千六百二十五町餘間
一塩濱九十七町五反
一塩塘三千四百十五

一川塘 十三万ニ百九十間
一井手塘堤 八万七千八百九十五間
一水除石垣 八百五十間
(一磧所 一万九千五十七間)
一磧除棚(水除棚)四千二百八十七間
一山崩(山岸崩所)一万七千百九十三間
一土橋 百五十五ヶ所
一往還道筋 一万九千七百四十六間
一井樋 百八十七ヶ所
一流舟 百一艘
一流失御番所 二ヶ所
一同 社 二ヶ所
一同 辻堂 八ヶ所
一八代蜜柑木之内 二百四十本餘
ママ
(一流家 二千百十八間)
一流木 三千ハ百二十二本
一流死(溺死男女) 五百六人
一怪我之者 五十六人
一溺死牛馬 五十八匹
右損耗破損之儀水引上り候上相改国許留守居之者ゟ
申越候 右損所郡村之内芦北球广川筋に有之瀬戸石
山 高サ二百間 横百間程崩落川向二有之御山に
(次回につづく)