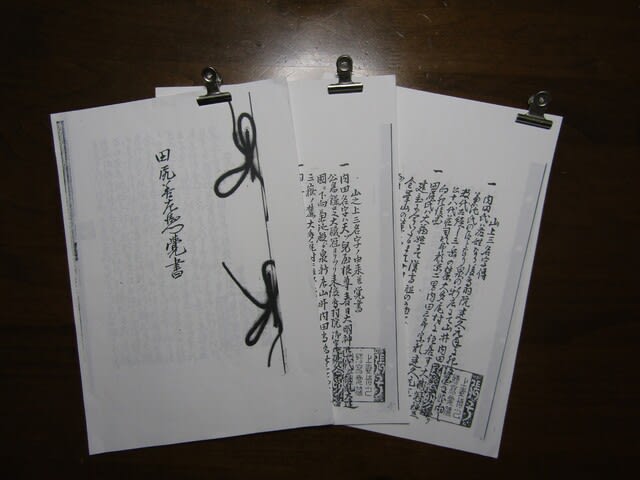吉祥寺病院・機関紙「じんだい」2022:10:31日発行 第69号
本能寺からお玉が池へ ~その⑬~ 医師・西岡 曉
むくどりや 野川 草の実 うち被り (及川貞)
あちこちで椋鳥の群れ飛ぶ声が響く季節になりました。この句の「野川」のことではありませんが、当院の少し西には野川公園があって、その西には多磨霊園があります。多磨霊園には当院初代医院長・塚本金助先生の墓所がありますし、[12]の与謝野晶子と[13]の岡本かの子とが眠る処です。
多摩公園の西にあるのが斎藤病院(@府中市浅間町)です。精神科病院として当院より後輩(当院の3年後=1957年開院)の斎藤病院ですが、今の医院長・斎藤章二先生は、斎藤茂吉のお孫さんです。実は斎藤病院は、章二先生のお母様の御実家の「宇田病院」(1939年開院)を発展的に継承したものですし、何より斎藤茂吉が委員長を務めた「青山脳病院」(1907年開院)が源流でもありますから、本院は当院の先輩病院と言った方が良いかもしれません。青山脳病院は、茂吉の次男・北杜夫(本名:斎藤宗吉。ご自身躁鬱病をカミングアウトされています。)が小説「楡家の人々」で「帝国脳病院」として描いています。
うつしみの 狂へるひとの哀れさを かへりみもせぬ世の人醒めよ もろびと覚めよ (斎藤茂吉)
先輩病院と言えば、当院と同じ市内の青木病院(@調布市上石原3丁目)を忘れてはいけません。青木病院は1962年の開院ですが、1945年開院の診療所「青木神経科」が発展した病院だからです。その青木精神科(と青木病院)の会員時の医院長・青木義作は、斎藤茂吉の義従弟(養母の弟の長男)にあたる人で、茂吉が院長だった時代の青山脳病院の副院長でした。青木病院の理事長・青木浩子先生は青木義作のお孫さんです。
[15] 愛宕山
前回までに、森鴎外の「鴈」の玉を含めて3人の「玉」という名の女性についてお話しました。「本能寺からお玉ヶ池へ」の流れから少し外れることになりますが、実はその後の「本能寺から本郷へ」の流れに関わる(そのお話は、来年稿を改めます。)玉という名の女性がもう一人います。お玉の局(=桂昌院;1627~1705)です。
お玉の局は、関白・二条光平の青侍だった本庄宗正の長女ですが、母が(玉を連れ子)に本庄宗正の後妻になったので本庄家の娘として12歳で江戸城大奥に上ったと言われています。後に将軍(徳川綱吉)の生母にまで上り詰めたことから「玉の輿」の語源になったと噂されました。「青侍」とは、公家(本庄宗正の場合は、関白・二条家)の家政部門に勤務する武士のことです。お玉の局の父の主君・二条光平は、大河ドラマ「麒麟がくる」に登場した二条晴良の系図上の曾孫ですが、光平の父・康道は(晴良の孫ではなく)九条幸家の長男です。康道の養父・昭美(あきざね)は秀吉に関白を譲った(ことで30年もの間関白の座を離れましたが、秀吉の死後17年で見事(?)再登板しました。)人です。光平の「光」の字は、春日局の息子・家光から戴いたものです(からその元は、明智光秀?)。町娘だった本庄玉を見初めて我が子家光の側室・お玉の局にしたのは春日局だとされます。こうして「玉の輿」に乗った本庄玉は、江戸城大奥御中臈・お玉の局になり、お玉の局は、5代将軍綱吉(1646~1709)の生母になりました。家光の母が春日局であれば、綱吉は(明智光秀の重臣で「本能寺の変」の主要メンバー=)斎藤利三の曾孫になります。
前回述べたように、春日局の墓所は、湯島の麟祥院にあります。そこから江戸城を越えて南へ6㎞余り、増上寺(@港区芝公園4丁目)にお玉の局の墓所があります。そして墓所とは別に、遥か遠く山城国西山の善峯寺(@京都市西京区大原野小塩町)と金蔵寺(@京都市西京區大原野石作町)に(遺髪を納めた)「桂昌院廟」があります。何故なら、お玉の局は幼少の砌この両寺によく参っていて、長じて大奥に上った後、荒廃していた両寺を再興したからだそうです。両寺には(お玉の局のお手植えと伝わる)「桂昌院桜」が、善峯寺にはお玉の局が寄進した「厄除けの鐘」が、今も残っています。余談ですが、私の苗字「西岡」は、この両寺のある今日の西山の東側、桂川、淀川との間の地域=西岡から戴いています。西岡には、ガラシャが輿入れした勝竜寺城や明智家を滅亡に導いた「山崎の戦い」の古戦場があるのです。
あたごやま いる日の如くあかあかと もやし尽くさん のこれる命 (西田幾多郎)
西田幾多郎は、(哲学の)京都学派(精神病理学の京都学派も西田の影響を強く受けています。)なので、この歌の「あたごやま」は、勿論京都の愛宕山です。愛宕山と言えば、「本能寺の変」の一週間前、明智光秀が愛宕山白雲寺(現存しません。@京都市右京区嵯峨愛宕町)の「勝軍地蔵」に詣でた処です。光秀は、翌日「愛宕百韻」を巻き、その発句に土岐明智家の苦境を詠みました。
時は今 あめが下なる 五月かな
明智家の未来を拓くべく起こした「本能寺の変」ですが、皮肉にもその結果明智家は滅亡の憂き目を見ることになってしまいました。愛宕山の勝軍地蔵への祈願が足りなかったのでしょうか?
明智家の滅亡から10年余り、光秀の孫・細川忠利は、少年期の4難関を愛宕山福寿院で過ごし、学問を修めています。愛宕山白雲寺は、明治維新後の「廃仏毀釈」に遭って破壊され、本尊の勝軍地蔵は金蔵寺に移されて金蔵寺「愛宕権現堂」に収められました。金蔵寺は、先ほど述べたように、「本能寺の変」の主要メンバー・斎藤利三の曽孫(と考えられる)徳川綱吉の母・お玉の局(=桂昌院)所縁の古刹です。
話は変わって、汽笛一声 新橋を はや我が汽車は 離れたり・・・ と始まるのが「鉄道唱歌」ですが、大昔(1900!)の歌なので、今ではご存知の方も少なくなりました。何せ、新橋を「汽車」が走っていたこと自体、百年近い大昔のことなのです。この歌は、続けて 愛宕の山に 入りのこる 月を旅路の友として と、東京の愛宕山を詠っています。(ご存知の方もおられるでしょうが、江戸=)東京にも勝軍地蔵を祀つた愛宕山があるのです。ただ「本能寺の変」の頃には江戸には愛宕山は(ありましたが、愛宕山という名では)まだありませんでした。
東京の愛宕山の勝軍地蔵も京の愛宕山のものと同じく(?)、少々「本能寺の変」と関りがあります。「本能寺の変」の翌日、堺にいた徳川家康は「伊賀越え」で三河に戻るべくまずは宇治田原(現・京都府宇治田原町)から甲賀の小川(現・志賀健甲賀市信楽町)の多羅尾光俊の館に入りました。光俊から多羅尾氏伝来の(源頼朝所縁と伝わる)勝軍地蔵像が贈られ、光俊を始めとする甲賀者が(明智光秀所縁の喜多村氏を含む伊賀者と協同して)伊賀越え道中の警護を担うにあたって地蔵像を同道させ、家康たちは無事三河・岡崎に帰還出来たと言われます。その後の家康の勝軍地蔵への帰依は弥増すばかり、戦陣に必ず護持して必勝を祈り、祈ったことで本当に勝ち戦が続いたそうです。
後年、征夷大将軍となった家康は、「本願寺の家」の21年後、京の愛宕山の勝軍地蔵を勧請した愛宕神社を江戸にも建立し、その別当寺・円福寺に伊賀越えに同道した地蔵像を祀りました。江戸の愛宕神社が建てられた桜田山は、その後「愛宕山」と呼ばれます。円福寺が(京の愛宕山白雲寺と同じく)廃仏毀釈で廃寺になると、勝軍地蔵は真福寺(‘港区愛宕山1丁目。江戸城に一番近い寺だったため、お玉が池種痘所開所の年・1885年には外国使節のしゅくしゃになりました。)に移転されましたが、関東大地震で焼失してしまいました。今寺庭に建っている地蔵像は、1934年(昭和9年)に再建されたものです。
 東都芝愛宕山遠望品川海図(昇亭北寿)
東都芝愛宕山遠望品川海図(昇亭北寿)
江戸の愛宕山は、(愛宕山になってからは)信仰の場であると同時にその見晴らしのよさから江戸で有数の名所になりました。今浅草の方が有名な「ほおずき市」や「羽子板市」も、始まりはこちらの愛宕山神社です。
ほおずき
鬼灯市 雨あをあをと 通りけり (永方裕子)
1874年(明治7年)に東京府(当時)は、愛宕山の東の麓に東京府病院を開院しました。初代院長は岩佐純、副院長は佐々木東洋、2代目院長は坪井信良です。懸命なる読者諸氏はお気付きかもしれませんが、佐々木東洋はお玉ヶ池種痘所発起人三宅艮斎の妹婿で、同じく発起人の坪井信良は坪井信道の娘婿ですから、「本能寺からお玉ヶ池へ」の流れの一端が、ここ愛宕下にまで流れ流れてきたようです。東京府民から(地名をとって)「愛宕下病院」とも呼ばれた東京府病院は、開院6年後には慈善病院となりましたが、残念ながらその半年後に兵員されてしまいました(が、今その跡地には東京慈恵会医科大学付属病院が建っています)。
「お玉ヶ池種痘所」に始まった近代日本の医学校は、明治の終わりには(お玉が池種痘所から発展した)東京帝国大学(現・東京大学)医学部を始め12校、大正の終わりには19校に増えましたが、西日本に(国公立の学校ばかりで)私立の医学校は有りませんでした。1927年(昭和2年)、大坂に開校した「大坂高等医学専門学校(現・大阪医科薬科大学)」が西日本で初の私立医学校です。大坂高等医学専門学校の初代校長・足立文太郎(1865~1945)は、入学時の学長が三宅秀(卒業時には退官)だった東京帝国大学医科大学卒業の解剖学者です。
夏目漱石が「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」を発表したのは、俳句雑誌「ホトトギス」でした。「ホトトギス」の同人で岡崎生まれの中村若沙(本名・中村一郎;1894~1978)は、大坂高等医学専門学校出身の外科医です。若沙の句の「地蔵盆」は、旧暦7月24日(現在の近畿地方では月後れの8月24日に行われます。)の地蔵菩薩の縁日のことです。
子が打てば 子の鉦の音 地蔵盆 (中村若沙)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回を持ちまして既刊分のご紹介は終了いたしました。次号が発行されましたら再度掲載させていただきます。
津々堂




























 本能寺焼討之図(楊斎延一)
本能寺焼討之図(楊斎延一)