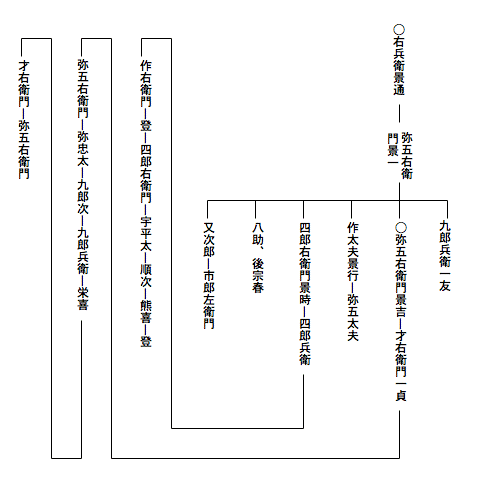いつも貴重な史料をご提供いただいている埼玉のTK様(現在お仕事の関係で和歌山在住)から、大坂城落城の様子について時系列にまとめられた資料をお送りいただいた。
御許しを得てここにご紹介する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■5月7日大坂落城の様子について(未定稿)
概ね信頼できる史料を時系列でならべ、5月7日大坂落城の様子を報告申し上げます。
位置関係等まだまだ認識不足の点がある未定稿なので、今後の修正をお許しください。
≪凡例≫:『 』…史料引用 [ ]…原注 ( )…史料名 〔 〕…私注
【合戰の開始】
『茶臼山邊巳刻合戰始ル』(駿府記)
『朝之四ツ過ニ天王寺口ニ事々敷煙見申候』(毛利家臣厚母元知大坂陣働之次第)
『九つ時分に越前衆より槍合申候』(藤堂家臣山本甚吉覺書)
『今日七日午の下刻大坂へ少々御よせ被成候』(慶長二十年五月七日付細川忠興書状)
【城方の敗北】
『七日〔中略〕午刻大坂燒煙見付、未刻計落城之由風聞』(義演准后日記)
『七日八ツ時分より及薄暮候迄ニ事澄申候』(慶長二十年五月八日付毛利秀元書状)
『大坂昨七つ時分ニ落城仕候』(慶長廿年五月八日付井伊家臣岡本半介書状)
『郡主馬合戰之刻、秀頼樣御馬印をもち候て御城より十丁斗も出申候、もはや惣敗軍ニ成候付而御城江持て歸候由申候』(慶長二十年五月十五日附細川忠興書状別紙覺)
【算用曲輪・二の丸玉造口の攻防】
(1)『速水甲斐守を御本丸に被指置候間、甲斐守鑓をも帶刀父子引廻候樣被仰付、御先手へ罷越候、〔中略〕祖父帶刀〔原田〕、父太郎助〔原田〕兩人は人數を召連、東の假門に罷在、帶刀、敵間爲見分に算用場之丸迄乘出候處、大野修理南之方より乘立參り、敵競來り候由を申、帶刀も左樣に見及申義、辭を合、一先請取所東之假門へ罷歸、御門を堅め罷在候へば、無程加州肥前〔前田利常〕殿之御先手人數大勢堀際へ着來候、此處之塀は前方堀を埋め俄に懸置申候假塀に候へば、殊外手薄にて、敵容易に乘入可申樣に相見申候故、味方敗北仕、僅十二三人計り殘り候處、櫻之御門之方より敵亂入、味方之後へ廻り申候に付、右十二三人計りと見え申、味方猶又散失』(原田理左衞門書上)
(2)『夏御陣五月七日落城之刻ハ、田原兵衞、私〔吉田次左衞門〕相詰居申候處、甲斐守〔速水〕被申候は、何と哉覽亂候間、東之御門防申候へと被申候ニ付、東之御門江參、敵押入候を討拂、一人も入不申候』(吉田次左衞門覺)
(3)『敵稻荷の前ニ而取て返し揉合、二三度火花を散し支しが、爰をも終に切崩し、玉造口東の門へ逃込、既ニ付入にせんとせしける所に、城中より北村五助と云者、鐡炮の藥箱に火矢を射かけ一度にはね上り候付、此口之寄手夫より引返し退候、櫻門ニ而本多豐後も手ニ逢、左手へ付、二本松、算用場より亂入』(大坂御陣覺書)
(4)『加賀勢、玉造口ノ門ニテ暫ク相戰フ、城兵北村五助鐵炮ノ藥箱ニ火ヲ付テ投出ス、是ニヨツテシハラク猛火ノタメニサヽヘラルトイヘトモ、ツイニ算用場、二本松ヨリ亂入』(武家事紀)
※(1)では、大坂七組の番頭速水甲斐守守之が、配下の原田帯刀・太郎助父子に、二の丸と三の丸の境にある東の仮門の防御を命じています。原田父子は一旦仮門の外、算用曲輪まで乗り出しますが、大野修理大夫治長が敵襲を告げ来ったので、東の仮門の防御に戻りました。(2)でも、速水守之が、配下の田原清兵衛や吉田次左衛門に東の御門の防御を命じています。
(1)東の仮門、(2)の東の御門とは、(1)の仮門が算用曲輪に通じていることから、共に玉造口の門を指すと推測されます。藤堂家編纂の「元和先鋒録」に、和睦に伴い城の土居や門・矢倉も引き崩して堀が埋め立てられ、所々畦道のような状態になっていたが、再度の開戦にあたり、大坂方で人夫を出して畦道を寸断し、柵を結い、生玉口等の諸口に木戸を構えたとの記録があります。玉造口の矢倉門も堀の埋め立てのため引き崩されたものの、夏の陣の時は仮門(木戸)が設置されていたものと思われます。
また、(1)で、玉造口の仮門を防御していた原田父子に対して、背後の桜之御門の方角から敵が迫ったことが記されています。これは西側の三の丸生玉曲輪から生玉口(元和先鋒録からこれも仮門だった可能性があると思います。)を突破して二の丸に乱入した敵が、桜之御門を左手に見ながら桜馬場を直進して玉造口の裏側から襲来したことを示していると思われます。
なお、(3)(4)では、玉造口に迫る加賀前田勢に対して、速水守之の与力北村五助が爆薬をもって防戦した様が記録されています。また、このため寄手は、算用曲輪、二本松から乱入したとありますが、算用場は玉造口の外に張り出した曲輪であり、二本松はおそらく二の丸櫻馬場の東方かと思われることから、少し位置関係が分かりかねています。「武功雜記」に『大坂城堀を埋め申たる時算用郭の地をひくな、其儘おけと御意なされ候由、算用郭は土地たかくして城中を見下すに利ありし故ならんか』とあることから、城中は南から北に向けて緩やかな下り坂となっており、算用曲輪は侵入の足場として恰好だったのかもしれません。
【本丸桜門の閉鎖】
(4)『櫻門迄參候へ共、最早本丸へはいり申候儀不相成、櫻門之西方ニ而槇島庄太、仙石左衞門、松井藤助、大野彌十郎、不破平左衞門、坂井助右衞門、此ものとも一所に罷在候』(林甚右衞門差出書付)
『大手口ニテハ拙者眞先ニ門キハヘ乘付候ヘトモ門ヲサシ申付テ馬ヲヒカヘ候』(松平忠直家中本多丹下郎從小笠原忠兵衞覺書)
(5)『落城ニ及旁々火掛リ御門打、海老ヲヲロシ申ニ付御門より入事相不叶』(早川太兵衞大坂合戰覺書)
※ (4)大坂七組の番頭真野豊後守頼包の与力林甚右衛門の証言から、既に本丸大手口桜門は、防御のため、鍵がおろされ閉鎖されていたようです。(5)豊臣方御宿越前の組頭早川太兵衛も城中の門扉が閉まり鍵(海老鎖)がおろされていたと証言しています。
【秀頼の動向(桜門→表御殿→奥御殿)】
(6)『秀頼公ハ修理參りて眞田謀を申上候ヘハ、則打立給んとし給ふ處へ、先手崩懸りしかは、最早乘出し討死せんと被仰候を、速水甲斐守來りて、先手惣敗軍と成候上ハ御出馬候とも不可叶、御本丸を御堅め時至候ハヽ御自害尤と申上候ヘハ、櫻門より千疊敷へ御入候、誰有て狹間配せよと下知する者もなく諸人色を失ひ、只落支度の外他事なし』(大坂御陣覺書)
(7)『一、敵も未かゝらぬ内に跡崩致候、我等〔今木源右衞門一政〕ハ御使に參、又ハ手にあい申候、秀頼生害之事無心元存候て御城へ參候ヘハ、城中人すくなく成りて、秀頼ハ於くと於もての間に御入候、御そはに修理一人、小姓共少々相見申候、天王寺表之樣子見及候段、又味方敗軍之樣子申上候て、さて御生害ハ何方にて可被遊候哉と申候ヘハ、殿守を用意仕候へと被仰候、則修理も御供いたし於くへ參候、我等も致御供候、扨奧へ參、鐵炮の藥ハ何方ニ御座候と申候ヘハ、たけへ助十郎にとへと被仰候、助十郎ニ向候て、鐵炮藥二人に爲持、殿守へあかり御生害の所にたゝミをかさねて敷申候而、藥を其處ニおき申候、其所へ頓阿彌樽をもちて參、御意之由申候』(淺井一政自記)
(8)『五月七日ニハ御城ニ居申候、其節秀頼公御雪隱ニ御入被成、御傍ニハ御打物赤座三右衞門、御手水ハ坂井平八、御手中郡平次〔郡主馬首宗保次子〕持居候處、大野修理被參、御城ハ落申候通言上、いつもの御氣色ニ而御出、御手水被遊、夫より奥へ御入、御座敷ノ間ノふすまを〔脱あるか〕加樣之時ハ子共ハ不參物とて、修理引立被申候、夫より何レも近習、小々性銘々御殿ヲ罷出候、平次事御玄關ノ前ニ而速見甲斐守ニ行逢申候ヘハ、手ヲ取候て、主馬ニハ逢不申哉と被尋候へ共、見不申由平次申候』(自笑居士覺書)
(9)『秀頼公、奧ノ御所ニ入給ヘハ、母北方ハ立向ヒテ、是ハ何ト成行事侍ルヤトアキレ立セ給ヒケリ』(豐内記)
(10)『一、下へさかり秀頼之御前ニ參、殿守を用意仕候と申上、火繩に火を付持參仕、殿守へ致御供參候、一、修理あとより參、僞を申候てとめ申候、我等申候ハ、加樣の時のび候ヘハ恥を御かき候ものに候、合戰のもり返し候事ハ僞にて御座候、はや千帖敷にも火かゝり申候と申候へ共、甲州、修理達而申候て下の矢倉へ御供いたし候』(淺井一政自記)
※(6)で、本丸大手口桜門まで出陣していた秀頼でしたが、城方敗北により速水守之から本丸の防御した上での自害を促され、一旦表御殿である千畳敷御殿〔御対面所〕に移動します。
(7)で、茶臼山口に出ていた秀頼の近臣今木(こんぼく)源右衛門一政が本丸に戻り、絶望的な戦況を報告すると、秀頼は天守に火薬を搬入するよう命じて、表御殿から奥に移動しています。(8)でも、秀頼は雪隠に行った後、大野治長から落城に極まった旨報告を受けつつも、普段と変わらぬ様子で奥に移動したことを豊臣家臣郡平次郎が証言しています。 (7)・(8)でいう「奥」とは奥御殿のことで、つまり秀頼は表御殿を出て、奧御殿がある曲輪の大手門に相当する鉄(くろがね)御門をくぐり、天守の南側真下に配置された奥御殿に移動し、(9)のように淀殿と言葉を交わしたたものかと思われます。
なお、(8)にあるように秀頼はいつもの御気色でおり、(6)で諸人が色を失っていたのとは対照的です。
(9)では、天守に火薬を装填した今木一政が、天守から降りて奥御殿の秀頼のもとに伺候し、天守への移動と自害を進言しています。この頃には表御殿(千畳敷御殿)にも火がかかっていました。しかし、大野治長や速水守之は、秀頼の助命に一縷の望みを託し、奥御殿がある曲輪の石垣を二段下った東下ノ段帯曲輪にある土蔵矢倉に移動を進言しました。(11)には『殿守より下りさせ給ひ』とありますが、(10)の秀頼近臣今木一政の証言のとおり、秀頼は奧御殿から直接土蔵矢倉に移動したのではないかと思います。
【二の丸から本丸の炎上と千姫退去】
『石田杢居申屋形〔二之丸大野修理大夫治長屋形〕ノ屏ヲ打破、拙者内ヘ入、火ヲカケヤキ立申候、拙者〔小笠原忠兵衞〕ヨリ先ニ火ヲカケ申候者御座有間敷候、ヤキ立申候後本丸モヤケ出申候』(松平忠直家中本多丹下郎從小笠原忠兵衞覺書)
『落人共爰元參候ハ、二曲輪より火かゝり本城も何も不殘燒申由申候』(慶長二十年五月八日付板倉勝重書状)
『未刻大坂之城火之手上り候由書留置申候』(高祖父輝宗曾祖父政宗祖父忠宗記録拔書)
『火手アカリ申候ヲ凉殿屋根ヨリ見物申候、晝之八時ヨリ夜半時分マテ火焰見申候』(土御門泰重卿記)
『大坂備前嶋片原町え晝之八ツ時分ニ乘込候〔中略〕、其節天守ニ火懸り燒上り申候』(石川忠總大坂陣覺書)
『八ツ時ニ大坂城火焰炎上ト云々』(伊達治家記録)
『大坂七つ時分落城仕候』(慶長二十年五月八日付井伊家臣岡本半介書状)
『七日之申之刻ニ本丸殿守燒申候』(慶長二十年五月九日付山口直友書状)
『大坂之御城天守も申之下刻ニ火かゝり申候』(慶長二十年五月七日付細川忠興書状)
『七日七ツ過ニ大坂ノ城ニ火かゝり同八日之朝迄燒申候』(井伊家臣富半右衞門覺書)
『七日城炎上之時、秀頼御袋より女房二人[刑部卿局、饗庭局]、侍二人[堀内主水、南部左門]等を御附、御所樣之御陣ヘ御送り被成候』(元和年録)
『大坂御本丸火ノカヽル時、内ヨリ姫君出シ申事ハ、此上御一所ニ果シ申テモ無詮事、出シ奉ル、俄事ニテ其期ナレハ、イカニモシタルヤラン麁相ナル乘物ニ乘セ參ラセ、上下六拾人計ニテ鎗ノ柄切折、棒程ニシテ天王寺表イ御出被成、皆名乘テ御輿近邊人ヲ拂テ出ル』(山本日記)
【東下ノ段帯曲輪土蔵矢倉への避難】
『七日〔中略〕同申刻從城中、大野修理郎從米村權右衞門爲使參于茶臼山、以本多上野介、後藤少三郎、訴申云、諸牢人不殘討死、今日姫君城中令出給、於岡山御座、秀頼幷御母儀、其外女中數輩、大野修理母子、速水甲斐守、其外山里帶くるわ二間、五間之庫に取籠り給由、秀頼幷御母儀命於御助、有御赦免、幕下可令問之旨雖被仰、及黄昏、右之使者、被召預于後藤少三郎云々』(駿府記)
(11)『秀頼公、淀殿と御一所に殿守へ御上り御自害可有所に、速見甲斐申候ハ、合戰の習、先陣破ても後陣り有事あり、御自害ハ不遲とて殿守より下りさせ給ひ、月見の矢倉の下より芦田曲輪の東上矢倉へ御薈』(大坂御陣覺書)
(12)『一、御袋〔淀殿〕ハはやさきへ御下候、秀頼ハ月見の矢倉の下よりさま〔狹間〕を御のそき被成候ヘハ、市正殿へ參候坂のとちうへ敵つき候躰に相見申候、其處にて内藏助〔渡邊〕切腹いたし候、渡邊長左衞門介錯仕候かと存候、一、煙にむせ候て我等ハ内へはいり候ヘハ、正永〔渡邊内藏助母〕介錯してくれ候へと申候間、介錯致候、御ちやあ、又あい、又比丘尼三人かいしやくいたし候、是ハ手からに成候ニてハ無之候へ共、此時ニハ皆々うろたへ、ものを申者も無之候』(淺井一政自記)
『秀頼幷御母堂ハ帶曲輪ノ土藏ニ入給フ』(元寛日記)
(13)『一、秀頼矢倉へ御出候、皆きやう〔興〕のさめたる躰ニ候、夜ニ入、ひき事なと永々と申候ては慮外、御手本を可仕と申候て、脇指をぬき候處ニ、津川左近、毛利長門とりもき候てそとへ引立、つれて出申候』(淺井一政自記)
※(11)にある『月見の矢倉の下より』がよくわかりません。大坂城図では月見矢倉は本丸の北西隅、天守の西側に位置しています。奧御殿から月見矢倉を経由して東下ノ段帯曲輪に行くためには、奧御殿を出て西に進み、月見矢倉の付近から西中ノ段帯曲輪に一段降りて山里曲輪を東へ堀際まで進むルートになりましょうか。
しかし、(12)に『秀頼ハ月見の矢倉の下よりさまを御のそき被成、市正殿へ參候坂のとちうへ敵つき候躰に相見申候』とあり、月見矢倉の下の狭間から窺うと、二の丸東方にある片桐東市正且元邸へと続く下り坂の途中まで敵が攻寄せている様子が見えたとなると、ここでいう月見矢倉は本丸の北西隅の矢倉ではないこととなります。また、大坂七組の番頭野々村伊予守吉安手の宮井三郎左衛門が『大手之門ヲうち候ヘハ入申事不罷成、月見之矢藏わきのへいヲのりこへ城中へはいり申候』と証言しており、ここでいう大手之門とは黒鉄御門のことで、その近くに月見矢倉があり、その脇の塀から本丸に入ったということかと思われます。
表御殿にも火がかかった状況下で、奥御殿とを繋ぐ黒鉄御門を閉鎖するのはごく自然のことと思います。月見矢倉が鉄御門付近にあったとすれば、秀頼の避難コースも、奥御殿から出て、一旦東南の月見矢倉付近の塀から外部を窺い、閉鎖する前の黒鉄御門から空堀沿いに東に進み堀詰を北に進んで東下ノ段帯曲輪の土蔵矢倉へと移動するルートも考えられます。
(12)・(13)では、皆もはや物言う気力も失っていた様がうかがえます。(13)で、今木一政が「未練たらしい繰り言はいけない。いざ手本を示さん。」と言い放って脇差を抜いたところ、津川左近将監近治等に押し止められ、土蔵矢倉の外に追い出されたと証言しています。
【城内の鎭火】
『程なく天守より火の手上り申候、九つ過より七つ半過迄に透とやけ鎭り申候』(藤堂家臣山本甚吉覺書)
『酉刻頃城中火鎭り候』(元和先鋒録)
『七日之晩片桐市正ハ病中ニ而候得共、城之案内者に候ヘハ乘物にて城江入、燒殘候所々に火をかけさせ燒拂ひ罷在候』(慶長見聞書)
『大坂ノ城ニ火かゝり同八日之朝迄燒申候』(井伊家臣富半右衞門覺書)
※こうして長い5月7日が終わり、日の出とともに豊臣家最後の日となる5月8日が始まります。前日皆が既に物言う気力を無くしている中でも、大野治長と速水守之は未明から粘り強い助命交渉を繰り返しました。しかしながら豊臣家の命運は尽きており、『五月八日未刻御切腹』(慶長二十年五月十五日付細川忠興書状別紙巨細條書)『八日ノひるすきニ御腹被成候』(慶長二十年五月十四日付毛利秀元書状)という結末を迎えることとなります。