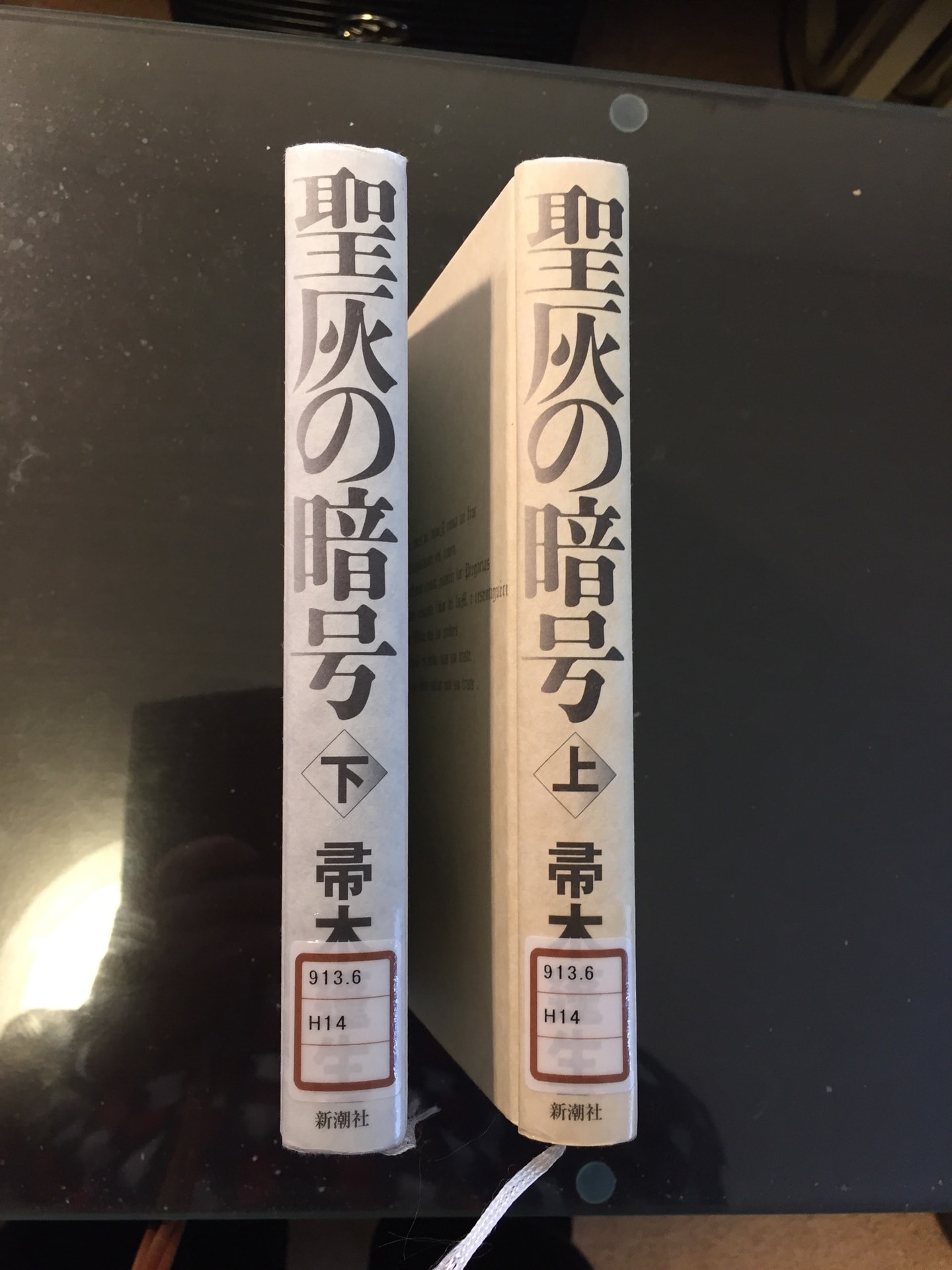こんにちわ。
「キリスト教の正しい学び方」本日も続けて参りましょう。
+++
前回、小さな小さな邦訳冊子『血まみれの道』が、原典不明の謎の本であったことを述べました。
後に筆者は、その探索を7年後、米国南部のバイブルベルト地帯で行うことになります。
だが、そこに一足飛びに行かないで、まずはそこに至るまでの経緯を述べておこうと思います。
でないと、筆者の探究自体がトンデモ本ならぬ「トンデモ行動」に見えてきてしまいますから。
+++
少し学問的な話になります。
煩わしいとお思いの方は、以下、ハウスマークで囲まれた部分は、飛ばしていいです。


















<マーケティングの新分野、CI>
筆者の生業は、流通経済学の研究と教育でした。
この経済学は経営視点からの流通活動をも研究対象に含んでおります。
そしてそれは、英語では、マーケティングとも言います。
筆者は、 マーケティングの研究屋でもありました(今も研究は続けていますが)。

<コーポレート・アイデンティティ>
さて、そのマーケティングに、1980年代頃、新しい研究課題が出現しました。
コーポレート・アイデンティティ(Corporate Identity)といいます。
頭文字をとってのCIという語をご存じの読者もおられるかもしれませんね。
+++
マーケティング学ではその研究は、企業のシンボルマークを対象としてはじまりました。
以後、CIの研究と論議は、そういう視覚的(ビジュアルな)用具をめぐって続けられていきました。
実践分野では中西元男や深見幸夫とかいった大家も現れ、活躍しました。
筆者もその研究を進めましたが、まもなく、言葉の上での疑問が浮かびました。

<アイデンティティって何?>
コーポレートは企業です。
それはいいのです。
だが、アイデンティティという語の意味がはっきりしなかった。
まあ、いまだからいいますけれど、マーケティング学者さんというのは、あまり深い思索をしない人種でした。
今も基本的には同じです。
彼らは、アイデンティティとは、シンボルマークのようなものだ、という認識で議論しておりました。
なんの疑いを持つことなくそうしていた。
+++
<旧約聖書に創造神の属性として>
だが筆者はそれでは気持ち悪くてしょうがなくなりました。
そこで、その語の由来を調べてみました。
すると、理念としてはとても旧いものであることがわかってきました。
+++
それは既に旧約聖書のなかに 出現していました。
旧約聖書のゴッド、すなわち、万物の創造神には「変わらざる方」という属性理念があります。
「毫も変わらなければ」それは永遠にそのままである続けますから、永続者でもあります。
そういう理念が旧約聖書に、そもそもとしてありました。

<ギリシャ哲学の「同一性」に>
この理念が、紀元前6世紀頃にはギリシャに流れ込んでおりました。
ユダヤ人は、世界に離散する歴史を繰り返しています。
中国の漢字にすら、彼らの思想の影響が入り込んだと推察される文字が見られます。
古代日本にも移住していたという説もある。
ギリシャはイスラエルのほとんど隣国ですから、もう「変わらざるもの」の理念も自然に流入していたでしょう。
+++
ギリシャ哲学者はこの理念を学問化しました。
論理学と数学をベースにした彼らの学問知識でもって、学問として取り組んだのです。
「変わらざるもの」を論理化したわけですね。
そしてそれを「同一なるもの」という言葉で表現しました。
任意の二つの時点を取って、全く同一ならば、それは「変わらざるもの」ということになりますからね。
ちなみに、その性質が「同一性」です。
英語では sameness です。
現代日本では、その言葉を取って、「同一性」といっています。
「性同一性」とかね。
+++
ギリシャ哲学者は、この言葉を使って、「はたして永遠不変なものは世界にあるか」と議論しました。
そこから沢山の副産物、存在論や認識論が生まれました。
それは後に、多くの学問的資産を人類世界にもたらします。

<神学の中で「アイデンティティ」に>
そのギリシャが次にローマ帝国に飲み込まれます。
ギリシャ哲学の知識も帝国での知的資産としてとりこまれます。
+++
紀元後、ローマ帝国ではキリスト教が大普及していました。
そのキリスト教活動の中に、神学(聖書の中の論理体系を探求する学問)ができました。
それが、ギリシャ哲学の論理的思考を取り込みました。
そして、旧約聖書の中にある創造神の属性「永続不変者」を神学的に考察しました。
その際、「変わらざるもの」に新たなラテン語名が与えられました。
identite がそれです。
紀元後2世紀の後半のことです。
こうしてわれわれ今日の流行語、アイデンティティの源が出来たのです。
+++
時は流れてルネッサンス時代となります。
このときギリシャの学問が再評価されました。
中世の期間中「哲学は神学のサーバント」といわれてきた知識が、分離独立して、浮上した。
アイデンティティ論も新展開しました。
ライプニッツの「モナド〈単子)論などはその代表ですが、この辺りは割愛します。

<エリクソンが一般用語にする>
ともあれそんなわけでアイデンティティという語は、神学的、哲学的概念でした。
こういう深い意味の用語は、なかなか一般日常語化はしないものです。
+++
ところが、現代になって、エリクソンという心理哲学者が、それを一気にポピュラーなものにします。
彼は・・・「変わらざるもの」という理念から、⇒ 「物事の深いところにあるもの」
⇒ 「物の中核にあってそれにまとまりを与えているもの」という風に連想展開をしたのではないでしょうか。
とにかく、アイデンティティを「人間の意識のまとまり (英語ではunity: 一体性といってもいい) に関連する理念」として用い始めました。

<属性意識を「アイデンティティ」で表現>
例をあげるとわかりやすいです。
たとえば、人間は自分について様々な所属(広くいえば属性)意識を持っています。
日本国民、東京都民、山田家の一員、**校の同窓生、等々です。
それが心のなかでまとまりを持っていると、その人の意識は一体性を得て、統一感覚を得ます。
すると人は快適な気分になるんですね。
+++
逆に、まとまらないと、意識は分裂症的になります。
すると人の気分は、不快で辛く苦しくなります。
+++
これらの属性イメージに、エリクソンは「アイデンティティ」の語を与えました。
民族アイデンティティ、コミュニティアイデンティティ、ファミリーアイデンティティ、スクールアイデンティティというがごとくです。

<属性イメージを統一する意識体は「自我アイデンティティ」>
さらにエリクソンは、これらを統一させ一体化させようとする意識体をも考えました。
そういう意識も、人の心の中核にある、と考えたのです。
そしてそれを「エゴ〈自我)アイデンティティ」としました。
+++
彼はこの理論でもって、戦後のベトナム戦争時代に発生した奇異な若者の心理を説明しました。
ヒッピーと呼ばれた彼らを、「アイデンティティが意識の中で統一されない」人間だと解説した。
そしてこの症状にアイデンティティ・シンドローム(アイデンティティ症候群)という名を与えました。
+++
それが結構「わかった気持ち」に人々をさせたのですね。
マスメディアも彼の概念を頻繁に用いて、社会問題を論じました。
エリクソンは一躍時代の寵児となりました。
それと同時に「アイデンティティ」という語も、流行し、一般用語になったわけです。
<ほとんど気分で>
コーポレート・アイデンティティの語は、その流れの中で誰かが言い出したのでしょう。
「その気分で」といってもいいかもしれませんね。
それが広がったものだとおもわれます。
+++
このとき漠然ながらも考えられたことを推察すると、たとえば、次のようにもなるでしょう。
つまり~
集団の成員が同じシンボルマークを共有したら、同じイメージを共有するのだから、一体性は高まるだろう。
だから、企業のシンボルマークはコーポレート・アイデンティティともいえるのだ。
~といったごとくです。
実際、エリクソンの考えは、個人だけでなく「人間集団にまとまりを与えているイメージ」にも応用出来そうなところをもっています。
その思考はかなり、直感的、連想的ですけどね。
ただし、この種の思考からは、用語の定義は~当然ながら~出てきません。


















~以上は学問的な話です。
こんなことは、興味のない人は、飛ばしていいです。
+++
直接大事なのはこれだけです~
どうして、コーポレート「アイデンティティ」などと言う言葉が使われるのか。
それはエリクソンという心理哲学者が、人間心理における「一体性形成要素」を示すに、アイデンティティの語を使ったからである。
米国でその意味を種としたアイデンティティが流行語になったからである。
ならば、その用語は人間「集団」にも応用できるだろう。
成員が共有し合って一体性を形成する要因とするのだ。
さすれば、シンボルマークも、アイデンティティ要素となるだろう。
のみならず、日本の富士山もそうだ。
これはマークではないが、同じ視覚的なシンボルだ。
日本人は、みんな、富士山というビジュアル物を共有している。
それでもって、日本国民としての一体性の意識を補強している。
企業も人間集団だ。
だから、従来コーポレート・マークといっていたものも、コーポレート・アイデンティティといおう。
~こうしてCIの語は出来たのです。

<理念も一体性要因になる>
筆者はそう理解し、それはそれでいいと考えました。
そしてもう一歩前進してみました。
~集団の一体成形生要素は、なにも、シンボルマークや他の視覚的なものに限らないではないか。
集団で共有する理念もそうであるはずだ。
たとえば成員が自己の集団に関する理念を持ち、自分をその一員としてのイメージしたらどうなるか。
彼らがその理念を共有するほどに、集団としてのまとまり(一体性)は増すだろう。

<内的ID,外的ID>
そして考えました。
ならばその理念にもアイデンティティの語を与えたらどうか。
それはシンボルマークなどのビジュアルな共有物とは違ったアイデンティティ要素になるだろう。
ではそれをビジュアル物と区分して、「インナー・アイデンティティ」と呼ぼう。
従来のシンボルマークは、外的な共有物だから「アウター・アイデンティティ」としよう。
~するとCIは、インナー(内的なもの)、アウター〈外的なもの)とで複眼的に見るべきものとなる。
また、インナーの考察を進めれば、CI論は、経営哲学の領域とも繋がっていくだろう。
筆者は、そう考えました。

<理念の構造>
ここで「理念」という言葉も明確にしておきましょう。
文字から行けば「念」とは「深い思い」です。
「理」とは、その思いに筋道を与えたものです。
筋道を与えると、それは概念になり、言葉になります。
+++
言葉で理念を集団で共有すれば、成員は同じ考えを共有することになる。
さすればそれだけ、考え方が似てくるでしょう。
それが集団の一体性を高めるでしょう。

<国家事例の方が理念内容は豊富>
筆者は企業のインナー・アイデンティティの事例収集を志しました。
個別事例が増えれば、共有理念に関する一般的理論もえられていくでしょう。
+++
そこで成員が共有し合って一体性を形成していそうな企業理念を具体的にを調べ始めました。
その結果、企業のもつ共有理念は、概して思想的にそんなに豊かなものでないことがわかってきました。
そのくせ、そんなものでも探索には結構エネルギーがかかることもわかりました。
企業にはいわゆる企業秘密が多く、それが支障になりがちなのです。
+++
筆者は、国家の理念についても概観してみました。
こちらは同じ人間集団でも、企業より遙かに豊かな思想内容をもっていました。
しかも、幸いなことに、こちらではその理念がほとんどオープンになっています。
筆者はそれを素材にして企業のID政策を考えたらいいのではないか、と考えました。
そして国家理念となると、ダントツに最適な経験素材がありました。
米国がそれです。
この人間集団では、個人の自由が世界でももっとも広範囲に認められています。
それでいて、成員の一体性意識はとても強いのです。
筆者は、米国を主要対象と定めました。

<米国国家理念の中核はキリスト教理念>
米国の国家理念となると、その代表はキリスト教の理念です。
大統領が就任式で、聖書に手を置いて宣誓するのもそれを示しています。
米国のキリスト教活動と理念を調べよう。
1990年代前半までには、筆者はその見解には到達していました。
若干の調査もし、新潮社で本も書かせていただきました。
+++
だが、具体的な手触りが、イマイチでした。
その後の米国での実地踏査でも確信ある答えには達せられませんでした。
(この踏査は前述した米国での仕事の機会~1996-7年~に行いました。これについては、また、後述します)
+++
一口にキリスト教理念といってもその対象範囲は広大です。
問題は、そのなかでいかなる思想要素が米国の国歌アイデンティティ(一体性)形成に効いているかです。
それがはっきりしない。
筆者の心風景は漠然としていました。
1997年頃まで、その状態が続きました。
+++
そうしたなかで、筆者の心に不思議な思いが生まれました。
このテーマの解明に、あの小冊子『血まみれの道』の原典は、不可欠な鍵を秘めているのではなかろうか。
それは国家アイデンティティ政策、ひいては、企業アイデンティティ政策にも深い知恵を与えてくれるかもしれない。
その思いは、成長し続けました。
(これは、訳者である「一匹狼牧師さん」を捕まえようとするよりも、米国の現場で原典を本格的に探求した方がいいな・・・)
筆者は、7年後に在外研究機会が得られそうな状況にありました。
そこでのCI研究計画の中に、謎の冊子の原典探索も含めよう。
そうすれば、その過程でまた、予想外の副産物も得られるかも知れない。
かくして探索は7年後に先送りされたのでした。
(Vol.28 マーケティング、CI、キリスト教の理念 完)