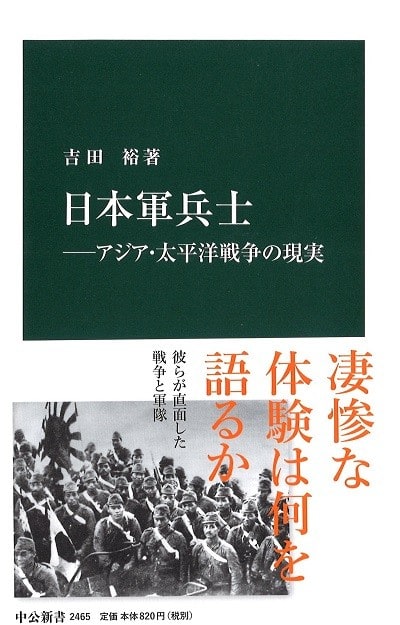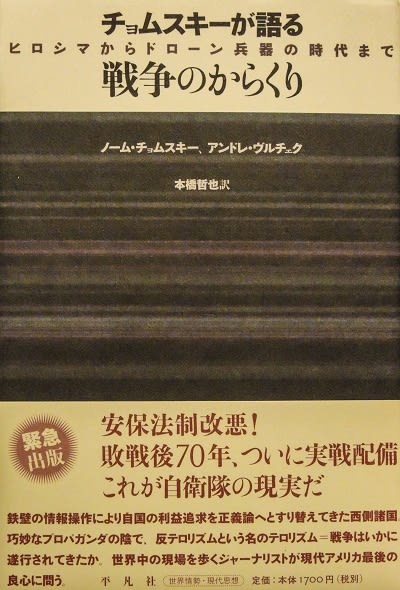植民地文化学会主催のフォーラム「内なる植民地(再び)」に足を運んだ(2015/7/11、江東区東大島文化センター)。会場は、1923年の関東大震災の直後に、多くの中国人や朝鮮人が殺された場所の近くである。水運のために中川と日本橋をつないだ小名木川には、多くの遺体が浮かんだという。
「内なる植民地」とは何か。植民地文化学会代表理事の西田勝さんより説明があった。国内にも心の中にも植民地主義は巣食っている。前回(2014年)のフォーラムでは、そのような背景があって「内なる植民地」を掲げたのだが、継続すべきテーマであり、「(再び)」を付したのだとのこと。また、座長の纐纈厚さん(山口大学)からは、「戦後、内なるファシズムを脱却できないでいるうちに、アベ的なものが現れた」との発言があった。

問題提起は4氏による。
※文責は当方にあります。
■ 【フクシマ】 エネルギー植民地としての福島 本田雅和(朝日新聞記者)
○「3・11」後、福島第一原発から25km離れた南相馬市に居を構えた。20km圏内はいまだ除染が進まないし、人の手も入らない。
○約1万6千人の死者の多くは一夜にして亡くなっている。しかし、原発事故のために避難せざるを得ず、「助かった命」であったが救出できなかった人も少なくない。
○今も22.9万人が避難生活を送り、その半数近い9.79万人以上が福島からの避難者である。いわば難民である。
○本来は短期間だけ使うはずの仮設住宅には、まだ多くの人が住んでいる。若い人は他へと移転し、そこに生活の根拠ができると、戻ることはない。その結果高齢化が進み、その人たちの希望は「戻りたい」「家族一緒に暮らしたい」ということ。福島の人は声を出さないと言われることがあるが、単純な問題ではない。うめきやため息は聞こえてくる。
○かつて、「村八分」になりながらも、何十年も原発の恐怖を詩に書いていた佐藤祐禎という農民詩人がいた(『青白き光』)。しかし、アカデミズムもジャーナリズムもそのような活動を取り上げることは少なく、いまだ、多くの人の共有財産とはなっていない。
○沖縄は米軍基地を押し付けられたが、福島は原発を誘致したという違いがあると言ったところ、金城実さんに「バカヤロウ」と一喝された。「オキナワでも、カネをぎょうさんもろうて基地に賛成しとる手先はいっぱいおる」と。
■ 【少数民族】 アイヌ民族否定論を駁する 岡和田晃(文芸評論家)
○「アイヌ民族はもういない」と発言した札幌市議(その後落選)など、アイヌ民族を否定するヘイトスピーチを吐く公人がいた。それに煽られた多数のネットユーザーが、攻撃的なデマを拡散した。その者たちに共通するのは、何ら知識を持つことなく発言することであった。
○マイノリティを「外部」として設定し、彼らに<憑依>することでその真意を代弁するつもりになったマスメディア(<マイノリティ憑依>)。それを過剰に内面化して仮想敵とみなし、社会の真の弱者を自認する者たちが、その原因を生み出した権力ではなく、マイノリティを攻撃するに至った可能性がある。すなわち、本質的に、相手がアイヌ民族であろうと在日コリアンであろうと誰でもよかった。
○向井豊昭という作家がいた(1933-2008年)。かれは征服者=和人の立場から、アイヌ民族を創作のモチーフにした。日本近代文学では稀な存在であった。かれは小熊秀雄という詩人に魅せられ、また批判もした。小熊の叙事詩「飛ぶ橇」(1935年)に出てくるイメージが、アイヌを征服した和人の言語感覚から由来するものだとして。その批判的視線が、自分自身にも向けられたものであることを、向井はよく知っていた。
○『アイヌ民族抵抗史』(1972年)を書いた新谷行も、征服される者からみた歴史を語る者であった。新谷はアイヌの血が自身に入っていることをカミングアウトするのだが、そのことは敢えて言わず、細かなひだをかきわけるように、屈折して同書を書いたのだった。


■ 【女性】 「満洲」女性作家呉瑛の場合 岸陽子(中国文学研究家)
○中国東北地方の女性作家たちは、女性、「満洲」という二重の圧迫を受ける存在であった。
○さらに戦後は、「売国奴の文学」として扱われた。しかし、銭理群(北京大学)という研究者は「設身処地」、すなわち、「そこに人間が存在するかぎり、人間の精神活動があるかぎり、文学は生まれる。必ず語る者が現れ、あれこれの声を発する」として、「満洲」文学の研究をはじめた。
○呉瑛という女性作家は、満洲族として吉林省に生まれた。日本に利用され、体制に沿った活動をしてはいたが、それでも官憲には危険人物として睨まれていた。いかに思想統制が厳しかったかということだ。戦後、売国奴扱いされることを避け、南京へと移った。
○呉瑛が書いた小説(『両極』など)では、旧いものが残されたまま日本の近代化が持ち込まれ、新旧が切り結ぶことなく分断した姿が描かれた。主体的に受容したのではない近代化は、個人の空洞化をももたらしたのだった。
■ 【在日】 ヘイトスピーチに抗して 梁英聖(一橋大学大学院)
○ヘイトスピーチは言葉にできないほど酷い差別であり、当然、レイシスト以外はこれを駄目だとする。
○話題になりはじめたのは2013年から、しかし、実態としてはその前からあった。また、発せられる言葉自体は百年前からあるものだ(「不逞鮮人」など)。
○何が過去と異なるか。それはレイシズムが暴力に達していることだ。
○ヘイトスピーチは暴力ゆえ視える。レイシズムは視えない。ヘイトスピーチはレイシズムの一部なのであって、前者だけを取り出して言論の自由などと論ずるのはおかしいことである(日本のみ)。実際に、日本における反レイシズムの規制や理解は、欧米より二周遅れている。
○まずは、レイシズムの可視化が必要である。低次元だが、そこからはじめなければならない。可視化されていないからこそレイシズムが視えないのである(セクハラが可視化されてはじめてセクハラをセクハラと認識できるようになったのと同様)。
○ただの差別意識が暴力にまで至るとき、上からの差別の煽動がなされることが多い。すなわち、キーワードは国家と政治空間である。関東大震災直後の虐殺も、軍隊や警察による上からの煽動があった。石原元都知事の「三国人」発言も、上からの煽動である。日本ではまだ、レイシズムが政治空間に入り込んでしまっている。
○レイシズムが暴力につながる回路はもうできている。もし何かあったときに、上からの煽動があったら、ヘイトクライムやジェノサイドは現実のものになりうる。
○したがって、批判されやすい「シングルイシュー」ではあるが、反レイシズムで一点突破することが必要である。それは他のシングルイシューを呼び寄せる結節点となるだろう。


■ コメント 李恢成(作家)
○現在、戦前レジームへの回帰がなされている。戦後の総括が極めて甘いものだったことも理由のひとつだ。
○アイヌ民族否定論は地域的な問題なのではないか。問題の根底には、これまで日本がアイヌを差別的に扱ってきたことがあるのではないか(たとえば、本庄陸男『石狩川』にもアイヌは出てこない)。
○小熊秀雄の『飛ぶ橇』は好きな作品だ。かれの作品には、アイヌも朝鮮人も登場する。そのような目を持った人だった。
○長見義三『アイヌの学校』では、和人(シャモ)とアイヌが共生しようとする。モラリッシュでヒューマンな作家の戦いである。また、鶴田知也『コシャマイン記』には、アイヌが感謝して作家の碑を建てた。こうした文学活動はもっと知られるべきだ。
○「やられた、やられた、やられた、やっつけた、やっつけた」ではないのだ。内と外とを、全体を見る視点が必要なのだ。
○人間は完全な存在ではない。戦争になれば、制御できないものが間違った形であらわれる。戦争はかならず性被害者を生み出す。慰安婦だけではなく、サハリンにおけるソ連兵によるレイプもそうだ。
○高見順は、『高見順日記』において、ビルマで慰安婦と寝たことを告白した。隠して尤もらしいことは書けないという、文学者としての精神性に賭けて書いたものであっただろう。韓国の民主化運動においても、運動にかかわる著名な者が、自分も仲間もそのような行為をしたのだと告白・告発した。その後、運動には関与しなくなった。アイデンティティを求め、沈黙に走ったのである。
○戦争が精神を破壊していく姿を追っていかないと、問題は、セクショナリズムの浅いところにとどまったままだろう。
■ コメント 岡田英樹(中国文学研究者)
○呉瑛の作品に、植民地であるがゆえの問題は見出されているのか。一般的な、封建社会から近代社会への移行という視点ではカバーできないのか。もっと分析が必要である。


■ コメント 岸陽子
○日本人の中には、満洲に結果として近代をもたらした、女子教育を改善した、いいことをしたのだという意見を持つ者が少なくない。
○それに反駁するために、この論点を取り上げた。自発的でない近代化は、個人の幸福は生まず、空洞を作り出してしまう。
○(中国東北地方出身の若い方がコメント)いまの若い人には、「結果としてよかった」などと言う者はいない。
■ コメント 本田雅和
○法規制でレイシズムは無くならない。レイシズムの底辺は、小市民(ファシズムを支える市民)による沈黙・容認である。関東大震災直後の虐殺を実行したのは、自警団という一般民衆だったのではないのか。ユダヤ民族を虐殺したクリスタルナハト(水晶の夜)もそうであった。
○シングルイシューでは不十分であり、しなやかな対応が必要なのではないか。
○上からの規制ではなく、下からのゲリラ的な運動こそが必要なのではないか。
■ コメント 岡和田晃
○インターネット時代にあって、アイヌ民族否定論は地域にとどまらない現象となっている。実際に、銀座でのデモがなされた。
○これに限らず、ヴァーチャルな仮想敵が設定されている。
■ コメント 梁英聖
○本田氏の指摘も正しいものである。しかし、シングルイシューに限界があるからこそ、シングルイシューが重要なのだ。
○自律性のない小市民に潜在的なレイシズムはあるのだろう。そのガスは抜かなければならない。しかし、ガスが充満している部屋で火を付けようとする輩を止めることがまずは必要なのではないか。
●参照
植民地文化学会・フォーラム『「在日」とは何か』(2013年)
新谷行『アイヌ民族抵抗史』
瀬川拓郎『アイヌ学入門』
田原洋『関東大震災と中国人』
加藤直樹『九月、東京の路上で』
藤田富士男・大和田茂『評伝 平澤計七』
李恢成『またふたたびの道/砧をうつ女』
李恢成『流域へ』
李恢成『沈黙と海―北であれ南であれわが祖国Ⅰ―』
李恢成『円の中の子供―北であれ南であれわが祖国Ⅱ―』