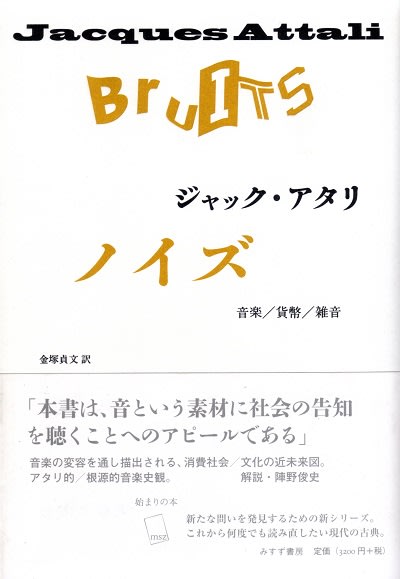先日、沖縄県宜野湾市の佐喜眞美術館で、鄭周河(チョン・ジュハ)という韓国人写真家による写真展『奪われた野にも春は来るか』を観た。展示されていたよりもさらに多くの写真群が、同じタイトルの写真集としてまとめられ、韓国で出版されている。テキストは日本語と英語に訳されている。
改めて、写真集を紐解き、じっくりと観た。写真展によって受けた印象が、また違った形で増幅されていくようだ。

ほとんどの写真には、人が登場しない。津波と福島第一原発の事故により、破壊され、汚染され、住民の方々がまずは避難した時期である。
このようなカタストロフという文脈でなかったとしたら、ひょっとすると、美しく懐かしい里山風景として観ているかもしれない。しかし、やはり、もの言わぬ風景が発する「ただごとでなさ」に、息を呑んでしまう。そして覚えるのは、観なければよかったという気分と、何ということになったのかという悲しさと、何ということをしてくれたのかという怒りと、このような社会を一緒につくりあげてしまったのだという絶望感と。
受け手の小賢しさなどすり抜けて、「なにものか」の力が迫ってくる。やはり、恐ろしい写真群だ。


タイトルの『奪われた野にも春は来るか』は、植民地朝鮮の詩人・李相和(イ・サンファ)の詩から引用されている。美しく懐かしい土地を表現し、体感したあと、詩人は、最後に1行付け加え、締めくくる。痛切と簡単に言ってのけるにはあまりにも痛切すぎる発語である。
「しかし、いまは野を奪われ春さえも奪われようとしているのだ」
この土地は、侵略者たる帝国・日本に奪われたものだったのである。
写真集に、徐京植によるテキストがある。福島と植民地朝鮮とを重ね合わせること。それは、「奪われた者たちの苦悩に、最大限の想像力を働かせなければならない」のだとする。そしてまた、この写真群の特徴たる「不在の表象」について、ナチスドイツに殺されたユダヤ人たちの衣服をもってインスタレーションを創るクリスチャン・ボルタンスキーの作品との共通点をも見出している。慧眼というべきである。
ボルタンスキー作品の映像(デジタルカメラによる) >> リンク


クリスチャン・ボルタンスキー『MONUMENTA 2010 / Personnes』(2010年、パリ)
今回の鄭周河の写真については、NHK「こころの時代」枠においても特集されていた(2013/5/12放送)(>> 映像)。そこでは、写真家自身による興味深い示唆があった。
「不在」を、森を撮ること。それは、日常の中に潜む「兆」や「予兆」を見出すための方法論であり、それにより、何が失われ、何が奪われたのか、何を視るべきなのかを考えるべきなのだ、という。
写真家は、かつて、精神病院を撮った写真集『惠生院』を発表した(1984年)。その過程において、相手を理解できず、なぜその人たちが自分ではないのかという内省があった。病院の取り壊しに反対して韓国の大学を中退、ドイツに留学して哲学を学ぼうとする。そこでの関係の中では、写真が持つ暴力性に取りつかれ、老人たちを、もっとも暴力的な手段であるフラッシュによって撮影し、『写真的暴力』(1993年)を公表した。そして、『大地の声』(1994-98年)、『西方の海』(1998-2003年)をまとめた後、韓国の原子力発電所近くの地域を対象とした『不安、火-中』(2008年)を撮る。
曰く、原発地域の人びとは、日常生活を営んでいる。しかし、勿論、不安は内側に潜んでいる。少し視線をそらし、目をしっかり開けて視ると、原発との共存という不安さが露出してくる。そのように、直視すべき現実をさらけ出す方法として、撮影行為をしたのだ、と。
確かに、この写真家は方法論の人であるようだ。むしろ、それを曖昧にして狙いや言葉を見えないようにする「芸術活動」のほうが、世間には多いのだと思う。しかし、写真家の意識は明確だ。
「カレンダーのように美しい」里山風景。それだけでは、何が言いたいのかわからない。自然の中に潜むものを、如何に伝えていくか。放っておけば目に視えないものを、如何に見せたり感じさせたりすることができるか。そこにおいて必要なものは、記憶と認識の共有、知識や経験の共有だという。
写真群のタイトルについても、意味や文脈が異なるものを重ね合わせ、それにより日本の侵略の過去を免罪する、のではない。そうではなく、「奪われる」という経験、ふるさとを奪われた人間としての心を共有化することこそが大事なのだ、と。
わたしはこの写真群を積極的に評価する。しかし、おそらく、この表現の方法論に関しては、賛否両論があることだろう。薄っぺらい芸術至上主義が、写真というアートの政治や歴史やテキストへの回収を否定するかもしれない。
それでは芸術とは何なのか。まったくの抽象が成り立つのか。たとえば、物語への回収を拒否したような写真作品は、その前提となる共有感覚や情報にもたれかかっているだけではないのか。
人間はことばによって生かされ、ことばによって知を形成する。勿論、ことばという制度による再生産だけだとすれば、それは芸術としての力をもたない。この写真群は、意味という場所への往還なのだと思うがどうか。
●参照
○鄭周河写真展『奪われた野にも春は来るか』
○徐京植のフクシマ(NHK「こころの時代」)
○辺見庸の3・11 『瓦礫の中から言葉を』(NHK「こころの時代」)
○クリスチャン・ボルタンスキー『MONUMENTA 2010 / Personnes』