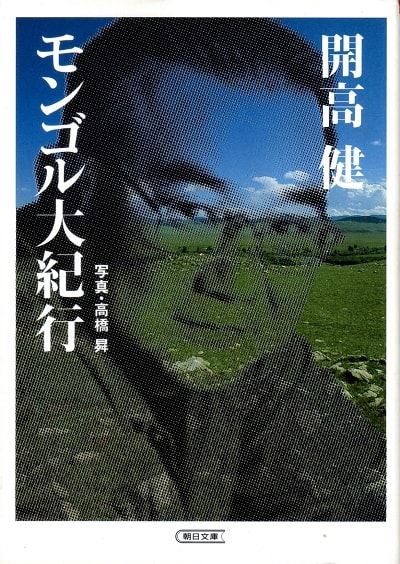趙景達『近代朝鮮と日本』(岩波新書、2012年)を読む。

朝鮮王朝(李氏朝鮮、1392年~)の末期から、日本による韓国併合(1910年)までを描く近代日朝関係史である。
言うまでもなく、韓国併合は日本による朝鮮侵略であり、当時ナショナリズムの高揚とともに形成された「日本が劣る国を保護してやる」といった言説は欺瞞そのものであった。侵略正当化のための言説が、明治以降血統という文脈で如何に変貌していったかについては、小熊英二『単一民族神話の起源』に詳しいが、本書においても、日本の朝鮮蔑視は根が深いことがわかる。
朝鮮通信使は、室町からはじまり、江戸末期にはすでに相手を一段低い存在とみなして対馬止まりとしていた。そして、約100年ぶりに朝鮮使節が東京(江戸)にまで来た1876年には、もはや、傲慢な優越意識が、朝鮮に対する侮蔑感を増幅してしまっていた。征韓論は、そのような上と下の意識のなかで醸成され、政治的に利用されていった。
もちろん、「やむを得なかったのだ」という議論として、ロシアや欧米という列強の脅威への対抗は無視できない。しかし、江華島事件(1875年)、東学農民軍の弾圧(1894年~)、日清戦争(1894年)・日露戦争(1904年)による朝鮮支配の強化、閔妃殺害(1895年)など、数十年の間に、単にパワー・ポリティクスというだけでは許されざる侵略行為を続けたのだった。そのことは、いまだ、日本人の意識のなかで顕在化しているとは言えない。
いっぽう、朝鮮においても、大院君、閔妃、高宗を含め、多くの為政者たちによる権力闘争や、外圧への対応の模索がなされていた。本書によれば、儒教的な政治支配のあり方が、近代となじまなかった側面は否めないようだ。しかし、やはりそれは、日本や他国による朝鮮侵略を正当化する理由にはならない。
●参照
井上勝生『明治日本の植民地支配』
中塚明・井上勝生・朴孟洙『東学農民戦争と日本』
小熊英二『単一民族神話の起源』
60年目の「沖縄デー」に植民地支配と日米安保を問う
尹健次『民族幻想の蹉跌』
小森陽一『ポストコロニアル』