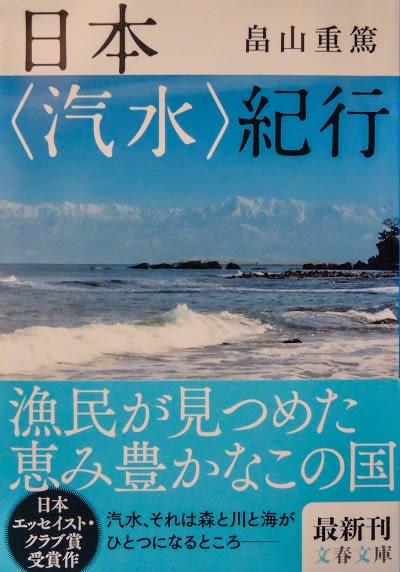アンドルー・レヴィタス『MINAMATA―ミナマタ―』をようやく観てきた。
映像が美しく、ドラマもまとまっていて良いエンタテインメント。チッソ社長役の國村隼は唇が薄いだけあって薄情なキャラに向いているし、もちろんスミス役のジョニー・デップはみごと。
・・・なのだけれど。やっぱりもやもやすることを備忘録として。
●初対面のスミスとアイリーン美緒子とがジャズクラブに行く場面で、「生音」として、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの「Moanin'」が流れる(同名のアルバムに収録されたヴァージョン)。映画の設定は1971年、アルバムは1958年。スミスもジャズ好きでロフトに住んでいたのだし、あまりにも雑。
●いかにも坂本龍一の音楽が流れてお涙頂戴、これには白ける。お仕事なの?たとえば秋吉敏子=ルー・タバキン・ビッグ・バンドが水俣に捧げた『Insights』でも使ったほうが1万倍良かったのでは。
●スミスが水俣で偶然出会った患者に気まぐれでカメラを贈ったため使うカメラが無くなり、水俣の住民たちがカメラを持ち寄るという設定。実際には新幹線で愛用のライカを盗難されたスミスに対し、付き合いのあったミノルタ宣伝部の社員が独断でSR-T101のボディ2台とレンズ3本を渡したのだった。だが、映画ではもともとミノルタを使っていたように描かれている(SR-1を使ってはいたはずだが無くしたものはライカ)。住民たちのカメラの中にSR系のミノルタが複数あるのも不自然で、当時の大衆機ならばたとえばペンタックスSP系やコンパクト機のほうが多かったのでは。それどころかステレオカメラさえもチラッと見えた(TDCステレオヴィヴィッドのように見えたがそんなものを田舎の住民が持っているわけがない)。
●スミスは沖縄戦の取材以来ひさしぶりの日本だという設定のようだが、実際には、1960年から日立製作所の仕事をもらい、いち企業のPRを超える作品として完成させた。これがスミスのキャリア形成にも金銭的にも大いに貢献した。映画はそのあとの1971年から。
●ミノルタとの付き合いや日立との仕事のことが映画で消されているのはなぜか。「ココロザシのある写真家やジャーナリズム vs. 巨大企業」という構図を映画で作りたかったからではないか。そしてエンドロールでは福島原発事故を含め「いまも続く構図」がアピールされる(その通りの側面はあるのだけれど)。スミスについては、富士フイルムのCMの契約をしておきながら「カラーフィルムは使ったことがない」と企業との付き合いに無頓着な雰囲気を強調している。そうでなければ映画でキャラが立たなかったのか。
●水俣病の実態や原因の追究は、原田正純、宇井純、石牟礼道子、土本典昭、川本輝夫、桑原史成を含め多くのひとたちによってなされている。それが映画ではどこにどう考慮されているのやら。もちろんドキュメンタリーではないから問題とまでは言えない。(とはいえ、僕も高校の図書館で宇井純『公害原論』を手に取ったことが社会や環境問題への関心のきっかけでもあったし、やっぱり気になる。)
●参照
森元斎『国道3号線 抵抗の民衆史』
『上野英信展 闇の声をきざむ』
『けーし風』読者の集い(31) 「生きる技法」としての文化/想像力
政野淳子『四大公害病』
原田正純『豊かさと棄民たち―水俣学事始め』
石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』
『花を奉る 石牟礼道子の世界』
土本典昭『水俣―患者さんとその世界―』
土本典昭さんが亡くなった
工藤敏樹『祈りの画譜 もう一つの日本』(水俣の画家・秀島由己男)
鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』
佐藤仁『「持たざる国」の資源論』(行政の不作為)
桑原史成写真展『不知火海』
桑原史成写真展『不知火海』(2)


阿部久二夫「カメラを盗まれた写真家ユージン・スミスのSR-T101」(『季刊クラシックカメラ』No.14、2002年)