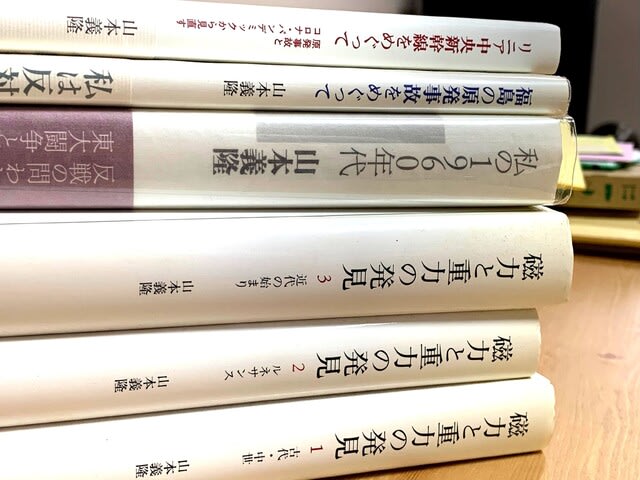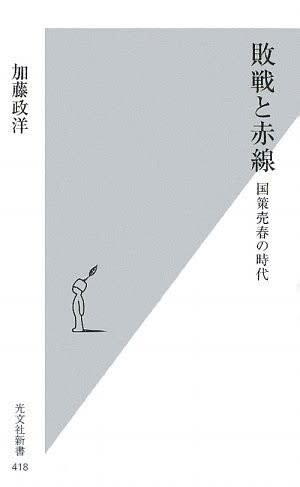東京琉球館で太田昌国さんのトーク(2024/11/29)。先ごろ亡くなった弁護士の大谷恭子さん、フランス文学者の鈴木道彦さんに関する話。

大谷恭子さんは全共闘世代、ブントのメンバーでもあった。たまたま脳性麻痺の小学生・金井康治の建造物侵入事件(1977年)の弁護を引き受け、そのことが彼女の弁護士生活を変えた。大谷さんのようなひとたちの地道な努力が、国連の障害者権利条約(2008年発効)、日本の障害者差別解消法(2013年制定)に結び付いた。2021年には民間企業にも配慮が義務付けられた。太田さんはこの社会を「インクルーシブ」(包摂的)なものと書く。
その後大谷さんは永山則夫の弁護団にも加わり、死刑廃止論者となる。永山は極寒の地に生まれ酷いネグレクトを受けた少年時代を過ごした。ひとの背景を鑑みることなく少年犯罪も死刑も誠実に考えることはできない。大谷さんはそれを追求した。
フランス文学者の鈴木道彦さんがなぜ小松川事件(1958年)や金嬉老事件(1968年)に関わったのか。鈴木さんは「李珍宇はジャン・ジュネだ」と言ったという。娼婦の子として生まれたジュネもまた過酷な少年時代を過ごした。
個の事情や背景はそれぞれ異なるものの、大谷さんや鈴木さんの残した論考を参照しつつ、太田さんは「民族性を盾にしてなにかを語ることは危険だ」と言う。昨今のクルド人たちに対する言説もまた、と。

●太田昌国
太田昌国の世界 その68「画家・富山妙子の世界」
太田昌国『さらば!検索サイト』
太田昌国の世界 その62「軍隊・戦争と感染症」
太田昌国の世界 その28「「従軍慰安婦」論議の中の頽廃」
太田昌国の世界 その24「ゲバラを21世紀的現実の中に据える」
太田昌国の世界 その15「60年安保闘争後の沖縄とヤマト」
60年目の「沖縄デー」に植民地支配と日米安保を問う
太田昌国『「拉致」異論』
太田昌国『暴力批判論』
『情況』の、「中南米の現在」特集