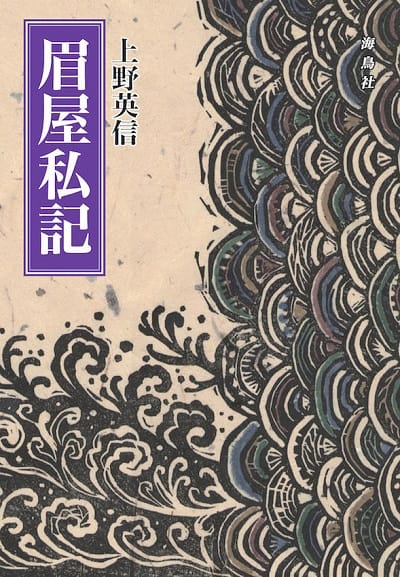剛田武さんにお誘いいただき、西麻布のスーパーデラックスへ。ノイズミュージックにはほとんど縁がなかったが興味津々。
■ .es(ドットエス)


橋本孝之 (as, harmonica)
sara (p)
橋本さんはハーモニカを吹き始める。フレーズではなく、音色に偏執し、音色が次第に変質してゆく。そのことは音数が多いアルトサックスでも同様であって、情を排除したところに独自のサウンドがあった。
相手が情という共感の道がない異星人であれば、サウンドの雰囲気を創出し左右するのは、saraさんのピアノなのだった。いつどこに居るのかという美しいパッセージは、ときにパーカッションともなった。多くの聴衆は息を呑んでこのデュオの緊張感を受け止めていた。
■ INCAPACITANTS
T.美川 (electronics, vo)
コサカイフミオ (electronics, vo)
おもむろに凄まじいノイズが発せられた。ふたりの前のテーブルには多数のノイズ発生機器が置かれ、箱を両手に持って、躍るようにフィードバックを効かせ、凄まじいノイズをさらに凄まじいものにしてゆく。会場は天井知らずでヒートアップしてゆき、怪人が叫び、両手を突き上げ、昇天し、遂にはテーブルに倒れ込んだ。
いつの間にか顔が勝手に笑っていた。もろもろのものが解毒されたようですっきりしたが、耳鳴りがはじまった。
■ グンジョーガクレヨン
宮川篤 (ds)
組原正 (g/vo)
前田隆(b)
中尾勘二 (tb)
橋本孝之 (as, harmonica, 尺八)
女装した組原さんがギターを弾き何やらを歌う。凶区か狂区か、その創出はエフェクターのトラブルによって一旦は消えた。しかし全員が登場し、また異なる形で顕出してみせた。全員が基底音であり露顕音である。
宮川さんのドラムスは、ひとつながりのものではなく、その都度変わる外敵に対して形作られるものだった。そして、フロントに並んでいることが奇妙に思える橋本孝之・中尾勘二(もっとも、こんど中尾さんと共演するから観に来たという橋本英樹さんによれば、いやそれは前からなのだということである)。異形生命体たる橋本さんはサウンドに亀裂を入れ続け、トロンボーンに集中した中尾さんは時空間をマジメに歪め続けた。
Fuji X-E2、XF60mmF2.4(撮影許可をいただいたのにすぐ電池切れトホホ)
◇
会場では、写真家の中藤毅彦さんが撮影していた(どんなものになるのだろう)。またGaiamamooさんも働き手として居て、こんどスペインにツアーに行くのだと話してくれた。
●参照
鳥の会議#4~riunione dell'uccello~@西麻布BULLET'S(2015年)(橋本孝之、コサカイフミオ参加)
橋本孝之『Colourful』、.es『Senses Complex』、sara+『Tinctura』(2013-15年)
中尾勘二@裏窓(2015年)
大島保克+オルケスタ・ボレ『今どぅ別り』 移民、棄民、基地(中尾勘二参加)
嘉手苅林次『My Sweet Home Koza』(中尾勘二参加)
船戸博史『Low Fish』(中尾勘二参加)
ふいご(中尾勘二参加)