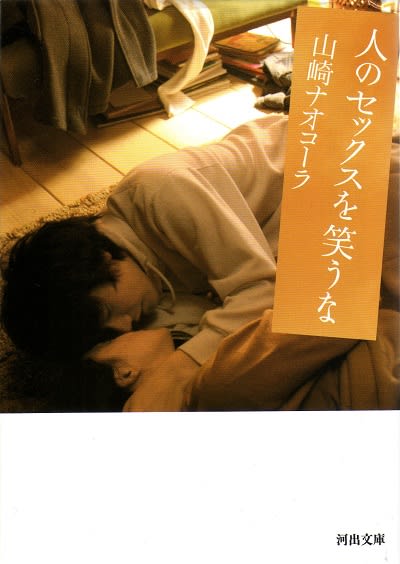バンコク行きの機内で、『藤田省三セレクション』(平凡社、2010年)を読む。

藤田省三は、丸山眞男の弟子筋に位置づけられる思想家である。最近では、徐京植が、「根こぎ」という言葉など、全体主義批判としての藤田の文章を取り上げている。本書は、彼の1950年代から晩年の90年代までの膨大な論考から、いくつもの興味深い文章を集めたものである(ほとんどは、みすず書房版の全10巻の著作集を底本にしている)。ひとつひとつの文章が刺戟的で面白い。
「天皇制国家の支配原理 序章」(本編含め、最近、みすず書房から新装版が出された)では、「天皇制国家」ではなく「天皇制社会」の独特な特質を説く。それによれば、日本が近代国家を構築せんとするにあたって、天皇制は、国家システムの形として採用されたばかりではなく、意図的に、法や規則や論理を疎外するものとして位置づけられていた。端から制度ではなかった、のである。法ではなく、人格として、心情として、原理として、すべてのミクロコスモスに浸透させた結果、何が生まれたか。決定は遍く論理ではなく解釈と調整によりなされ、その決定者はどこにも姿を見せない社会である。それが、生活秩序にも官僚機構にも見られる大小無数の天皇制社会であるとする。
「かくして官僚機構の縦の階層性が、客観的規則によってではなく人格的・直接的に構成されるや、機構内部の系統的セクションは必然にクリーク(clique 徒党)と化し、それらの間の相互関係は、絶対的倫理的意思の独占をめぐって深刻な抗争を展開する。」
「理論人の形成―転向論前史」も面白い。ここでは、日本共産党の活動史において多く見られた「転向」なるものの正体を、少し距離を置いて眺めようとする。獄中で転向した面々も、ソ連共産党に否定された福本和夫の「福本イズム」も、ヴィジョンと現実との乖離をどのように自己の中で処理するかの違いにすぎない。
「「プロレタリア民主主義」の原型」では、レーニンの苛烈な論理構造と言動を賛美する。あるいは、レーニンという個人の枠を超えた歴史においては、その理想が現実化されないことは当然であると言っているようだ。
「維新の精神」では、明治維新をもたらしたものを考えている。維新を維新たらしめたのは、国家単位での動きではなく、無数の論議と無数の横行の連結であった。トップダウンのメカニズムではなく、国家なるものへの問いを含めた、ぎりぎりの条件下での結果であったのだ、とする。そうしてみれば、まるで政権交代を「維新」であるかのように喧伝し、何年も経たないうちに実はヴィジョンなどなかったのだという馬脚をあらわす現代の政治家にこそ当てはまる指摘なのではなかろうか。
「従って、今日の日本で「現実主義」というイズムを売り物にする多くの知名人は、この「政治的リアリズムの精神的基礎」をさっぱり御存知ないために、かえってしばしば政治的リアリズムを喪失している。リアリズムのない「現実主義」という滑稽な姿は勿論維新の精神とは無縁である。」
「松陰の精神史的意味に関する一考察」では、吉田松陰が如何にヴィジョンの人ではなく行動の人であったかを描く。理論によるリードではなく、矛盾だらけであったとしても、行動によって多くのフォロワーをリードし、そして罰された人物ということである。何だか、先ごろ評伝を読んだ徳田球一のことを思い出してしまった。
1985年に書かれた「「安楽」への全体主義」においては、発展後の現代社会にあって、全体主義へのヴェクトルがそこかしこに見え隠れすることの恐ろしさを指摘している。かつての国家権力による、気にいらぬものの排除と地ならしではない。視線は、私たちの内部に向けられている。いやむしろ、「天皇制国家の支配原理」において説いているように、端からファシズムは「みんなのもの」であったということか。
「・・・不快の源そのものの一斉全面除去(根こぎ)を願う心の動きは、一つ一つ相貌と程度を異にする個別的な苦痛や不愉快に対してその場合その場合に応じてしっかりと対決しようとするのではなくて、逆にその対面の機会そのものを無くして了おうとするものである。そのためにこそ、不快という生物的反応を喚び起こす元の物そのものを全て一掃しようとする。そこには、不愉快な事態との相互交渉が無いばかりか、そういう事態と関係のある物や自然現象を根こそぎ消滅させたいという欲求がある。恐るべき身勝手な野蛮と言わねばならないであろう。」
●参照
○徐京植のフクシマ(藤田省三の「安楽全体主義」に言及)
○尹健次『民族幻想の蹉跌』(藤田省三の天皇制国家論に言及)