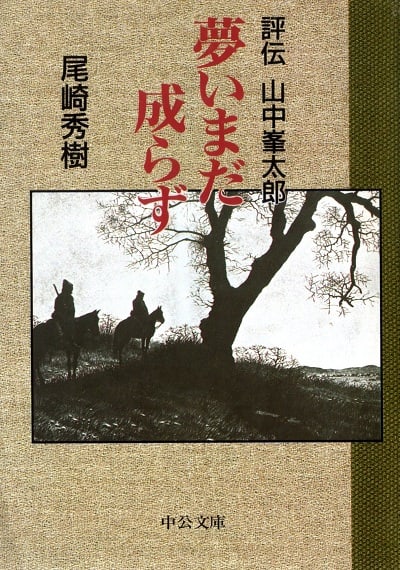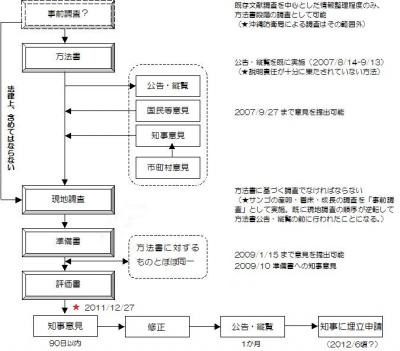ベルナルド・ベルトルッチ『ラストエンペラー』(1987年)を観る。大ヒットした映画だが、実は観るのははじめてだ(どうも昔から宣伝されるものに反発する癖があって)。

シナリオ集の表紙
公開版よりも長いディレクターズカット版、219分と長いが、ヴィットリオ・ストラーロの色素が濃縮して沈んだようなカメラの素晴らしさ(同じベルトルッチの『暗殺のオペラ』も印象的だった)もあって、まったく飽きない。清朝末期から中華民国誕生、国民党支配、日本の侵略、満洲国建設と崩壊、戦後の中華人民共和国建国、文化大革命の開始まで、愛新覚羅溥儀を巡る激動の歴史を数時間で語ることはどだい無理なのであって、もっと長くてもよかったくらいだ。ただ、全員が英語で喋るのはやはり余りにも不自然。
溥儀役のジョン・ローンは格好良すぎて、(虜囚後もひとりで靴も履けないし、歯磨き粉も出せない生活無能力ぶりは描かれているものの)大日本帝国、中国共産党と、強者に寄り添ってゆくカメレオンのような屈折した個性が充分に表現できているとは言えない。また、英国帰国後に『紫禁城の黄昏』を書く雇われ教師レジナルド・ジョンストン(ピーター・オトゥール)も立派すぎて、「溥儀と、まさにナルシシズムの合わせ鏡」(入江曜子『溥儀』)のような奇妙な存在感も希薄だ。さらには、甘粕正彦(坂本龍一)もやはり上品すぎるのであって、日本が醸成していた侮蔑的視線も充分に感じさせるものではない。
紫禁城を追われたあと、溥儀は日本占領下の天津に蟄居し、さらには満洲国皇帝におさまることになる(出席者があまりにも少ない空虚な建国イベントの描写は面白く、ここで甘粕はドイツ製の左手で巻き上げる一眼レフカメラ・エキザクタを使っている)。このあたりの空っぽの権力構造をもう少し丁寧に追ってほしかったところではある。溥儀の弟・溥傑に嫁ぐ日本人・嵯峨浩なんて、折角妊娠した様子で登場し、狂気に走る溥儀の妻・婉容を不気味そうに見つめるというシーンが挿入されているのに、日本人の血を混ぜて版図を広げるというおぞましさは忘れられているのだ。それに、川島芳子(戸田恵子)が出ているのだと後で確認したが、まったく登場場面の記憶がない。
などと、ケチばかり書いているが、良く出来た映画だった。要は盛り込み過ぎなのである。
●参照
○入江曜子『溥儀』
○小林英夫『<満洲>の歴史』
○満州の妖怪どもが悪夢のあと 島田俊彦『関東軍』、小林英夫『満鉄調査部』
○菊池秀明『ラストエンペラーと近代中国』
○林真理子『RURIKO』
○四方田犬彦・晏妮編『ポスト満洲映画論』