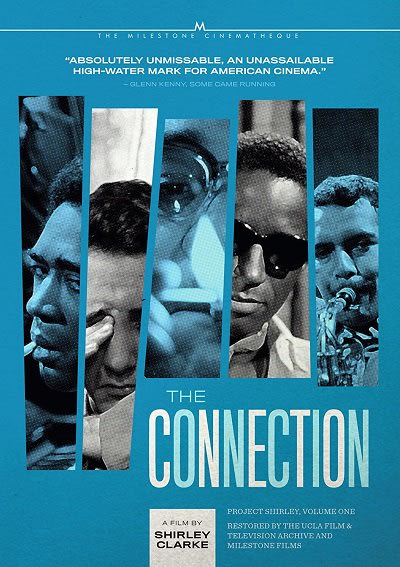ウィリアム・パーカー『Essence of Ellington / Live in Milano』(AUM Fidelity、2012年)を聴く。

William Parker (b)
Hamid Drake (ds)
Dave Burrell (p)
Kidd Jordan (ts)
Dave Sewelson (bs)
Sabir Mateen (cl, ts)
Rob Brown (as)
Darius Jones (as)
Ras Moshe (ss, ts)
Steve Swell (tb)
Willie Applewhite (tb)
Roy Campbell (tp, flh)
Matt Lavelle (tp)
Ernie Odoom (vo)
「6、7歳のときからデューク・エリントンを聴き親しんでいた」というウィリアム・パーカーによる、エリントン・プロジェクト2枚組。もちろんここで展開されているのはウィリアム・パーカーの音楽であり、喜怒哀楽とわけのわからない生命力をここぞとばかりに爆発させるエリントンのジャングル・サウンドではない。だが、パーカーにこのメンバーであり、悪いわけがない。
1枚目。まずは「Portrait of Louisiana」では、泡立ちひっくり返るようなキッド・ジョーダンのテナー、過度な破裂音を出さずしてエネルギーを最大限に放出させるハミッド・ドレイクのドラムス。「Essence of Sophisticated Lady / Sophisticated Lady」ではひしゃげたようなデイヴ・セウェルソンのバリトンや、ひたすら擾乱を起こすデイヴ・バレルのピアノ。「Take The Coltrane」での高音を攻めるサビア・マティーンのテナーも良い。重戦車のようにサウンドを駆動するパーカーはやはり最強である。
2枚目。「In A Sentimental Mood」では、デイヴ・バレルの美しく響かせるピアノに続いて、伸びてびりびりと震えるダリウス・ジョーンズのアルト。「Take The A Train」ではまた大勢で盛り上げていて、そのまま「Ebony Interlude」においてマティーンのクラリネットとのデュオになったときのパーカーのベースは、超重量級のくせに軽やかに舞っている。「Caravan」では、硬質なプラスチックのような艶のあるロブ・ブラウンのアルトソロに耳を奪われる。ここでもサウンドを力強く駆動するパーカーのベースがとにかく素晴らしい。そしてオリジナルの「Essence of Ellington」で、エリントンらしく賑々しく締めくくる。
編成のことは置いておいても、2015年の来日時には、このようなパーカーを聴きたかったのだ。
●ウィリアム・パーカー
スティーヴ・スウェル『Soul Travelers』(2016年)
エヴァン・パーカー+土取利行+ウィリアム・パーカー(超フリージャズコンサートツアー)@草月ホール(2015年)
イロウピング・ウィズ・ザ・サン『Counteract This Turmoil Like Trees And Birds』(2015年)
トニー・マラビー『Adobe』、『Somos Agua』(2003、2013年)
Farmers by Nature『Love and Ghosts』(2011年)
ウィリアム・パーカー『Uncle Joe's Spirit House』(2010年)
DJスプーキー+マシュー・シップの映像(2009年)
アンダース・ガーノルド『Live at Glenn Miller Cafe』(2008年)
ブラクストン、グレイヴス、パーカー『Beyond Quantum』(2008年)
ウィリアム・パーカーのカーティス・メイフィールド集(2007年)
ロブ・ブラウン『Crown Trunk Root Funk』(2007年)
ダニエル・カーター『The Dream』、ウィリアム・パーカー『Fractured Dimensions』(2006、2003年)
ウィリアム・パーカー、オルイェミ・トーマス、ジョー・マクフィーら『Spiritworld』(2005年)
ウィリアム・パーカー『Luc's Lantern』(2005年)
By Any Means『Live at Crescendo』、チャールズ・ゲイル『Kingdom Come』(1994、2007年)
ウィリアム・パーカーのベースの多様な色(1994、2004年)
Vision Festivalの映像『Vision Vol.3』(2003年)
ESPの映像、『INSIDE OUT IN THE OPEN』(2001年)
ペーター・コヴァルト+ローレンス・プティ・ジューヴェ『Off The Road』(2000年)
アレン/ドレイク/ジョーダン/パーカー/シルヴァ『The All-Star Game』(2000年)
ウィリアム・パーカー『... and William Danced』(2000年)
エバ・ヤーン『Rising Tones Cross』(1985年)
ウェイン・ホーヴィッツ+ブッチ・モリス+ウィリアム・パーカー『Some Order, Long Understood』(1982年)
『生活向上委員会ニューヨーク支部』(1975年)