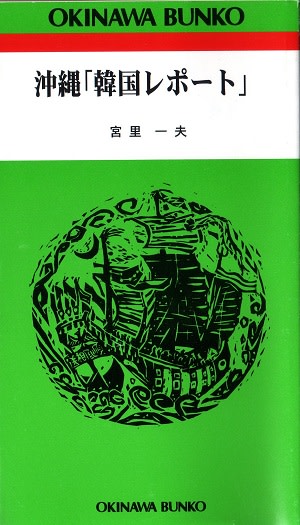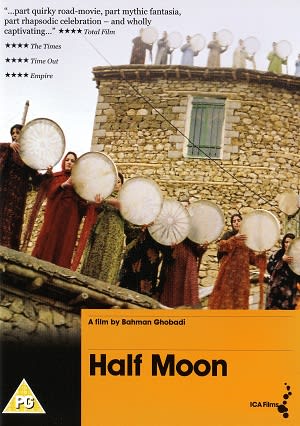所用で札幌に足を運んだ。機内で『世界』最新号を読む。特集は「巨大な隣人・中国とともに生きる」と題されている。
■行天豊雄「豊かで強い中国とどう向き合うか」
高度成長(5-10%)はあと10年は続く、なぜなら潜在需要があり、都市への人口流入がまだ続き、貯蓄率が高いため投資能力があり、不動産バブルを処理できる税収の余力があり、そのバブルも慎重に対応しているので一気にはじけることはない、といった分析。また人民元がアジアの基軸通貨になるのはまだ先だと見ている。
■樊勇明「成長パターン転換の大局面に立つ中国経済」
景気の減速を示す指標が多く提示されている。中国経済が危いバランスのもとに成立しているが、そのことは中央も認識しており、地方の実情を踏まえて安定成長に持っていく方向だという。興味深いのは不動産バブルの分析であり、その原因を地方政府と不動産業者との癒着にあるとしている。すなわち土地は国のもの、利用するための土地使用金は地方政府に財源となっているが、いまやそのサイクル(土地使用金の増加、さらに行われる都市開発、債務の増大)がかなりアンバランスなものになっている。
さらに、輸出業への逆風、労働人口の豊富から不足への転換にともなう歪みといった分析に関しても、上の論文に比べより実証的で評価できる。
■童適平「中国経済の持続成長に何が必要か」
安定成長のためには消費を促進しなければならないが、実際には、インフラ投資がいびつに膨らんでおり、また都市と農村の格差が拡大し続けているという分析。上の樊論文とは矛盾はしていない。内陸の安くいくらでもある労働力を沿岸が吸い上げる構造を、マクロ的・静的に評価することには限界があり、これが長く続くことはない、ということである。
消費が圧迫されているのは、社会保障(医療費の患者負担率は日本の10%台前半と比較して極めて高い、50%前後!)、教育費負担、住宅価格高騰のためでもあり、加々美光行のいう「社会権」要求の声がますます高まるだろうと読むことができる。
■岡田充「中国―台湾 ECFAがひらく新潮流」
中国と台湾との経済統合が進んでいる(チャイワン)。著者のいう「第三次国共合作」という言葉が適切なものかどうかはともかく、海峡を越えた武力行使は限りなくゼロに近いとする分析は納得できる。対ロシア、対中央アジアも含め、関係の好転による果実をこそ求めているのだ、ということだ(堀江則雄『ユーラシア胎動』)。中国脅威論を軍事的にのみ語るメディアの知的水準の低さよ、ということになるだろうか。
■朱建栄「上海万博から見る中国の現在と未来」
中国との関係が悪化した小泉政権が、万博開催地の投票において中国に票を入れなかったことはともかく、その延長にある「反中」報道がいまだ尾を引いている。日本館が国旗を掲揚しなかったのは過敏な自粛だ(上海環球金融中心の形が変わったことを想起させられる)、いや強制だ、などという報道がなされた。実は通常の習慣だったということで、中国側の担当者からは「フランス、イギリスなどのように国旗を掲揚しない国には別にクレームをつけないし、なぜ日本国内で自分だけがいじめられているような騒ぎになったのか理解できない」との意見も出たという。
■松田康博「「不確実性」としての中国に向き合う」
ここでも、「中国脅威論」をベースとした対中政策(ハード・バランシング)はもはや時代遅れだとの指摘がある。相互依存関係(ソフト・バランシング)が有効であり、何か綻びが出てきても自然と対処できる仕組みが重要であるとする。
■遠藤誉「「網民」パワー 四億人の声が政府を動かす」
韓国では「ネチズン」、中国では「網民」。ネット原論の影響力は相当に大きいようであり、何と、意見表明手段のうちBBS人口は1.32億人、ブログ開設者の数は2.31億人(!!)。政府への圧力を加える結果も出てきているという。著者の考えでは、「網民」は多くの場合弱者の代弁者として言論を展開し、貧富の差が国家を危くしかねない中国にとって、民意を逆なでできないから、である。検閲やグーグルとの不和が常に話題となっているが、それを逆手にとったアナーキーなパロディも流行しているようである。
■麻生晴一郎「公民社会への道」
NGOへの規制強化が強まっているが、これは上の遠藤論文にあるネット規制と同様、その影響力が強まっていることを示している。
●現代中国論
○『情況』の、「現代中国論」特集
○加々美光行『裸の共和国』
○加々美光行『現代中国の黎明』 天安門事件前後の胡耀邦、趙紫陽、鄧小平、劉暁波
○加々美光行『中国の民族問題』
○竹内実『中国という世界』
○藤井省三『現代中国文化探検―四つの都市の物語―』
●『世界』
○「普天間移設問題の真実」特集(2010年2月)
○「韓国併合100年」特集(2010年1月)
○臨時増刊『沖縄戦と「集団自決」』(2007年12月)
○「「沖縄戦」とは何だったのか」特集(2007年7月)