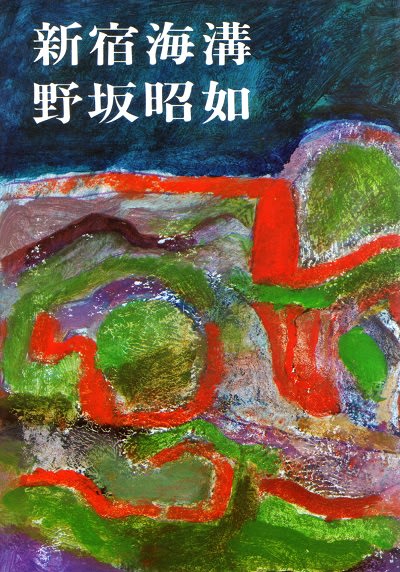J・M・クッツェーの新作『The Childhood of Jesus』(Viking、2013年)を読む。
クッツェーは南アフリカ出身のノーベル文学賞作家であり、ブッカー賞も2度受賞している。わたしは『夷狄を待ちながら』(1980年)と、ポール・オースターとの書簡集『Here and Now: Letters (2008-2011)』(2013年)を読んだことがあるだけだ。

モンゴルへの行き帰り、福岡への行き帰りと読み続けて、昨夜読了した。次の展開が気になってしまうストーリーテリングの技は、さすがである。
新しい地に、着の身着のまま辿り着いた男シモン。彼は、両親不明の幼児デイヴィッドを連れ、その母親を探しだすと心に決めていた。シモンは、難民収容施設を経て、港湾での力仕事に就き、友人や仲間も見つける。ある日、散策に出かけた里山で、テニスをしている女性イネスを目撃し、シモンは、彼女こそデイヴィッドの母親だと直感的に決めつける。隔離された環境で30歳近くまで過ごしてきた処女イネスはそれを受け容れるが、デイヴィッドを囲い込み、外の環境に接することを許さない。シモンの説得により、デイヴィッドは学校に通うようになるが、もはや自らの宇宙を持つデイヴィッドは、学校の社会から拒絶され、放逐される。当局はデイヴィッドを特別学校に強制的に入れようとし、シモン、イネス、デイヴィッドはそれを拒否する。そして、彼らは車に乗って、北へのあてのない旅に出る。見えてきたのは、再び、過去が関係のない新しい地であった。
またしても異人となることを繰り返す、終わりのない物語。読了後、肩すかしにあったような脱力感を覚えた。
この奇妙な物語世界は何だろうか。もちろん、タイトルといい、登場人物たちの名前といい、キリスト教に直接紐付けた寓話ではある。しかし、社会秩序や、性欲や、食糧や、言語や、労働の目的などを巡る哲学的な会話は、浅くて薄い。
港湾の倉庫にネズミが多すぎることについて、シモンは清潔にしてネズミを駆逐すべきだと主張する。それに対し、労働管理者は、食糧がこぼれていることによって、ネズミが生きているのだと語る。ネズミを生かすためにつらい労働をしているのか、いや世界はそのように己だけのために存在するのではない、というわけだ。面白くはあるが、たとえば、埴谷雄高『死霊』における生態系についての対話のほうが、遥かに思索的であり、狂気と笑いに満ちているものだった。
それとも、このペラペラの哲学的対話も、制度や規範に受容されない者たちの存在も、そして異人としての絶対的な出現も、固陋で自由からはほど遠い現代社会と宗教の歴史を、相対化して提示するためのものだったのだろうか。
●参照
○ポール・オースター+J・M・クッツェー『Here and Now: Letters (2008-2011)』