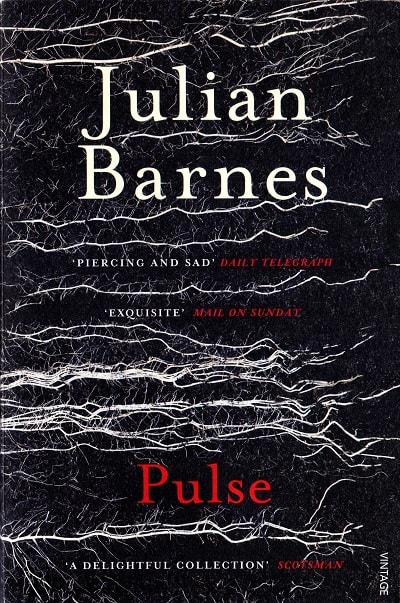ポール・オースター『最後の物たちの国で』(白水社、原著1987年)を読む。昔友人に借りていい加減に読んだものなので、あまり内容を覚えていなかったのだ。ブックオフで105円、良い買い物だった。

この小説はオースター初期の作品であり、『ガラスの街』、『幽霊たち』、『鍵のかかった部屋』という<ニューヨーク三部作>の直後に書かれている。そのためか、とてもシンプルな構成だ。何しろ、最初から最後まで、ある女性の書く手紙による語りだけで成立させている。
兄を追ってある国に入り込んだ女性。そこでは、すべてのものが次々と消えていき、ほどなく人びとは<それがあった>という記憶さえ完全に失くしてしまう。絶望と諦念が支配し、感情を失った者たちによる暴力を回避し、何も考えずただ目の前のことだけを淡々と処理し、生きつないでいくだけの世界。この喪失感たるや読んでいて怖ろしいものがある。
「私としては懸命に努力したのですが、なぜかいつもすべては失われてしまったのです。結局唯一思い出せるのは、自分がいかに懸命に努力したかということだけでした。物たち自体はあまりにも速く過ぎていき、私の目に止まると同時にもう頭のなかから飛び出してしまい、別のものがそれに取って代わるのですが、それらの物もまたたく間に消えてしまうのでした。いまの私に残っているのは、一個のかすみだけです。」
ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』では「虚無」が襲ってくるものの、物語の底流には大きな希望があった。小説世界から文字がひとつずつ無くなっていく筒井康隆『残像に口紅を』は、日常世界=言語世界の喪失を赤裸々に見せつけた作品だったが(何しろ、筒井康隆はワープロのキーボードに順次画鋲を貼り付けていったというのだ)、それは畏怖であり寂しさではなかった。むしろ、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』において、アルバイト先でジョバンニが活字をひとつひとつ拾っていくという茫漠な寂しさ、世界が活字でフィクショナルに出来ていていつでも活字の入った箱をひっくり返すだけで滅びてしまうような危うさ、その世界と共通するような印象を覚えた。
もちろんそれは読み手の勝手な気持ちではあるのだが、実際にこの後も、オースターは「綴られたノート」という物語をアンバランスに積みかさねていくメタフィクション(『オラクル・ナイト』や『Invisible』)を構築していく。さらには、それがひとつの小説のなかだけでなく、オースター自身の他の小説ともチャネルが作られていくことになる。その極致が、主人公のもとに次々にオースターの小説の登場人物たちが訪れるという怪作『Travels in the Scriptorium』だった。この『最後の物たちの国で』では、『ガラスの街』に登場する男・クインのパスポートが出てくるだけで、そのような自己言及はほとんど見られない。シンプルだというのはそのような意味でもある。
喪失感は後悔をも伴って現れる。たまらないな。
「私は思うのですが、人生には、誰も強いられるべきでない決断があります。とにかく精神に対してあまりに大きな重荷を課してしまう選択がこの世にはあると思うのです。どの道を選ぶにせよ、結局絶対に後悔することになるのであり、生きているかぎりずっと後悔しつづけるしかないのです。」
●参照
○ポール・オースター『Sunset Park』(2010年)
○ポール・オースター『Invisible』(2009年)
○ポール・オースター『Travels in the Scriptorium』(2007年)
○ポール・オースター『オラクル・ナイト』(2003年)
○ポール・オースター『ティンブクトゥ』(1999年)
○ポール・オースター『ガラスの街』新訳(1985年)